白菜の育て方

育て方の基本的なポイントと種付け育苗
大型の野菜である白菜ですが、プランターや鉢でもベランダ菜園でも栽培することが可能な野菜ですただ、病害虫の被害にあうこと多く、このことが育て方を多少難かしくしている面があります。
ですので、その点の対策をしっかりした育て方をしておけば初心者でも問題なく育てることが出来ます。白菜の育成に適した温度は18~20℃です。冬野菜らしく高温には弱く22~23℃以上になると成長に難が出て結球しにくくなります。
畑を選びには、連作障害があり2年ほど間を置く必要があります。日当たりのよい水はけのよい場所を選び害虫の被害にあいやすいので早期の対策が必要です。以上のようなポイントを踏まえたうえで栽培を始めます。
育て方は、まず苗を作ります。種付けの時期は8月終わりから9月の初旬です。培養土を入れた 3号ポットに種を3粒ずつ種付けして、うすく土をかけておきます。芽が出たら、寒冷紗で日よけをして高温にならないようにするため、直射日光が当たらないようにします。夕方ははずして夜露に当てるようにしましょう。
子葉が開ききったら成長の遅い株を間引いて2株にします。その後、本葉が2枚になったら、同じく成長の遅いものを間引いて1株にします。白菜は苗を作らず直播でも栽培することが出来ます。
植え付けとその後の育て方
白菜は植え付け時期が重要でその後の育成に大きく影響しますので植え付けの時期が遅れたり根を傷めたりすると根付きが悪かったり葉の付きが少なかったりしますので慎重に行います。
まず、苗を植え付ける2週間前に苦土石灰150g/m2と堆肥3kg/m2を入れてよく耕しておきます。その後植え付ける1週間前に元肥として化成肥料120~150g/m2を入れて畝を作ります。植え付ける前日には根鉢を壊さないようにするため、ポットの苗に十分な量の水やりをしておきます。
畝に50㎝間隔で穴をあけ根鉢のまま植え付けていきます。この時、 植え穴は大きめにあけて、根鉢が見えるくらいに浅く植えます。葉の付け根を土で覆ってしまわないように気を付けましょう。
植え付けた後は株元に土を寄せて周囲の土を軽く抑えて安定させます。この後たっぷりの水を与えておきます。植え付けてからおよそ2週間ほどたったら化成肥料70~80g/m2を畝の中央部分に追肥を施してして土寄せしておきます。
この後、結球し始める前ぐらいに、畝の両端に化成肥料70~80g/m2を追肥して土寄せしておきます。白菜を直播で栽培する場合は植え付けるときと同じような畝を作り、8月中旬から下旬に、畝の幅が80cmくらいなら1条、120cmのものなら2条に、まき溝を作り、株間50cmをあけて種付けします。
溝の深さは1㎝程で一か所に5~6粒ずつ蒔いておき薄く土をかけておきます。雨で種が流れてしまわないように、切藁などで覆っておきます。芽が出たら、苗作りと同じように間引いていきます。プランターの場合は、面積が小さいこともあって直播よりは苗を作るか購入したほうが育てやすく失敗も少ないでしょう。
苗を選ぶ際は本葉の枚数が多いと根付きが悪いので本葉の数は4~5枚のものを選びます。この時点で害虫の卵や幼虫がついていることもあるのでよく確認して購入します。白菜の栽培で一番難しいと言われる害虫の対策ですが特に幼苗期は害虫の被害にあいやすいので注意が必要です。
この時期に害虫にあうと一晩で全滅することもあり害虫対策は必須の作業となります。育苗期から植えつけた後しばらくは寒冷紗を使ってトンネル掛けをして害虫から守るようにします。また、成長点を害虫に食害されると育成が止まり、結球しなくなります。このため結球が始まったら特に害虫の点検は毎日行うようにします。
水やりは植え付けた後から根付くまでは十分な量を与えます。根付いたかどうかは葉の育ちがよくなることでわかります。また、植え付けから大体2週間ほどたつと根付きます。根付いたら1回の水やりの量を控えるようにして、土の状態を見て乾燥した状態が続かないように適度な水やりを心掛けるようにします。
水が多いと軟腐病といった病気にかかりやすくなるので水やりには注意が必要です。また、水遣りの後や雨が降った後、土が流れてしまったときは土寄せをします。土寄せをしないと白菜は倒れてしまいます。結球時期の株を安定させるために土寄せは適宜行います。
なお、株間の根を傷つける恐れがあるので、土寄せは結球が始まる前までに行います。
結球し成長してくると外葉に黄色くなったものや害虫のために傷んでしまったものが出てきますので、このような葉は、早めに摘み取っておきます。これを放置しておくとそこから病気になったりまた、他の株まで病気が広がってしまいます。
白菜の収穫
白菜の収穫時期は、結球した頭の部分を手で押さえてみて頭がが固く締まっていれば収穫時期とみなします。防寒対策のとられた畑であればそのまま収穫せずに保存することが出来ますので使う量の分だけを収穫します。収穫方法は、結球部を斜めに倒して外葉と一緒に根元から刃物で切り取ります。
白菜の歴史
白菜は、アブラナ科の野菜で、生息地は他のアブラナ科の野菜類と同様に、ヨーロッパの北東部からトルコ にかけての地域でだと考えられています。この野生種が中央アジアを経由して中国に伝わり、中国で改良されました。そのことから原産地は、中国の青島(チンタオ)ともいわれています。
日本での歴史は意外に浅く、日本に入ってきたのはは明治8年東京で開かれた博覧会に中国からの出品されたことがきっかけで初めて紹介されることになりました。その後、日清戦争・日露戦争を経験して日本の農村出身の兵士たちが、中国でこの野菜を食べたことから種が持ち込まれることになりました。
ここから日本の白菜の栽培と利用が始まることになります。ところが中国から輸入した種子からの栽培は成功するのですがその成体から種を取って栽培しようとしても成功しませんでした。どれも白菜にならずほかの植物に成長してしまい栽培は成功しませんでした。
この理由が全く判明しなかったため長らく栽培するための種は中国からの輸入に頼ることになりました。この後長い間の研究の結果、日本での在来種であるアブラナ科の他の野菜との花粉を自然受粉してしまい純粋な白菜にならなかったことが分かりました。
この理由を知るために20年もかかったと言われています。
白菜の特徴
西洋のキャベツの元になったともいわれる東洋を代表する葉野菜です。味は癖がなくやや甘い味がします。この癖のなさが様々な料理に利用しやすく大変多くのレシピが考案されています。
漬物から鍋物、サラダ、スープ,炒め物など和、洋、中華とどのような料理のジャンルにも登場します。また、カロリー値も低くダイエットにもよく利用されています。旬は11月下旬から2月ごろの晩秋から冬にかけてです。
また、霜にあたると繊維がやわらかくなり風味も増し、鍋の季節でもあるこの時期は甘みが増して特に美味しいとされています。しかし、最近ではトンネル栽培という作物の上にトンネル状の覆いを付ける育て方によって、春から初夏の収穫も盛んになってきましたので、冬の野菜というよりも年間を通じて手に入る野菜となっています。
栽培のためのとしての白菜は、野生種からそのまま進化した物ではなく、かぶとツケナを交配させて中国でつくられたと考えられています。原産地である中国では大まかに3種類ほどに大別されますが、気候と風土の関係から、日本においては山東型といわれる一種類のみが定着しています。
この種の株の形態としては結球性、半結球性、不結球性に分けられ、主なものは結球型です。現在での栽培品種は主なものだけでも150種を超えます。
野菜の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:漬け菜類の育て方
タイトル:タアサイの育て方
タイトル:ハクサイの育て方
タイトル:キャベツの育て方
タイトル:カリフラワーの育て方
-

-
ウツボグサの育て方
中国北部〜朝鮮半島、日本列島が原産のシソ科の植物です。紫色の小さな花がポツポツと咲くのが特徴です。漢方医学では「夏枯草」...
-

-
プテロスティリスの育て方
プテロスティリスは、オーストラリアの南東部が主な生息地であり、ニュージーランドやニューカレドニア、パプアニューギニアと言...
-

-
ガーベラの育て方について
ガーベラは、キク科の花であり、毎年花を咲かせる多年草です。園芸では、鉢花や切り花などに広く利用され、多数の園芸品種が存在...
-

-
ヘチマの育て方
熱帯アジアを生息地とするインド原産の植物です。日本には中国を通して江戸時代に伝わったと言われています。ヘチマは元々、果実...
-

-
ダーウィニアの育て方
ダーウィニアの特徴を挙げていきます。まずは、植物の分類ですが、ダーウィニアはダーウィニア属のフトモモ科に属します。このダ...
-

-
ボロニアの育て方
ボロニアはミカン科、ボロニア属になります。ボロニアは、3月から4月にかけて綺麗な花を咲かせる樹木になります。ですので、寒...
-

-
ナンブイヌナズナの育て方
ナンブイヌナズナは日本の固有種です。つまり、日本にしか自生していない植物です。古くは大陸から入ってきたと考えられますが、...
-

-
レプトシフォンの育て方
この花についてはハナシノブ科、リムナンツス属になります。属に関しては少しずつ変化しています。園芸における分類としては草花...
-

-
アナガリスの育て方
ギリシア語で「楽しむ」や「笑う」を意味する言葉、「アナゲラオ」が名前の由来といわれているアナガリスは、スペインやポルトガ...
-

-
ティアレ・タヒチの育て方
ティアレ・タヒチのティアレとはタヒチ語で花という意味があります。つまりティアレ・タヒチはそのままタヒチの花という意味の名...




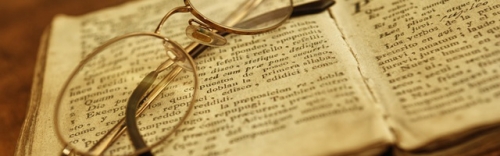





白菜は、アブラナ科の野菜で、生息地は他のアブラナ科の野菜類と同様に、ヨーロッパの北東部からトルコ にかけての地域でだと考えられています。この野生種が中央アジアを経由して中国に伝わり、中国で改良されました。そのことから原産地は、中国の青島(チンタオ)ともいわれています。