エラチオール・ベゴニアの育て方

育てる環境について
エラチオール・ベゴニアを育てる為に重要になってくるのが、温度です。熱帯、亜熱帯で生息していた植物ですが、暑い場所で育てると、葉っぱが火傷状態になり、上手く育たなくなってしまいます。ですから、日当たりは良い方が好ましいですが、日差しが強過ぎる場所で育てる事はお勧め出来ません。
適温となるのは、高い場合で20℃前後、低い場合で10℃前後となります。庭などに地植えをする場合、この程度の気温を保つ事が出来るかどうかを考えて、場所選びをする事が大切です。日差しが強い場所に植える場合、ホームセンターなどで販売されている遮光ネットなどを使い、
日差しを調整していく事がお勧めです。それにより、適温を維持しやすくなります。ただ、気温というのは突然変わる事もあるものです。ですから、栽培初心者などは、地植えから始めるのではなく、まずは鉢植えから育ててみる事がお勧めです。鉢植えの場合、春先から花が咲き終わる6月頃までや、
花が咲き始める9月から寒くなる前までは日当たりの良い場所で育てていく事がお勧めです。そして、夏場は、風通しの良い日陰などで育て、冬になると室内の日当たりの良い窓際で育てていく事がお勧めです。それにより、
一年を通じて良い温度を保ちやすく、何度も美しい花を楽しめるようになります。常に室内で育てていく場合でも、季節によって、温度や日当たりを意識して、置き場所を変えながら育てていくと、長く花を楽しめるようになります。
種付けや水やり、肥料について
エラチオール・ベゴニアは種からではなく、差し芽をして増やしていく事になります。挿し木のタイミングとしては5月から6月、秋の場合は9月頃となります。育てる際の水やりは、しっかりと行う事が大切ですが、水のやり方には注意が必要です。
鉢で育てる場合、底皿を使い、皿の中に水を溜めた状態で育てていく事がお勧めです。エラチオール・ベゴニアが育つ為には、しっかりとした水が必要となります。特に、天気がよく日当たりが良い状態で育てる場合、土の表面が乾いているようであれば午前中に多くの水を与える事が重要になってきます。
ただ、水を与える際に、葉っぱに水をかけてしまうと、葉っぱが弱ってしまう原因となります。ですから、上から水を与える場合、葉っぱを持ち上げ、その下の土に、水を与えるようにしていく事が大切です。その手間を考えると、鉢植えの場合、
ジョウロなどで水を与えるのではなく、底皿を使って育てる事が有効となってきます。更に、水の与え過ぎも良くない為、底皿を使わないで育てる場合、土の状態を確認しながら与える事が大切です。肥料は、冬場は10日に1回程度、液体肥料を与えるようにしていくと、
長く美しい花を楽しむ事が出来ます。ただ、肥料をこのペースで与えるのは、冬場や、花に元気がある時期で、気温が高くなり、エラチオール・ベゴニアが少し元気のない状態になっている場合、肥料を与えない方が、より元気に長持ちさせていく事が出来ます。
増やし方や害虫について
エラチオール・ベゴニアを増やしたいと考えた場合、挿し芽をしていきます。タイミングとしては、暑くなる前の5月頃が最適です。この時期に挿し芽をする事で、株が元気に若返り、夏を無事に越しやすくなります。挿し芽をする際は、茎の先端から数えて葉が3枚から4枚残る状態の枝を作り、
それを水はけの良い土に差していきます。そのまま1ヶ月程度育てると、根が出てくるので、根が出たタイミングで、鉢植えにしていくと、増やしていく事が出来ます。こうした挿し芽をすると同時に、しておきたいのが、切り戻しです。
エラチオール・ベゴニアは一度花が咲いた場所に、再び花が咲く事はないので、花が咲いた枝を切り、花が咲いていない枝や新しく伸びてきている芽を残すようにしていくと、次にまた再び綺麗な花を多く咲かせる事になります。葉っぱもまた、古いものは取り除いておく事で、
新しく綺麗な葉っぱが育ちやすくなります。ですから、良い状態を維持するには、花が咲き終わった後の切り戻しも重要になってきます。そして、切り戻しを行う季節に同時に行っておきたいのが、害虫の対策です。エラチオール・ベゴニアにはアブラムシが大量発生する事があります。
アブラムシは初夏頃から発生しやすくなる為、暑い季節には、アブラムシが発生していないか、確認しておく事が大切です。気づいて、早目に取り除く事が出来れば、大量発生を防いでいく事が出来ます。そして、それにより、長く、綺麗な花を楽しめるようになります。
エラチオール・ベゴニアの歴史
エラチオール・ベゴニアは、日本でもポピュラーな園芸植物のひとつで、鉢植えにして室内で楽しむ植物としても高い人気を誇ります。ベゴニアは、熱帯や亜熱帯地方が生息地となる植物です。ただ、原産自体は、熱帯や亜熱帯などの暖かい地域ですが、
現在、観賞用として親しまれているのは、ヨーロッパで栽培、品種改良を加えられ、日本に渡来したものです。ベゴニアにはいくつかの種類があり、そのうち球根ベゴニアとベゴニア・ソコトラナを交配させて、作られたのが、このエラチオール・ベゴニアです。
誕生は、19世紀後半のイギリスで、茎が立ち上がるという特徴がある事から、ラテン語で背が高いという事を意味する、エラチオールという名前がつけられました。更に、西ドイツで厚さや病気にも比較的強い、リーガスベゴニアという品種が作られました。
現在、これらは、どちらもエラチオール・ベゴニアとして扱われる事が多くなってきています。そして、実際にこれらの品種が日本に伝わったのは、1960年頃となっています。日本では、冬の室内に、暖かな色合いを添えてくれる花として、人気となりました。
11月11日の花になっていたり、冬にその姿を良く見る事から、冬の花というイメージを持つ人も多いでしょう。開花期が9月下旬から6月の為、冬にも楽しめる花の一つですが、元々が熱帯や亜熱帯の花の為、冬の寒さには弱く、冬に育てる際は、室温や育て方に注意が必要となってきます。
エラチオール・ベゴニアの特徴
エラチオール・ベゴニアの特徴は、小さく可愛らしい花が、多く咲き誇る事です。半八重や八重咲きが主流となっているその花は、小さいながらも、とても華やかで、小さな鉢植えでもしっかりとした存在感を誇ります。更に、室内に置く鉢植えとして、
人気が高い理由に、その色の鮮やかさがあります。色は、ピンク色やオレンジ色、赤や黄色、白とピンクのグラデーションなど様々ですが、花は暖色系をしているものが多い事が特徴です。暖色系をした小さく可愛らしいけれど、存在感のある花は、
葉っぱの濃い緑と美しいコントラストを見せ、殺風景になりがちな、冬の室内を優しく、そして華やかな状態へと変えてくれる効果があります。更に、多年草である為、しっかりと育てる事が出来れば、毎年、その花を楽しむ事が出来ます。
冬に良く見かける花の為、冬場に咲いているというイメージが強い花の一つですが、開花時期が長く、9月から6月頃まで花を楽しめるという特徴もあります。ですから、冬場に限らず、長く、室内で育てていく事が可能となっています。庭などに地植えをしていく事も可能ですが、
暑さにも寒さにもあまり強くない為、地植えをする場合、育てるのに適した場所を選んで植えていく事が大切です。良い場所に植える事が出来れば、冬を越し、それにより何度も花を楽しむ事が出来ます。気候に問題がある、場所に問題がある場合、寒くなると室内に持ち込める鉢植えで楽しむ事がお勧めです。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:球根ベゴニアの育て方
タイトル:オカトラノオの育て方
タイトル:エリカの育て方
-

-
観葉植物と盆栽の育て方と栽培時の注意点
空前のガーデニングブームにより、観葉植物や盆栽と言った家庭で楽しめる植物が流行しています。簡単な知識と栽培方法を用いて育...
-

-
サンキライの育て方
英名は「Chinaroot」で科目はサルトリイバラ科です。原産国は日本や中国、朝鮮半島、インドシナ半島などのアジアを主な...
-

-
サルナシの育て方
見た目が小さなキウイフルーツの様にも見える”サルナシ”。原産国は中国になり、日本でも山間部などを生息地とし自生している植...
-

-
モナルダの育て方
この植物に関しては、被子植物に該当し、シソ目、シソ科、ヤグルマハッカ属になります。非常に見た目がきれいな花が咲くことから...
-

-
レティクラツム・オウァリウムの育て方
この花についてはキツネノマゴ科、プセウデランテムム属となります。園芸上の分類としては熱帯植物です。また暖かいところに生息...
-

-
グズマニアの育て方
パイナップル科グズマニア属の観葉植物です。常緑性で、熱帯アメリカが原産です。背丈は25〜50cmほどで、横幅は35〜60...
-

-
パイナップルの育て方
パイナップルは日本でもよく目にする果物ですが、原産地はブラジルで、代表的な熱帯果樹の一つです。先住民によって果物として栽...
-

-
ブルーファンフラワーの育て方
ブルーファンフラワーはクサトベラ科スカエボラ属で、別名はファンフラワーやスカエボラ、和名は末広草といいます。末広草と名付...
-

-
ミント類の育て方
ミントは丈夫で育てやすいのが特徴です。家庭菜園でも人気があり、少しのスペースさえあれば栽培することが出来ます。ミントには...
-

-
フトモモの育て方
フトモモと呼ばれる果実をご存知でしょうか。これは、フトモモ科の常緑高木であり、原産は東南アジアで、漢字で書くと「蒲桃」と...




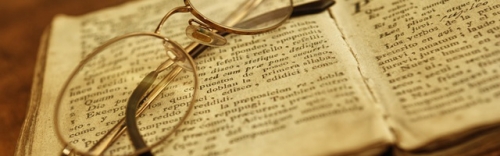





エラチオール・ベゴニアは、日本でもポピュラーな園芸植物のひとつで、鉢植えにして室内で楽しむ植物としても高い人気を誇ります。ベゴニアは、熱帯や亜熱帯地方が生息地となる植物です。