大根の育て方

大根の種付け
植物の多くは種付けを小さな容器にして、発芽したらプランターや花壇などに移植をするのですが、大根の場合は移植ができないので、初めから畑などに直接種付けをします。大根は下や横に成長していくので、畑はできるだけ深く耕しておき、プランターの場合には60cm以上の深さのものを使うようにします。土嚢袋や米袋でも栽培することが可能です。
使用する土は市販の培養土を使用したり、種付けの2週間前に畑の畝に苦土石灰を入れて耕しておき、1週間前に肥料を入れて耕しておいた土を使用します。耕す時には土の中に木片や石などがあると大根が「また根」になるので、取り除いておくようにします。大根の種付けの時期は春と秋の2回あり、春まきは4月下旬、秋まきは9月中旬に行います。
25センチから30センチくらいの間隔で4、5粒の種をまいていきます。種をまく部分に空き缶やビール瓶の底を押し当ててくぼみを入れておくと種がおきやすく、また種をまいた後は土を1センチくらいかぶせるのですがその時に軽く手で押さえることで水やりで種が流れたりせず落ち着くようになります。このようにして種付けをし、大根が発芽するまでこまめに水を与え、表面の感想を防ぐようにします。
大根が発芽したら
種をまいてから4、5日で発芽してきます。芽が出そろったら一回目の間引きを行います。一か所に4、5粒の種をまいているので、生育の良いものを3つ残して、ほかの芽を抜いていきます。抜くときには残す芽も一緒に抜けてきたり傷ついたりしないようにそっと根元を抑えるようにして抜くようにします。
次に本葉が1、2枚になったら二回目の間引きをします。二回目は双葉の生育がよさそうなものを2本残します。芽が近すぎて抜けない時はハサミを使って切り取るという方法もあります。二回目の間引きが終わったら一株当たり3gから5gの化学肥料をまいて追肥をし、そして土寄せを行います。
そして本葉が4、5枚になったら三回目の間引きで1本抜いて一本だけを残します。その残った株が大根を成長していきます。そして3回目の間引きの後にも2回目の間引きのあとと同じように追肥を行います。
間引きをして最終1本にすることで、よく生育しそうな大根が太く成長していくことになるので、大根の栽培には間引きがとても大切なことです。発芽してからの水やりは土の表面が乾いたとき、暖かい日中のうちに行います。夕方以降の水やりは病気にかかりやすくしてしまいます。
収穫時期は品種によって違い、種の袋にも示されているのでそれをしっかり確認しておきます。収穫のタイミングがずれると「す」が入ってしまうので注意が必要です。収穫時期の目安としては種まきから55日から60日経過し、草丈が25センチから35センチくらいになり、土から首が6、7センチ出てきたころが良いタイミングです。
病気と害虫の予防
多湿によって斑点細菌病や横縞症などの病気にかかりやすくなります。また春まきの場合はアオムシ、コナガ、アブラムシなどの害虫にも注意が必要です。時には散布剤の使用が必要になりますが、種を植える時に寒冷紗やマルチを使用することで害虫から防ぐこともできます。
大根の育て方のポイント
地面の奥に向かって成長していくので、有機質をたっぷりと含み、通気性がよく排水性にも保水性にも優れた土で栽培をすることが必要になってきます。また土の中に成長に障害をもたらすようなものがあれば取り除いておくこともよい大根が育つ要因になるので、栽培をするにはたっぷりと養分を含んだ土をしっかりと耕しておき、栽培のための準備を整えることが大切になってきます。
また10度以下になると花芽分化が起きて根の成長が止まってしまいます。生育の適温は17度から20度なので、種まきの時期を逃さないことやその時期に合った品種のものを栽培するようにすることも育て方のポイントとなります。
大根は暑さにやや弱く、冷涼な気候のほうを好むので、初心者なら秋まきのほうが成功しやすいといわれています。種をまいてから発芽まではたっぷりと水を与え、発芽したら三回間引きをして一本立てにし、追肥も二回行うことが育て方のポイントとなります。また発芽後の水やりは日中に行うことも上手な育て方のポイントとなります。
大根を上手に成長させるには土をいかに良く耕すか、水の与え方、肥料をしっかり与えるということが大切になってくということです。栽培の前半の土つくり、水やり、間引き、肥料が重要なポイントとなり、これらさえしっかりと丁寧にしておけば後は成長を見守るばかりです。
そして種まきと収穫時期のタイミングをずらさないように気をつけることで太くてまっすぐな大根に成長していくことでしょう。料理での利用用途が多く栄養をたっぷり含む野菜なので、家庭菜園で自分で作ることができれば、愛情がこもった新鮮なものをよりおいしく食べることができることでしょう。
大根の歴史
大根の原産地は地中海沿岸といわれていますが、いろいろな説もあります。紀元前2500年ごろにエジプトでピラミッドを通っていた人が食べていたという説もあります。そこからヨーロッパに広がり、中国を経由して日本に伝わってきました。
日本では「古事記」で登場しているので、古くから伝わっていたのですが、一般的に広がりを見せたのは室町時代のころのようです。日本では多くの人に好まれ、必要不可欠な野菜となっていて春の七草にも「すずしろ」という名前で出てきています。
大根の特徴
アブラナ科ダイコン属の一年草で、たくさんの品種があり、大きさや形も様々です。色も白いものだけではなくラディッシュなどの赤いものや海外では黒いものもあります。日本での生息地は全国各地ですが、特に多く生産しているのは千葉県、青森県、北海道で次いで、宮崎県や鹿児島県などの九州地方でも多く生産しています。
一般的に良く出回っているものは青首大根ですが、ほかに源助、三浦、亀戸、桜島、聖護院、守口、桃山など生産される地域の名前が付いたものもあります。根の部分は淡色野菜で栄養価は低いのですが水分が多く低カロリーで満腹感が得られる野菜です。
葉の部分は緑黄色野菜でビタミンCやビタミンE、カリウムやカルシウムをたっぷり含んでいます。βカロチンもかなり含まれていて栄養価が高いです。大根の辛み成分はアリルイソチオシアネートと呼ばれる成分で、おろすことで酸素と触れ合って精製されます。これには抗がん作用や抗菌作用があるとされています。
また大根にはジアスターゼと呼ばれるでんぷんの分解酵素を多く含んでいるので、消化を助け、胃酸過多や胃もたれなどに効果があリます。大根は料理での利用ほうがたくさんあります。
おろしやサラダで生食するほか、なべ物やや煮物料理、汁物料理に使われたり、干して乾物として長期保存をしたり、糠漬けや浅漬け、酢漬けなどの漬物料理として食べたり、さまざまな食べ方があるのでとても重宝されている野菜です。
和食の野菜というイメージがありますが、フレンチやイタリアンなどの洋食系でもよく使われている野菜なので、日本だけでなく世界中でよく食されている野菜なのです。
大根を保存する際には葉のほうから水分が失われていくので、葉の部分と根の部分に分けて保存するようにします。根の部分はラップでくるんだり濡れた新聞紙で包んでからナイロン袋に入れて冷蔵庫で保存します。
大根の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ダイコンの育て方
タイトル:ラディッシュの育て方
-

-
ケールの育て方
ケールはベータカロテンやルテイン、ビタミンCやカルシウム、食物繊維と言った非常に多種多様な栄養素を含むことから緑黄色野菜...
-

-
オカトラノオの育て方
オカトラノオはサクラソウ科の多年草で、その歴史としては中国を生息地としていたこの種類の植物が朝鮮半島を経由して日本に入っ...
-

-
イチゴの育て方
イチゴは比較的古くから人間に食されていた果物です。その歴史は石器時代にさかのぼります。農耕技術や養殖などを行う前から野生...
-

-
ペンタスの育て方
この花については、アカネ科、ペンタス属となっています。和名の方をとってクササンタンカ属とすることもあります。熱帯植物に該...
-

-
ペトレア・ボルビリスの育て方
ペトレア・ボルビリスは原産地がキューバ・ブラジルといった中南米の常緑蔓性高木です。和名では寡婦蔓(ヤモメカズラ)と呼ばれ...
-

-
ラベンダーの育て方
ラベンダーはシソ科の植物で、精油などにもよく使われています。実はこのラベンダーの精油はなんと古代ローマ時代から使われてい...
-

-
アレカヤシ(Dypsis lutescens)の育て方
アレカヤシという観葉植物をご存知でしょうか。園芸店などでもよく見かける人気のある植物です。一体どのような植物なのでしょう...
-

-
シネラリアの育て方
シネラリアはキク科の植物で、早春から春にかけての代表的な鉢花のひとつです。原産地は北アフリカの大西洋沖に浮かぶスペイン領...
-

-
イチゴノキの育て方
マドリードの旧市街の中心地には、「プエルタ・デル・ソル」(太陽の門)と呼ばれている広場が有ります。この広場はスペイン全土...
-

-
ユリオプスデージーの育て方
特徴として、キク科、ユリオプス属になります。南アフリカを中心に95種類もある属になります。園芸において分類では草花に該当...





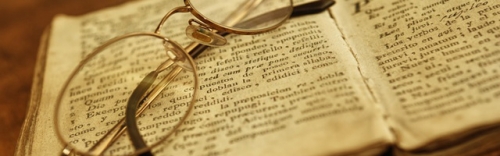





大根の原産地は地中海沿岸といわれていますが、いろいろな説もあります。紀元前2500年ごろにエジプトでピラミッドを通っていた人が食べていたという説もあります。そこからヨーロッパに広がり、中国を経由して日本に伝わってきました。