小かぶの育て方

小かぶの畑の準備と種付け
畑は、保水性とともに水はけのよい場所を選びます。種付けの2週間前程に1㎡あたり良質の完熟たい肥を1㎏と苦土石灰を同じく1㎡あたり100gの割合でよく混ぜ込み、高さ15~20㎝程に畝立します。
その1週間後には畑の1㎡あたりに、化成肥料を100gの目安で施してよく耕しておきます。通常種付けはかぶの種まきの最適温度である20度前後になる4月上旬から中旬に行います。畝の上にトンネル状にビニールなどで覆いをトンネル状にかけて栽培する育て方をするトンネル栽培をする場合は、2月中旬ごろに種付けします。
この場合は収穫も早くすることが出来ます。畝が乾いている場合は、ふんだんに水やりをして少し時間をおいて種付けします。種付けの前日に水やりをしておくとよいでしょう。菜園での育て方として、畝の幅が1mほどであれば、まき溝として20㎝の間隔を置いて4条ほど作り両端は20㎝程空けておきます。これより狭い畝の場合は列の数を減らすかばら蒔きをすることになります。
この条に2㎝程の間隔で種を蒔き1㎝程の土をかけておきます。種を蒔いた後は足で踏み固めるか、板で鎮圧しておきます。水が足りない場合は再度水やりをします。小かぶをプランターで栽培する場合は、用土を入れた後、やはり事前にふんだんに水をまいて、しばらく時間を置きます。用土が落ち着いたのを見はからって、深さ1㎝程で種を条まきします。
プランターでの育て方の場合は2条ほどになるでしょう。種を蒔く間隔は1㎝とし、乾燥を防ぐため新聞紙やキッチンペーパーなどを被せその上から多めに水やりをしておきます。
その後2~3日して芽が出たら新聞紙を取り除いておきます。発芽までは乾燥しないようにしなければならないので注意が必要です。プランターの場合も簡易的なトンネル状の覆いをつけるか、不織布等を使って覆いをするとよいでしょう。
小かぶの発芽後の育て方
小かぶの病気として考えられるのは、かぶモザイク病、べと病、白さび病、根こぶ病、黒腐病などがあります。連作は根こぶ病になりやすいので避けた方がよいでしょう。また、病害虫の対策は木酢液や食品由来の殺虫剤などを使って早めに駆除します。この害虫の予防のためにも不織布を種付けと同時にかけておくことが大切です。
しばらく成長して葉が触れ合うほどに込み合ってきましたら間引きを行います。トンネルを作っておいた場合はこの時期にはずします。本葉が1~2枚ほどになったら3~4㎝の間隔になるように間引きして調整します。この時、土寄せも行っておきます。
この間引きをしないと、かぶの玉がなかなか大きくなりません。プランターの場合もほぼ同様で、葉が触れ合うぐらいの時期に間引きを行います。ほぼ2~3回の間引きを行いますがこの時適宜水に液肥を混ぜて与えます。
間引きしたかぶも食べることが出来ますので捨てずに利用しましょう。水やりのポイントは、基本的には土が乾いてきたら水を与えます。ただし、多すぎる水やりは根腐れを起こしてしまいますので注意が必要です。水やりの目安は土が乾いてから葉が少ししおれるぐらいになってからたっぷりと与えるようにします。
この時、葉の状態を見て追肥をしていきます。化成肥料や液肥を適宜与えてください。肥料の与えすぎも根が焼けてしまうため加減する必要があります。一度にたくさん与えるのではなく様子を見ながら少しずつ施していきます。
プランターでの栽培の場合は、追肥は不可欠です。菜園よりも土が少ないため水やりのたびに土の養分が流れてしまい、肥料不足になりやすい環境にあります。かといってこれも一度にたくさんの肥料を与えると根を傷めてしまいますので注意が必要です。
小かぶ収穫と保存、利用法
小かぶの収穫は5~6㎝に成長した頃が収穫になります。この大きさになったものから順次収穫していきます。葉の付けを手で持ち、ゆっくり引き抜きます。収穫時期が遅れると大きくなりすぎて根が割れたり、スが入ったりして質が悪くなってしまいます。
せっかくここまで育ててきたのですから収穫の時期をを逃さないように適宜に収穫します。春栽培の小かぶはたいへん柔らかくきめ細やかで美味しいとされています。小かぶを保存するときは?がついたままにしておくと葉に水分を吸われてしまいますので、収穫後すぐに葉と根を切り離しておきます。
根の部分はビニール袋などに入れて冷蔵庫の野菜室に保存します。それでも5日位を目安に使い切った方がよいでしょう。葉の場合もラップなどで保湿した後冷蔵庫の野菜室に保管します。葉の場合はさらに持ちが悪く2日以内には利用したほうがよいでしょう。
長く保存したい場合は塩ゆでして冷凍保存するという方法もあります。小かぶは煮物や漬物、蒸し物。焼き物と多くの調理方法で楽しむことが出来ます。特に小かぶは皮が柔らかく煮物や漬物に、または炒め物などに向いています。葉の部分の漬物やおひたしも大変おいしく特に自分で栽培したものは格別の味わいがあります。
小かぶの歴史
原産地を示す説はアジア系とヨーロッパ系に分かれており定かにはなっておりません。
諸説ある中でも地中海沿岸と西アジアのアフガニスタン地方が生息地であったのではないかといわれています。ただ、中国では2000年前には食用として利用されていたことが分かっています。
その当時名前を「諸葛菜」とも呼ばれており、その由来は有名な「三国志」に登場する「諸葛亮」にちなんだもので、諸葛亮は遠征をする際、兵士たちの食糧確保のためにかぶを栽培するように命じたとされています。
日本に伝わった時期は、これも定かになっていませんが奈良時代には食べられていたことが分かっています。一説によると弥生時代に大陸から伝わったというものがありますが、確かめられているのは、「日本書紀」に特統天皇の7年に五穀である主食を補うものとしてかぶの栽培を奨励する、というおふれを出したことが記されています。
日本での株の栽培はこのように古くからおこなわれており各地で品種の開発が盛んに行われていました。世界的に見ても日本でのかぶの品種開発は重要な位置を占めています。
小かぶの特徴
かぶは春の七草のひとつである「スズナ」のことで「スズシロ」といわれる大根とともに日本にはなじみのある野菜の一つです。ポピュラーな野菜だけにその品種は多く、大きさの大小、色、形といったものにさまざまなものがあります。小かぶもその品種に一つになります。
小かぶに限らず、かぶは基本的に秋から冬にかけて最もおいしくなり特に寒さが増すほど甘みが増しておいしいと言われています。小かぶはまるい根の部分だけではなく葉の部分も様々な調理方法で楽しむことが出来ます。
むしろ、この葉の部分のほうが栄養が豊富で味の主張も強く、おいしいので捨てずに利用したいものです。名前の由来は、頭を振るということをかぶりを振ると言ったりしますがその「かぶり」から来たものといわれています。
他の呼び名として古くからあるのが「あおな」とか「かぶらな」というものがあります。この名からわかるように根だけではなく葉の部分にも注目していたことが分かります。昔から根も葉も漬物として食べられ種は薬として用いられてきました。
かぶは耐寒性があり日本では東日本を中心に栽培されており、小かぶは各地で改良されたものが生産されていますが、もともと東京の葛飾区金町付近が原産だと言われています。小かぶは、根の部分が小型で、色は白くきめの細かいのが特徴です。葉は非常に柔らかく栽培はやはり関東を中心に行われています。
野菜の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:カブの育て方
タイトル:ラッキョウの育て方
-

-
トルコギキョウの育て方
長野県は、世界に冠たるトルコギキョウの生産地です。そしてここは、日本で初めてトルコギキョウが栽培された土地でもあります。...
-

-
ヒオウギの育て方
ヒオウギの名前を聞いて和歌を連想する人、京都の祇園祭を思い浮かべる人、様々ですが、原産国は東アジアとなっています。日本も...
-

-
リアトリスの育て方
北アメリカが原産の”リアトリス”。日本には、大正時代に観賞用として渡来した花になります。苗で出回る事が少なく、切り花とし...
-

-
トウモロコシの育て方
トウモロコシの育て方のポイントは、日当たり・通気性・水はけが良い場所を選ぶことと、花粉が雌穂にたくさんかかるように株を複...
-

-
キュウリの育て方について
キュウリは、夏を代表する野菜であり、カリウム・ビタミンC・カロチンなどの栄養素が豊富に含まれた野菜です。浅漬けにしたり、...
-

-
コチョウランの育て方
コチョウランは、18世紀中頃に発見された熱帯植物で、原産地は赤道付近の高温多湿地帯です。インドネシア、フィリピン、台湾南...
-

-
クロガネモチの育て方
クロガネモチの原産地は、日本の本州中部から沖縄、朝鮮半島南部、台湾、中国中南部、ベトナムなどです。もともと日本に自生して...
-

-
シクラメンの育て方
シクラメンはもともと地中海沿岸地域の山地を生息地としている、サクラソウ科の原種であるシクラメンを基にして、品種改良を加え...
-

-
アオキの育て方
庭木として重宝されているアオキは、日本の野山に自生している常緑低木です。寒さに強く日陰でも丈夫に育つうえ、光沢のある葉や...
-

-
オーブリエタの育て方
オーブリエタとは、アブラナ科オーブリエタ属に類する多年草です。多年草とは、毎年生息して育つ植物の事を言います。いわば土の...




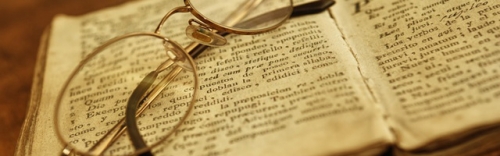





原産地を示す説はアジア系とヨーロッパ系に分かれており定かにはなっておりません。諸説ある中でも地中海沿岸と西アジアのアフガニスタン地方が生息地であったのではないかといわれています。ただ、中国では2000年前には食用として利用されていたことが分かっています。