アスチルベの育て方

アスチルベの育てる環境について
アスチルベは世界中で栽培されている人気品種で比較的新しい園芸品種ですが、もともと日本原産の植物を品種改良したということもあり、日本の風土に良くなじみ、九州から北海道まで幅広く育てることができます。耐寒性が強いため、寒冷地や降雪がある地域でも育てることができます。
この植物は宿根草ですが、冬場は地上部は枯れて地下で年越しをしますので降雪も問題なく乗り切ることができます。ただし耐暑性はそれほど強くないので夏場に直射日光が当たりあまりに乾燥しすぎる地域では葉焼けをお越して株が弱ってしまうことがありますので注意が必要です。
できるだけ木陰などの半日陰で栽培するのが花を綺麗に咲かせるポイントと言えるでしょう。また水はけも大事で、半日陰とは言っても常にジメジメして水はけが悪いところですと、根腐れを起こしてしまうことがあります。できるだけ水はけが良い場所に植えて、
株元をバークチップなどでマルチングして乾きすぎないように注意すると良いでしょう。かなり大きくなる品種ですので鉢植えよりも地植えでの管理をおすすめしますが、鉢植えでも栽培することができます。その際は鉢は乾いて水切れを起こしやすいので、
夏場の水切れ、乾燥に注意して管理しましょう。鉢植えなら春秋は日当たりのいい場所に置き、夏の暑い時期は日陰に移動させることもできるので、株を弱らせないで管理することもできます。基本的に強健で初心者でも安心して栽培することができる品種です。
種付けや水やり、肥料について
植え付けについては真夏の暑い時期を除いては一年中植え付けが可能です。最適な時期は3月から4月の生育期に入る頃、そして花が終わった10月の秋の時期です。地植えする場合には根鉢よりも3倍ほどの大きさの穴を掘り、そこに腐葉土をよく混ぜて耕しておき、植え付けます。
鉢植えの場合には一回り大きな鉢に根鉢を崩さずに植え付けましょう。数年間は植えたままでよいのですが花が少なくなってきたら、株分けして植え直しをしましょう。鉢栽培の場合には成長とともに根詰まりを起こしやすいので一回り大きな鉢に植え替えをします。
古い用土をふるい落として、新しい用土に植え付けます。赤玉土、腐葉土を混ぜ、緩行性の粒状肥料を鋤込んだものに植え付けましょう。この植物は有機質のやや肥えた土地を好み、更に酸性の土を好む性質があります。またアスチルベといえばシェードガーデンの主役とも言える人気の品種ですが、
耐陰性も強く明るい日陰なら丈夫に育てることができます。ただし乾燥に弱いので、水切れを起こさないように水やりを欠かさず行いましょう。特に夏の暑い時期には水切れを起こして葉がチリチリになってしまうこともありますので、朝夕二回の水やりをしましょう。
また、鉢栽培の場合には更に水切れを起こしやすいので、必ず鉢底から水が出てくるまでたっぷりと水やりをしましょう。アスチルベは種から栽培することもでき、新しい品種の中には種まきから一年で開花することができる品種もあります。
増やし方や害虫について
アスチルベは強健で育て方はそれほど難しくありません。害虫についても特に目立ったものはつきません。隣に植えているバラなどにはさまざまな害虫がつくのに、アスチルベは全く害虫がつかずに病気にならない、というケースも多くある強健な植物です。
希にアブラムシがつくことがありますので緩行性の粒状殺虫剤などで退治するのが良いでしょう。葉が黒く斑になる黒斑病というものもありますので殺菌剤を定期的に散布すると予防になります。ただし植えたままにしておくことで徐々に花付きが悪くなってしまうケースがあります。
植え付けてから3年、4年たった頃に株分けをすることで株を更新してまた花付きを改善することができます。植え付けてから数年たち大きくなった株は一度彫り上げて株分けをします。掘り上げた株元を茎を3本から4本ほど付けた状態でカットし、
そうして別々に受け付けることで株分けが完了で、新しい芽が出て花付きが元に戻ります。これは鉢植えの場合にも可能で2年ほどすると根が回って窮屈になり株が弱ってしまうので、株分けをして増やすことをおすすめします。
この際にあまりに小さく株分けをしてしまうと芽を出す分の栄養をしっかりと保つことができないので、3芽位をつけた大きさでカットするようにしましょう。種まきでも増やすことができますが、開花まで一般的に2年から3年程度かかってしまいます。最新の品種には種まきから一年で開花するものもあります。
アスチルベの歴史
アスチルベの歴史は比較的浅く、ドイツで品種改良された園芸種ですが日本にも自生しているので古くから親しまれてきました。日本ではアワモリショウマという品種やチダケサシというものが自生しておりこれがヨーロッパに渡ってアスチルベの品種改良に大きな役割を果たしました。
和名のアワモリショウマは花の様子を泡にたとえて付けられたと言われており、まるで泡のように柔らかで軽やかなこの花の様子をよく表していると言えます。アワモリショウマは生薬として日本人に古くから使われてきたという歴史もあります。
このアワモリショウマや日本原産のチダケサシ、中国産のオオチダケサシなどをかけ合わせてドイツで開発された品種がアレンジーというアスチルベの中でも代表する人気品種です。つまり東洋のチダケサシ類やアワモリショウマがヨーロッパの地で色とりどりで大型のアスチルベとして生まれ変わったと言えるでしょう。
品種改良をすることで開花時期にも幅があり、草丈や花色にもバラエティーに富んだアスチルベが登場して人気を博しています。同じく人気の品種にロセアなどがありますが、いずれも半日陰や痩せた土地でもしっかりと育つことができる、強健さが、
初心者でも安心して栽培できるという魅力になっているのです。このようにまだまだ歴史の浅い品種ですが、その元の原産品種は日本人にも古くから親しまれていることから、日本人もこの植物に親しみや懐かしさを感じるのです。
アスチルベの特徴
アスチルベはユキノシタ科チダケサシ属の植物でアケボノショウマとも呼ばれています。生息地は地中海沿岸東アジア、北米東北部、中国、そして日本などヨーロッパからアジアまで広く分布しています。樹高は20センチメートルから中には100センチメートルにもなる大型の品種もありバラエティに富んでいます。
ボーダーガーデンの一番バックの背景にも使われるボリュームある品種も人気があります。開花時期は5月から9月と品種によっても幅広く少しづつ開花時期が違う品種を植え付けて長く楽しむということもできます。この品種の最大の特徴として耐陰性があります。
もちろん明るい日向でも育ちますが、日陰でこそ生き生きと美しい花を輝かせるため、シェードガーデンの主役にもなっているのです。耐寒性も強いですが、暑さには弱いので夏の日差しが一日中当たるような場所ではしっかりと丈夫な株に育たないケースもあります。
植栽域は九州から北海道と幅広く耐寒性もあるので、寒冷地などでも育てることができます。繊細な小花がびっしりと咲きまるで柔らかい泡のように見えます。色も豊富で赤やパステルピンク、白などカラフルでマイルドなカラーが揃っています。
耐陰性があるので建物の影になるようなところでも植えることが出来、樹林の下などに植えられるケースも多く見られます。バラと合わせてイングリッシュガーデンの主役になることもできますが、日陰の庭をカラフルに彩ることができるのがこの植物の最大の魅力と言えます。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:アマドコロの育て方
-

-
植物の育て方を押さえてオリジナルな庭づくりを楽しみましょう
最近では、様々な所でガーデニングなどの園芸講座が開かれています。自分オリジナルな庭を作ることが出来るため、一つの趣味とし...
-

-
ワックスフラワーの育て方
花についてはフトモモ科、チャメラウキウム属になります。園芸上の分類としては庭木であったり花木としてになります。草丈に関し...
-

-
かぼちゃの育て方
生息地はインドのネイル河沿岸やペルー、南アジアやアンゴラなど様々な説があったのですが、ここ数年の間に研究が進められ、中南...
-

-
ハーデンベルギアの育て方
ハーデンベルギアはオーストラリア東部に位置するタスマニアが原産のツル性の常緑樹で、コマチフジ・ヒトツバマメ・ハーデンベル...
-

-
クレソン(オランダガラシ)の育て方
クレソンは、日本では和蘭芥子(オランダガラシ)や西洋ぜりと呼ばれています。英語ではウォータークレスといいます。水中または...
-

-
ツバキの育て方
ツバキ属は科の1属で、生息地は日本や中華人民共和国、東南アジアからヒマラヤにかけてです。日本原産の花で日本国内においては...
-

-
ゲンノショウコの育て方
この植物の原産地と生息地は東アジアで、中国大陸から朝鮮半島を経て日本全国に自生しているということですので、昔から東アジア...
-

-
ヒビスクス・アケトセラの育て方
ヒビスクス・アケトセラが日本に入ってきた年代は詳しく知られていないのですが、本来自生しているものは周種類であるとされてい...
-

-
食べ終わったアボカドを観葉植物として栽培しよう
最近、美容にとてもいい効果があるとしてハリウッド女優やモデルがよく食べているというアボカドは、栄養価が高く質のいい不飽和...
-

-
ケラトスティグマの育て方
中国西部を原産としているケラトスティグマは明治時代に日本に渡ってきたとされています。ケラトスティグマの科名は、イソマツ科...




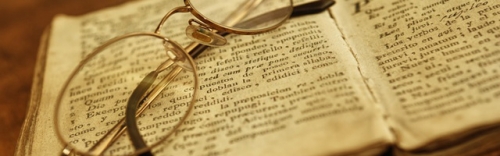





アスチルベの歴史は比較的浅く、ドイツで品種改良された園芸種ですが日本にも自生しているので古くから親しまれてきました。日本ではアワモリショウマという品種やチダケサシというものが自生しておりこれがヨーロッパに渡ってアスチルベの品種改良に大きな役割を果たしました。