アカンサスの育て方

アカンサスの育てる環境について
生育旺盛で、あまり土地を選ばずに育ち、基本的には露地植えで育てることが適しています。ゴボウのような根が地中を走り、そこから芽を出して広がっていきます。他の植物の領域にも侵入することがあるので、スペースや他の草花との兼ね合いをよく考えて植えることが育て方のポイントです。
花が一通り咲き終わったら、花茎を株元から切り落とします。これにより余分な栄養が枯れた花茎に行かなくなり、次の花が咲きやすくなります。耐寒性、耐暑性が強く、よほどの寒地でない限り栽培可能です。乾燥に強く、日当りの場所〜やや日陰の場所で育てることができ、
花を楽しむ場合は、日当りのよい場所に植えることが必要で、最低でも木漏れ日程度の日差しは必要です。日当りが悪いと花付きが悪くなり、葉を観賞するのであれば、やや日陰になる場所を選びます。やや日陰になる場所でもよく育つため問題はありません。
種により耐寒性は若干異なります。モリスよりスピノススの方が寒さに強いですが、アカンサスは概ね耐寒性は強く、マイナス2度〜3度まで大丈夫です。乾いた寒風にさらされると葉が傷むため、乾いた寒風があたるようであれば風よけをします。
モリス種などは常緑性ですが、鉢栽培では夏に葉が枯れて休眠状態になりやすく、秋に新芽が出ます。また寒冷地では冬に地上部が枯れます。土は水はけの良い土が適しています。水はけが悪い場所は、腐葉土や堆肥を混ぜます。手間のかからない宿根草で、花がらや枯れ葉を取り除くほかは、殆ど作業の必要がありません。
種付けや水やり、肥料について
アカンサスはかなり大きくなるため、露地植えで育てることが適しており、植えつけは真冬と真夏、開花期を除けばあまり時期は選びませんが、3月〜5月、10月〜11月が適期です。鉢植えの場合の用土は、一般の草花用向けの培養土が利用できます。
水はけを良くしておくことが大切なので、山野草向けの用土なども使用可能です。ポット苗の植えつけは、ほぼ周年で可能です。植えつけの際、株元をマルチングしておくとよいです。大きく育つため生育スペースが必要ですが、狭い場所で小さく育てることも可能です。
ただし、小さく育てた場合は花は殆ど咲きません。植え替えは、4〜5年、またはそれ以上植えたままの状態でも育てられます。表土が硬くなったり、水はけが悪いようなら植え替えや植え直しをします。切れた根からも芽を出して増えるため、掘り上げて他の場所に移す場合は、根は土の中に残さないようにします。
根をブチブチ切って、それを土の中に残すということは、それだけ芽の出る苗を増やしていることになるため、注意が必要です。水はけの良い適度な湿り気のある土壌を好み、土が乾いたらたっぷりと水を与えますが、乾燥に強いため水のやり過ぎには注意が必要です。
鉢植えの場合も同じで、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えます。肥料は植えつける際に、あらかじめ土の混ぜ込んでおくとよいです。後は様子をみて春か秋に少量の追肥を与えます。ただし、肥料はあまり与えなくても良く育ち、庭植えの場合などは、殆ど肥料は必要ありません。
増やし方や害虫について
増やし方は、根伏せ、株分け、種まきで増やすことが可能です。根伏せは、早春か秋に行い、ゴボウのような太い根を約5〜10cm程度の長さに切って、土の上の寝かせて浅く埋めます。これで芽が出てきて生長して苗ができます。株分けは、早春か秋に行ないます。
葉はしおれるので切り取っておきます。株の脇から出てくる芽がある程度の大きさになったら切り離して植えつけます。種まきの場合は、春に7.5〜9cmのポットに1粒ずつまいて育てると3〜4年後には花が咲きますが、花や葉などの性質にはばらつきが出る場合があります。
アカンサスは丈夫な植物ですが、水はけが悪いと根腐れしやすくなり、センチュウの被害が出ることがあります。害虫のセンチュウは、土の中にいる体長1mm以下の小さな生物で、肉眼で確認することが難しいほどです。根に寄生して養分を吸い取り、植物の生育を衰えさせて枯らしてしまいます。
同じ植物を何年も同じ場所で連続して栽培している発生しやすい害虫です。センチュウの駆除は農薬で消毒したり、太陽熱で消毒したりする方法があります。露地植えの場合は、他の植物の土と繋がっているため消毒が行き届かないことがあり、そこから侵入してくるセンチュウもいるため、抑えきれないのは否めません。
センチュウが発生するのは土の中の微生物のバランスが崩れているためです。そのバランスを専用の肥料などで元に戻す必要があり、センチュウには事前の土への対策が必要になります。やっかいなセンチュウなので、大切なことは、健全な苗を選んでセンチュウを持ち込まないようにすることです。
アカンサスの歴史
アカンサスはキツネノマゴ科アカンサス属またはハアザミ属の植物で、別名をギザギザの葉がアザミの葉に似ていることから和名を葉薊と言われています。アカンサスは通常は観賞常用に栽培されるスペインからギリシアを生息地とするモリス(A.mollis)を指し、
名前はギリシア語でakanthaトゲという意味があり、そのトゲは花の付け根の苞にトゲがあることによります。地中海沿岸を生息地として、日本には明治末〜大正時代に渡来しました。アザミに似た形の葉は、古代ギリシア以来、建築物や壁画の内装などの装飾モチーフとして使用されています。
ギリシア建築の柱(オーダー)の一種のコリント式オーダーにはアカンサスを意匠化した柱頭を装飾として特色しています。アカンサスはギリシアの国花で、アカンサスをモチーフにした柄は絨毯などにも用いられており、ビザンチンリーフとして知られています。
紀元前5世紀のギリシア時代、ある彫刻家がコリントという土地で女の子のお墓にあったアカンサスの姿形からアイディアを得て、コリント様式の建築物を作ったという説があります。アカンサスは葉を表す装飾の中でも一般的なもので、装飾はコリント式のオーダーの柱頭を始め、
さまざまな部分に施されています。古代ギリシア文化が装飾の期限で、渦を巻く先端の部分はローマ人により磨きがかけられました。アカンサスの装飾としての人気は、ビザンチン、ロマネスク、ゴシック建築の時期まで続き、ルネサンスの復興時期にも及び、現在まで支持され続けています。
アカンサスの特徴
原産は地中海沿岸で、大型の常緑多年草です。葉には深い切れ込みや光沢があり、根元から長さ約1mで、幅は約20cm程度になります。晩春から初夏に高さ約2mに花茎を出して、緑色か紫がかった尖った葉とともに花をつけます。花弁は筒状で色は白や赤などがあります。
乾燥や日陰、寒気にも強いです。アカンサス属は約30種あり、地中海沿岸を中心に分布しています。アカンサスの種類は、モリス(A.mollis、ハアザミ)、スピノスス(A.apinosus、トゲアザミ)、ハンガリカス(A.hungaricus)などの品種がよく栽培されています。
モリスは草丈約2mほどで、スピノススは約1.5m程度です。これらは常緑で葉に幅がありますが、ハンガリカスは細い葉で冬に落葉します。コリント式オーダーの柱頭に使用されているのはスピノススで、大きな根生葉で、葉が深裂しており、アザミの葉に似ていますが、
先端はトゲ状ではありません。園芸ではアカンサスというとモリスを指すことが多く、モリスには葉や花びらが白くガクや苞が緑色のアルバがあります。モリス以外にはスピノススが花壇などで比較的よく栽培されています。主な開花期は6月〜9月で、花穂は長さが約60cm程度あり、そこには沢山の花を咲かせます。
花は上部に赤紫色でひさしようなガクがあり、下部にトゲの生えたあごのような苞があり、その間から白〜淡いピンクの花びらが出てきます。他にはあまりみられない変わった形状をしています。雄大な花穂と濃緑色の葉との組み合わせは落ち着いた雰囲気があり、単独でも存在感がある植物で、重厚な洋風建築などに非常に合います。
観葉植物の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ヒポエステスの育て方
タイトル:コエビソウの育て方
-

-
家庭菜園や花壇の作り方において大事な事
家庭菜園や家庭花壇などを作る場合においては、まず植物の栽培方法はもちろん、植物の育て方から植物の種まきのやり方の基本まで...
-

-
アメリカアゼナの育て方
アゼナ科アゼナ属で、従来種のアゼナよりも大きく、大型だが花や葉の姿形や生育地はほとんどが同じです。特徴はたくさんあります...
-

-
ミヤマオダマキの育て方
ミヤマオダマキはキンポウゲ科のオダマキ属になります。ミヤマオダマキの特徴としては、葉はハート形になっていても、その丸美帯...
-

-
ディアスキアの育て方
ディアスキアの原種は南アフリカを生息地とする植物です。原産の南アフリカには50種が分布しています。ヨーロッパで栽培される...
-

-
観葉植物と盆栽の育て方と栽培時の注意点
空前のガーデニングブームにより、観葉植物や盆栽と言った家庭で楽しめる植物が流行しています。簡単な知識と栽培方法を用いて育...
-

-
トウモロコシの育て方
トウモロコシの育て方のポイントは、日当たり・通気性・水はけが良い場所を選ぶことと、花粉が雌穂にたくさんかかるように株を複...
-

-
オシロイバナの育て方
日本に入ってきたのは江戸時代に鑑賞用として輸入されたと言われており、当時この花の黒く堅い実を潰すと、白い粉が出てきます。...
-

-
アエオニウムの育て方
アエオニウムはアフリカ大陸の北西の北アフリカに位置するカナリー諸島原産の植物です。生息地は亜熱帯を中心に多くく見られる植...
-

-
ザゼンソウの育て方
ザゼンソウは、ザゼンソウ属サトイモ科の多年草の草木です。学名はSymplocarpusfoetidusで、漢字では座禅草...
-

-
ウツボグサの育て方
中国北部〜朝鮮半島、日本列島が原産のシソ科の植物です。紫色の小さな花がポツポツと咲くのが特徴です。漢方医学では「夏枯草」...




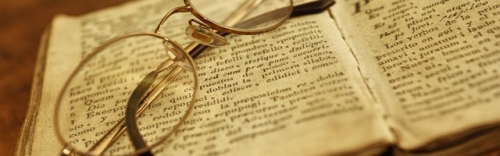





アカンサスはキツネノマゴ科アカンサス属またはハアザミ属の植物で、別名をギザギザの葉がアザミの葉に似ていることから和名を葉薊と言われています。