ヒメリュウキンカの育て方

ヒメリュウキンカの育てる環境について
湿り気がある草原などに自生するヒメリュウキンカですが、11月頃から6月頃まではよく日が当たるような場所に置いておくのが良いです。それ以降は直射日光や雨が当たらない棚下やベランダの日陰に置いてあげるのが良いです。これは6月以降になると葉が枯れて休眠期間に入るからです。
耐寒性は強いので、冬場は少し凍結するくらいならなんとか越冬することができます。しかし乾いた寒風や霜は葉が傷んでしまう原因になるので、そこは避けるようにしましょう。土は水はけさえ良ければ特に質は選びません。鉢植えであれば赤玉土や鹿沼土か、
この二つの土を混ぜ合わせたものを使うようにするのが良いです。植え付けをするのであれば晩夏から初秋にかけてがベストです。植え替えも同じ時期で大丈夫です。鉢植えにするのなら鉢底には大粒の軽石を敷いて、その上に粒状の肥料を軽く施しててから用土を少しだけ入れます。
ここで注意したほうが良いのは根と肥料が直接触れないように気をつけるのがポイントです。この上に根茎を置いてから用土を入れて芽は1、2cmほど隠すように植えます。植え付けや植え替えをした後は芽が出てくるまで日陰で極端に乾かさないように管理をしていきます。
ヒメリュウキンカの育て方はその生育のサイクルをしっかりと理解しておくことが大切なのです。庭植えにする場合は環境が合えばどんどん増えていくので、もし増やしていくつもりなら他の植物と一緒の場所に植えるのは避けて単独で植えたほうが良いです。
種付けや水やり、肥料について
水やりは土の表面が乾いてきたらたっぷりと与えるようにします。1年を通して1日1回の水やりを基本にしておくのが良いです。しかし庭植えの場合は雨水でも十分なので、特に気を使う必要はありません。開花後は水やりの回数を少なくします。
しかし土の表面がしっとりとしているくらいが良いと考えておきましょう。肥料は10月半ば頃から5月頃までは10日に1度液体肥料を与えるか固形肥料を少量施すようにするのが良いです。特に開花後は株を大きくするためにも肥料を必要としますので忘れないようにして与えましょう。
ただし肥料は多過ぎると形が乱れますし、量に関してはちょうど良いという量をその個体の状態によって考えながら与えるようにするのがいいです。庭植えの場合は水やり同様で、特に必要ありません。種付けは開花後に花茎をそのままにしておくことでできます。
種を採取できるようになるのは4月下旬頃から梅雨明け頃までなので、その頃に種まきもしてしまうのが良いでしょう。ヒメリュウキンカの種はとても小さく、白っぽい部分がほとんどですが、端っこだけは濃い目の茶色のような色をしています。
小さいので採取する時には花茎ごとカットし、紙などを下に敷いてからにすると良いでしょう。ヒメリュウキンカは1つだけ植えてあってもすぐに増えていく植物なので、種付けされたものを全て採取するのではなく、必要な分を残してあとは摘み取ってしまうようにしたほうがいいです。
増やし方や害虫について
害虫はアブラムシやイモムシ、ナメクジなどがつきやすいので気をつけましょう。アブラムシは蕾や花茎によくつきますので見つけ次第除去します。茎などについているものであれば落とさないように気をつけて手でさっと取り除くこともできますから、
薬を購入しに行くまでのしのぎとしてやっておくだけでも違います。アブラムシは一度に大量の幼虫を生みますのですぐに増えてしまうからです。イモムシやナメクジなども見つけたらすぐに取り除き、専用の薬をまいておくのが良いでしょう。
病気も灰色かび病やウイルス病にかかりやすいので注意しておきます。特に低温多湿の頃に灰色かび病は発生しやすいので気をつけます。そして葉に色むらが出てくるようであればウイルス病の可能性があります。増やし方は株分けや根伏せ、種まきなどで増やすことができます。
株分けするのは植え替え時で、必ず芽が1つ以上ついているかどうかを確認してから行います。植え替えする時に小さな棒状の根茎を一本ずつ株から外して用土に伏せておくのが根伏せです。根伏せしたものは晩秋に芽が出て生長を始め、運がよければ翌春からすぐに花を咲かせ始めます。
株分けする時には塊根は芽をつけた状態でも軽く引っ張るだけで分かれるので簡単です。多めの数に増やしたい時には塊根をばらばらにしてしまいます。芽が出てくるのは少しだけ遅れますがしばらくすると発芽し、1年で親株に育ちます。種まきは培養土にまきます。すると翌年の2月から3月にかけて発芽するので約1年ほどで開花するようになります。
ヒメリュウキンカの歴史
ヒメリュウキンカの原産はイギリスで、生息地は山野の湿った草原や川沿いの林床などです。原産はイギリスではありますが、自生地はヨーロッパからシベリアの辺りまでと幅広いです。別名を欧州金鳳花として販売されていることもあります。
ヒメリュウキンカという和名は花や葉がリュウキンカに似ていることからつけられました。しかしリュウキンカは同じキンポウゲ科ですが、属は違います。英語では地面にはりつくようにして広がる葉が矢じりに似ているということからパイル・ウォートという名前がつけられています。
学名のRanunculus ficariaはラテン語で、Ranunculusが蛙という意味があるRanaからとられており、ficariaはイチジクのようなという意味があります。キンポウゲ属の名をつけたのは古代ローマの政治家で軍人、そして博物学者のガイウス・プリニウス・セクンドゥスです。
イギリスから渡来したのはそれほど昔ではなく、日本では園芸種として入ってきており、今ではそれが野生化もしています。鉢植えにも植えることができますが、草丈もわずか5cmから10cm程度なので世話をしやすいのがメリットです。
多年草なので毎年可愛らしい黄色い花をつける姿を見ることができます。一度野生化してしまうとあっという間に増えてしまいますので、もし必要ない場所に生えているのを見かけたら掘りあげて違う場所や鉢植えにしてしまうのがオススメです。
ヒメリュウキンカの特徴
ヒメリュウキンカは漢字で書くと姫立金花で、葉は暗緑色のハート形をしており、葉の縁には浅いぎざぎざがあります。春になると花茎を伸ばして表面に光沢がある3cmから4cmほどの黄色の花を咲かせます。次々に花が咲きますので長ければ1か月は花を楽しむことができます。
開花後は種ができます。夏くらいになると葉は枯れてしまい、地中に根茎を残して休眠状態になります。5枚の花びらのように見えるものは萼片です。一般的にはその名の通りで黄色の花のイメージがありますが、園芸品種になると白やクリーム色のもの、八重咲きのものもあります。
開花後にはそう果といい、熟しても勝手に裂開するものではなく、種子は一つで全体が種子のように見えるものです。開花は2月から4月で、栽培の難易度もそれほど難しいものではありませんから、初心者でも育てやすいです。耐寒性は非常に強いですが、
あまりに寒い地域では葉が落ちてしまうこともありますのでその辺りはちゃんと管理をしてあげる必要があります。花言葉はあなたに会える幸せです。あまりに増えていくようであれば、ある程度育ったところで剪定をするのが良いでしょう。
見た目が似ているリュウキンカとの違いは、リュウキンカは腰水栽培をすることができますが、ヒメリュウキンカはこれと同じように腰水栽培をすると根腐れを起こしてしまうということです。成長期には水を好みますが、水はけも良い場所に植えてあげるのが良いでしょう。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ブルークローバーの育て方
タイトル:フヨウの育て方
-

-
イブキジャコウソウの育て方
イブキジャコウソウなどのタイムの原産地は南ヨーロッパで、古代ギリシャ時代から薬用や食用として利用されています。紀元前の7...
-

-
ホテイアオイの育て方
ホテイアオイという水草の原産地は南米大陸であり、現在では北米大陸や欧州やアジアなど、多くの国々を生息地として分布されてい...
-

-
キンギョソウの育て方
キンギョソウはもともとは多年草ですが、暑さで株が弱り多くが一年で枯れてしまうので、園芸的には一年草として取り扱われていま...
-

-
コツラの育て方
この花の特徴はキク科となります。小さい花なので近くに行かないとどのような花かわかりにくいですが、近くで見ればこれがキク科...
-

-
かぼちゃの育て方
生息地はインドのネイル河沿岸やペルー、南アジアやアンゴラなど様々な説があったのですが、ここ数年の間に研究が進められ、中南...
-

-
ルドベキアの育て方
ルドベキアは北米を生息地としており、15種類ほどの自生種がある、アメリカを原産とする植物です。和名ではオオハンゴウソウ属...
-

-
ライラックの育て方
ライラックの特徴としてあるのはモクセイ科ハシドイ属の花となります。北海道で見られる事が多いことでもわかるように耐寒性があ...
-

-
クリサンセマム・ムルチコーレの育て方
クリサンセマム・ムルチコーレの生息地は、ヨーロッパ西部と北アフリカなどの地中海沿岸です。アルジェリア原産の耐寒性または、...
-

-
アイビーの育て方について
観葉植物にも色々な種類が有りますが、その中でもアイビーは非常に丈夫な上に育てやすいので初心者や、観葉植物の育て方が分から...
-

-
ムラサキサギゴケの育て方
ムラサキサギゴケは、ハエドクソウ科のサギゴケ属になります。和名は、ムラサキサギゴケ(紫鷺苔)でその他の名前は、サギシバな...




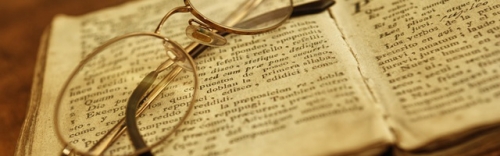





ヒメリュウキンカの原産はイギリスで、生息地は山野の湿った草原や川沿いの林床などです。原産はイギリスではありますが、自生地はヨーロッパからシベリアの辺りまでと幅広いです。