オクラの育て方

オクラの種付けと間引き
オクラは育て方一つで収穫量が大きくかわる野菜ですが、初心者にも簡単に栽培できる丈夫な野菜です。まず、遅霜の心配がなくなった4月下旬~5月中旬がオクラの種付け時期です。オクラの種は種皮が非常に固いため、一昼夜水につけてから播くと、発芽がよくなります。
この際に、浮いてきた種子は不良なので捨ててしまいましょう。これで発芽率を上げることができます。種付けの一週間前までに栽培予定箇所に堆肥と肥料をまき、よく耕しておきます。酸性土壌に弱いという特徴があるため、酸性が強い場合にはあらかじめ石灰などの資材も散布して、Phを調整しておきます。
オクラは発芽適温が高いため、黒マルチを使用して、地温を上げるという育て方が無難です。これをするとしないでは、発芽、初期生育に大きな差がでます。畝の表面に密着するようにマルチシートを張り広げます。一般的な育て方としては、オクラは移植を嫌うため、直播で行います。幅90cm、株間35~40cmの点播きとします。
指で深さ1cm程度のくぼみをつけ、1か所に3~4粒ずつ種を播き、土を被せてたっぷり水をまきます。ポットで育苗して移植という育て方もありますが、くれぐれも根を傷つけることがないよう、丁寧に作業を行い、一度定植したら、その場所から移動させないようにします。
双葉の頃にアブラムシの発生で株が弱まることがあります。種付け後、寒冷紗やべたがけシートをかけ、アブラムシの飛来防止や鳥よけとします。べたがけシートをかける際には、苗の生長を妨げないように必ずゆるみをもたさせてかけておきます。
寒冷紗やべたがけシートは保温や土壌中の水分保持にもつながります。本葉が2~3枚になったら寒冷紗やべたがけシートをはずします。2週間もすると発芽がそろいますので、苗が30cmになるまでは3本、その後1~2本にします。残す株の根を痛めないように注意しながら間引きます。
オクラの育て方 追肥と病害虫
花が咲き始めた頃、追肥を開始します。2週間おきくらいに一握りの化成肥料を施します。有機栽培ではゴミ汁液肥等を与えます。肥料はマルチシートの外側にまき、軽く土をかぶせます。オクラは肥料不足になると葉の形がかわってきます。
葉の切れ込みが浅いと肥料は十分足りており、深いと肥料不足が考えられます。また、結実した実についても肥料不足だといびつな形になります。肥料不足のサインを見極めて、適切に施しましょう。病害虫としては、苗の時期にネキリムシの被害をうけやすいです。
ネキリムシとはネブラヤガ、タマナヤガなどの我の幼虫類のことです。野菜の茎の根をばっさり噛み切ってしまうためネキリムシと呼ばれています。昼間は土中にもぐり、夜間にでてきて食害します。翌朝に被害にあった作物の根元を掘り起こしてみるとネキリムシが見つかるので捕殺します。
事前にできる防除策としては、プラスチック性のコップやペットボトルを高さ4cmくらいの輪切りにして1~2cm土中に埋め込み、そこに種付けをしたり、苗を植え付けます。アブラムシの被害も多く見られます。苗から初期段階にかけてアブラムシの被害を受けると生育を阻害し、ひどい時には枯れてしまいます。
アブラムシは反射光が苦手であることがわかっていますので、銀紙やアルミホイルを茎にぶらさげたり、根元にしいておくだけで多少はアブラムシを寄せ付けない効果はあります。また発生してしまった場合には、牛乳散布でアブラムシを窒息させる方などがあげられます。
ハマキムシとよばれるワタノメイガの幼虫は、葉の先を丸めて、そこに住んでいます。これについては数が多くなければそれほど被害を受けることはありません。どの害虫についても早期発見することができれば、地道な手作業での駆除で、ある程度は被害を防ぐことができます。何より、マメに畑に足を運び、作物と周囲の環境を観察し、早期発見を心がけることが大切です。
オクラの収穫と採種
花が咲くとその4~5日後にはもう収穫時期となります。オクラは葉のつけ根に実ができます。へたをハサミで切って収穫します。五角オクラは長さ6~7cm、丸オクラは12~15cmで収穫します。
適期が短く、五角オクラは採り遅れるとすぐに固くなってしまうので栽培に注意します。収穫が始まったら適度に葉を切り落とすと株に勢いがつき、上に伸びて実が次々とつきます。実より下の葉はハサミで切り落とすと上の葉や実の生長が促されます。日当たりや風通しがよくなる効果もあります。株の生育があまりよくない場合には、葉はつけておき光合成を促すようにしましょう。
オクラの種とりは比較的簡単です。健康な状態の良いオクラの実を収穫せずに残しておきます。すると徐々に固くなり、しまいには黒ずんでカラカラになります。その時、茎からかきとって種をとり出し保管し、翌年の栽培で使用します。一度オクラを栽培した場所では、翌年、同じ場所での栽培は控えましょう。うどんこ病や立ち枯れ病などの連作障害のリスクがあります。
オクラの歴史
アオイ科に属する野菜で、原産地は、マントヒヒの生息地で知られるアフリカ北東部です。エジプトでは紀元前から栽培されていました。日本には幕末にアメリカからはいってきましたが、食用としてはほとんど栽培されていませんでした。
今でこそ、オクラの特徴でもあるネバネバは健康野菜の象徴のように言われていますが、独特の青臭さや、粘りが受け入れられなかったようです。第二次世界大戦中には完熟した種子をコーヒー豆のかわりに代用されたり、鑑賞用として栽培されていただけでした。
戦後、台湾、東南アジアの生活経験者が帰還し、これらの人たちがわずかに栽培をはじめたと言われています。一般家庭に食用として普及しはじめたのは1960年頃です。オクラという名前は現地語からきており、和名はアメリカネリといいます。
アメリカから渡来したネリ(トロロアオイ)という意味です。現在、日本では鹿児島県や高知県、沖縄県など温かい地域での生産量が高く、冬から春にかけてはフィリピンやタイからの輸入ものが店頭に並びます。
オクラの特徴
日当たり、水はけがよく、肥沃なところを好みます。暑さに強く、真夏でも野菜の中で最も美しい言われる黄色い花を次々と咲かせ、実をつけます。その一方で、寒さに弱く、10度以下の低温では生育が停止してしまいます。
寒さに弱いので日本では一年草となっていますが、暑い熱帯気候のもとでは多年草となります。発芽適温は25~30度、寒いと発芽しないので、種まきは十分温かくなり、遅霜の心配のない4月下旬~5月が適期です。オクラは直根性で移植を嫌うので、直播をおすすめします。
草丈は品種により異なりますが1~2mになります。収穫が遅れるとサヤが固くなってしまうので、早めの収穫が重要なポイントとなります。サヤの形が五角形で緑色のものが一般的ですが、サヤが丸いものや、赤色の品種もあります。
五角オクラよりも丸オクラのほうが草丈が高く、収量は少なめですが、多少収穫が遅れて大きくなってしまってもおいしく食べることができます。花オクラは花を食べますが、トロリとしていてとても美味です。
栄養的にはカロチンやビタミン群はもちろん、カルシウムや鉄、カリウムなどのミネラルも多く含む栄養価の高い野菜です。独特の粘り成分は、ペクチンという食物繊維とムチンという糖タンパク質によるもので、胃の粘膜を保護し、腸内環境を整えるなど夏バテ予防に効果的です。
-

-
バーベナの育て方
バーベナは、クマツヅラ科クマツヅラ属(バーベナ属とも)の植物の総称です。様々な種類があり、基本的には多年草、あるいは宿根...
-

-
小かぶの育て方
原産地を示す説はアジア系とヨーロッパ系に分かれており定かにはなっておりません。諸説ある中でも地中海沿岸と西アジアのアフガ...
-

-
カラジウムの育て方
カラジウム/学名・Caladium/和名・ハイモ、カラジューム/サトイモ科・ハイモ属(カラジウム属)カラジウムは、涼しげ...
-

-
ヘリクリサムの育て方
このヘリクリサム、ホワイトフェアリーの一番の特徴は何といってもその触り心地です。ドライフラワーかと思うような花がたくさん...
-

-
シーマニアの育て方
シーマニアは、南アメリカのアンデス山脈の森林が原産の植物であり、その生息地は、アルゼンチンやペルー、ボリビア等の森林です...
-

-
スプラウトの育て方
スプラウトの歴史はかなり古いとされています。5000年も前の中国では、すでにモヤシが栽培されていたとの説があります。モヤ...
-

-
スプレケリアの育て方
スプレケリアは別名「ツバメズイセン」と呼ばれる球根植物で、メキシコやグアテマラなどに1種のみが分布します。スプレケリアは...
-

-
ノビルの育て方
原産地や生息地の中国では漢方薬としても利用されていて、すりおろして痒み止めやかぶれ等の付け薬にしているということでした。...
-

-
キンバイソウの育て方
キンポウゲ科キンバイソウ属に属する多年草で、その土地にしか生えていない固有の種類です。過去どのような形で進化してきたのか...
-

-
エボルブルスの育て方
エボルブルスは原産地が北アメリカや南アメリカ、東南アジアでヒルガオ科です。約100種類ほどがあり、ほとんどがアメリカ大陸...




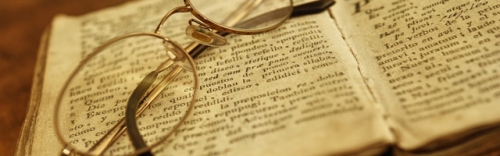





アオイ科に属する野菜で、原産地は、マントヒヒの生息地で知られるアフリカ北東部です。エジプトでは紀元前から栽培されていました。日本には幕末にアメリカからはいってきましたが、食用としてはほとんど栽培されていませんでした。