スパティフィラムの育て方

育てる環境について
スパティフィラムは日当たりの良い、風通しの良い所で育てるのがお勧めです。直射日光に当たってしまうと葉焼けを起こしてしまいますし、逆に暗すぎると今度は花を付けません。その為、室内の明るい所で管理するようにしましょう。戸外で育てる場合は半日陰になるような場所がお勧めです。
冬になれば日中は日向に出して日光浴をさせ、夕方気温が下がってきたら暖かい室内に取り込むようにするとよいでしょう。成長がとても早いため、根詰まりには注意が必要です。鉢の底から根が出てきたら根詰まりを起こしていますので植え替えをしてあげましょう。
その際、花が咲いている時には控えた方が無難です。根詰まりを起こしていなくても、根が弱ってくると花の付きが悪くなってしまいますので、出来ることなら毎年植えかえてあげることをお勧めします。スパティフィラムは水はけの良い土を好みますので、赤玉土と腐葉土、
パーライトを6:3:1くらいの割合で混ぜたものを使用するとよいでしょう。パーライトがなければ川砂でも結構です。市販の観葉植物用の用土を使用しても大丈夫です。植えかえをする際、古い土は完全に落とす必要はありません。上の部分の土を軽く落とし、
弱っている根があればその部分を切り落として、一回り大きめの鉢に植え替えます。親株の周りに子株がたくさん出てきていたら、株分けをして、根にゆとりを持たせてあげることが大切です。もし増やしたければ植え替えの時に切り落とした部分を利用して新株にするとよいでしょう。
種付けや水やり、肥料について
スパティフィラムを種が入手できたら、是非発芽させてみましょう。赤玉土(小粒)に十分に湿らせた水苔をしっかりと混ぜ込んで保水力をあげた土を使用します。パラパラとばら撒くようにまいて、極浅く土をかぶせ、乾燥しないように日陰で管理しておくと発芽します。
種から育てたものは開花するまでに数年かかると言われていますが、それも楽しみの一つといえるのではないでしょうか。スパティフィラムは水を好む植物ですので、用土が乾いてきたらたっぷりと水を与えるようにしましょう。夏場は頻度を上げ、用土が乾く前に与えて下さい。
葉がしおれるのを防ぐためにも定期的に葉水を与えるのもポイントです。冬になれば生育が止まり気味になりますので、水やりは控えめにします。用土が乾いてからさらに数日経過してから水やりをするくらいで十分です。スパティフィラムの花は、十分な肥料がないと咲きません。
春から秋ごろが生育期になりますので、2ヶ月に1度位の割合で緩効性のある置き肥などをして、しっかりと肥料を与えてあげるようにします。冬の間はあまり肥料は必要ありませんが、もし新芽が出てきているようであれば同様に追肥をしましょう。
葉が弱ってきたように感じたら、1〜2週間に一度ほど液体肥料を与えるのも効果的です。葉はドンドン茂ってきているのに花が咲かないという場合は、逆に肥料が多すぎる場合があります。また根詰まりや日光不足なども考えられますので、肥料は控えめにして、日光量と根のチェックをしてみましょう。
増やし方や害虫について
スパティフィラムは種まきと株分けによって増やすことが出来ます。時間はかかりますが、種まきから育ててみたいという方は、仏炎苞が茶褐色に変色するまで摘まずにおいてみてください。やがて花序部分が完熟し、種を採取することが出来ます。
一般的には植替えの際に切り落とした部分を使用し、株分けで増やします。5月から7月頃に行うのが適期です。大きく育った株をハサミなどで2〜3株に切り分け、土を丁寧に落とした後、清潔な新しい用土に植えつけてあげます。または親株の周りに伸びてきた子株を使用してもよいでしょう。
植え替えた後は新芽が出てくるまで、風の当たらない明るい日陰で管理するようにします。水やりは控えめにし、乾燥気味にしておくのがポイントです。スパティフィラムは病気に強い植物ですが、時折カイガラムシやハダニ、アブラムシが発生することがあります。
ハダニは乾燥していると発生しやすいので、防止のためにもマメに葉水を与えるか、濡れた布で葉の表裏を拭いてあげるようにしましょう。発生しているのを見つけたら、殺ダニ剤で駆除します。カイガラムシは風通しが悪いと発生します。薬剤が効きにくいので、
もし見つけたら歯ブラシかウェットティッシュを使ってこすり落とします。カルホス乳剤を散布しておくのも効果的です。アブラムシは養分を吸い取って弱らせてしまいますので要注意です。見つけ次第、早めにアブラムシ専用の薬剤を使用して駆除しておくようにしましょう。
スパティフィラムの歴史
スパティフィラムは中央アメリカから南アメリカの熱帯地域を原産とするサトイモ科の多年性植物です。主に森林の湿地帯を生息地としており、およそ30種類ほどあるといわれています。深い緑色の大きな葉には光沢があり、葉脈がくっきりとしていてとてもきれいです。
上手く育てると真っ白な花のようなものを咲かせますが、正式にはこの部分は花ではなく、仏炎苞といわれる部分です。花言葉が「爽快」「清々しい日々」というだけあって爽やかな雰囲気を持つ植物で、花序を覆い包むような仏炎苞は非常に美しく、絹のような繊細な印象があります。
この白い仏炎苞と緑の葉のコントラストがとてもきれいで、切り花としても人気があります。これらの特徴から、スパティフィラムという名前はギリシア語のSpathe(仏炎苞)とPhyllion(葉)から付けられました。スパティフィラムは難しい手入れを必要とせず、
日陰にも強いので、室内で鑑賞するのにも向いています。非常に存在感のある植物ですので、シンプルに花瓶に活けるだけでも華やかさを演出してくれます。高級感と華やかさがあり、それでいて凛としている植物ですので、贈り物としても人気があります。
花束などに使用されたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。最近ではこの白い仏炎苞を年中楽しみたい方の為に、スパティフィラムの造花も多く作られるようになってきました。シルクフラワーや、ペーパーフラワー、パンフラワーなど、様々な素材で作られ、雑貨屋さんなどに並んでいます。
スパティフィラムの特徴
スパティフィラムは光沢のある葉と白い仏炎苞のコントラストが非常に印象的な植物です。よく勘違いされがちですが、仏炎苞の中に包まれている黄色い棒状のものが花序と呼ばれるスパティフィラムの花にあたる部分で、甘い香りを漂わせることもあります。
観葉植物の中には花を咲かせるものが少ないので、このように葉と花穂を楽しめるタイプはより親しまれるのでしょう。スパティフィラムは育て方が簡単で、病気にもなりにくい植物です。難しい手入れを必要とせず、比較的簡単に増やすことも出来るのも人気の理由の一つでしょう。
上手に水やりと温度管理をしてあげれば、年に何度も花穂をつけますので、一年中楽しむことが出来ます。また、花穂を摘まずに育てていると種をつけることもあります。もしスパティフィラムの種が採取出来たら、是非発芽させて、種から育てることにもチャレンジしてみましょう。
スパティフィラムには様々な品種があります。株が大きめのキャニフォリウムや、葉にビロードの様な独特の光沢を持つフロリブンドゥム、日本で作られた中型のメリーなどが代表的です。また、コンパクトな鉢で栽培するのに向いているドミノは、小さめの株で、葉に斑が入るのが特徴的です。
大きさは品種によって異なりますが、30センチくらいの高さのものから、1メートル近くなるものまであります。葉が大きく広がらずスラリとした形状ですので、比較的大きめの株でも圧迫感がなく、あまり置く場所を選びません。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ディフェンバキアの育て方
タイトル:アロカシアの育て方
タイトル:ウラシマソウの育て方
タイトル:ツワブキの育て方
-

-
セッコクの育て方
セッコクは単子葉植物ラン科の植物で日本の中部以南に分布しています。主な生息地は岩の上や大木で、土壌に根を下ろさず、他の木...
-

-
プテロスティリスの育て方
プテロスティリスは、オーストラリアの南東部が主な生息地であり、ニュージーランドやニューカレドニア、パプアニューギニアと言...
-

-
カンナの育て方
原産地は熱帯アメリカで日本には江戸時代前期にカンナ・インディアカという種類のものが入ってきて、現在では川原などで自生して...
-

-
ゴールデンクラッカーの育て方
この花についての特徴としてはキク科、ユリオプス属になります。花が咲いている状態を見るとキクのようには見えませんが、黄色い...
-

-
スターアップルの育て方
スターアップルは熱帯果樹で、原産地は西インド諸島および中南米です。アカテツ科のカイニット属の常緑高木です。カイニット属と...
-

-
ハナズオウの育て方
ハナズオウはジャケツイバラ科ハナズオウ属に分類される落葉低木です。ジャケツイバラ科はマメ科に似ているため、マメ科ジャケツ...
-

-
ジュエル・オーキッドの育て方
種類としてはラン科になります。通常園芸分類においてはランとして分類することが多いですが、葉っぱを中心に楽しむものに関して...
-

-
クラブアップルの育て方
科名はバラ科であり属名はリンゴ属、学名をMaluspumilaと言い、和名をヒメリンゴと呼ぶのがクラブアップルです。リン...
-

-
ミズナの育て方
水菜の発祥地は静岡県小山町阿多野といわれており、JR御殿場線、駿河小山駅近くに水菜発祥の地を記した石碑が立っています。静...
-

-
レウカデンドロンの育て方
「レウカデンドロン」は、南アフリカ原産の常緑低木で熱帯地域を中心に広く自生しています。科目はヤマモガシ科レウカデンドロン...




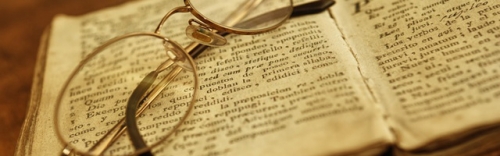





スパティフィラムは中央アメリカから南アメリカの熱帯地域を原産とするサトイモ科の多年性植物です。主に森林の湿地帯を生息地としており、およそ30種類ほどあるといわれています。