サクラソウの育て方

サクラソウの育てる環境について
サクラソウの開花時期は4月から5月で、中央部分から1本の花茎を出し、小さな数輪の花を咲かせてくれます。春が終わり6月頃になると葉が黄ばんで枯れはじめ、夏から秋にかけての時期は休眠期となります。乾燥には弱いサクラソウですが、他の植物同様に土は水はけの良いものが適しています。
サクラソウの育て方としては、まず芽が出て花が咲き終わる6月頃までは、日光に良く当てて育てることが重要です。暑さは苦手な植物なので、夏の暑さが激しい時期は、風通しが良い日陰で育てるのがおすすめです。自然環境の中でたくましく生きることができる野生種の場合は問題ありませんが、
それ以外の園芸種は雨に弱く、雨が直接当たってしまうと、花や葉が傷むことがあるので気をつけます。一方寒さには強い植物なので、寒さ対策は特に必要ありません。サクラソウの植え替えをするときは、植え替えに適した時期は休眠期にあたる冬となっています。
寒さに強い植物とはいえ、厳寒期の作業は避けるようにします。植え替えのボリュームとしては、5号鉢に4芽くらいを植えるのが目安となります。鉢の底にごろごろした軽石を多めに敷き、水はけが良くなるように配慮します。そして古い土をよく洗い流し、
鉢の中に根を浅く広げるようにし、芽は先が少し上を向くような雰囲気で横向きに置いて植えます。土は芽に2cm程度かぶせるように優しくかけます。地植えする場合は野生種や強い園芸品種を選ぶようにし、落葉樹の下などに植えるのが適しています。
種付けや水やり、肥料について
サクラソウは元々川岸などに広く自生する植物なので、湿り気のある土地を好みます。乾燥には弱いため、水やりに関しては良く気を配り、土を乾燥させないことが重要です。土の表面が乾いてきたら水をたっぷり与え、芽が出てから花が咲くまでの時期には特に水が豊富に必要になるので、
多めに水を与え水切れしないよう注意します。冬の休眠期は日照もきつくなく土もすぐ乾かないので、水やりは控えめに行いましょう。肥料は芽が出てから花が咲き終わるまでの間、液体肥料を1週間に1回程度与えます。肥料を与えるとどんどん葉が大きくなりますが、
肥料を与え過ぎると根腐れを起こすことがあるので気をつけましょう。培養土を使用している場合、培養土自体に肥料分が加えてあれば、追加で肥料を与える必要はありません。サクラソウの花が咲き終わった後は、花がらを折り取って、根元に培養土を2cm程度かける増し土という作業を行います。
サクラソウは地面の際に新しい根茎を作り、次の春そこから芽を出して成長していきます。そのためそのまま何もしないで放置していると、根茎の一部が地表に出た状態のままになってしまうので、乾燥して弱ってしまいます。
増し土はサクラソウを乾燥から保護する大切な作業であり、翌年の芽が順調に発育するために必要な作業で、これを行わないと上手に芽が出ないことがあるのでぜひ行いましょう。増し土の際には同時に薄い液肥を与えると、より発育を促し翌年の花への期待が高まります。
サクラソウの増やし方や害虫について
サクラソウを増やす方法は、種から育てるのはもちろんのこと、植え替え時に株分けすることもできます。種を蒔く方法としては、まず6月頃、花が咲いた後にできる種をを採取します。そして湿らせた砂の中に種を入れ、冷蔵庫など涼しい場所で保存して、翌年の初春に蒔きます。
早ければ種を蒔いた翌年から花を咲かせてくれます。種を保存する際には、乾燥させてしまうと発芽率が非常に落ちてしまうので、湿度を保つことが重要です。株分けの方法としては、黒くなった根茎を取り除くと自然に株分かれの状態になります。
切り口の処理などは特にする必要はありません。根伏せの場合は植え替えの際に、できるだけきれいで太い根を選んでカミソリやカッターで切り、切り口を上にして浅く植えるようにします。できる苗はとても小さく、開花までに2年はかかります。
園芸品種のサクラソウでは、株分けか根伏せが基本です。花を育てる際には、病気や病害虫に注意する必要がありますが、サクラソウにとっての病害虫は、主にアブラムシやヨトウムシ、ネコブセンチュウです。茎や葉、花にアブラムシやヨトウムシが発生するので、万が一見つけた場合には、
すぐ薬剤を散布して駆除するようにしましょう。ネコブセンチュウを見つけたときは、寄生部位を取り除いて新しい土で植え替えます。その際植木鉢はしっかり煮沸消毒し、再び病害虫が付かないようにしておきます。また、病気に関しては特にないので、気にする必要はありません。
サクラソウの歴史
サクラソウとは、サクラソウ科サクラソウ属(プリムラ属)の植物で、学名をPrimula sieboldiiといいます。日本での生息地は北海道南部から本州、九州などの広範囲に分布し、林間の湿った土地や原野に群生する多年草です。
原産国はシベリア東部から中国東北部、朝鮮半島、日本列島にかけての地域となっていますが、野生の群生はまれになってきています。埼玉県と大阪府の花に指定されているなど、日本のサクラソウの代表品種となっています。サクラソウ生育の歴史は江戸時代にさかのぼります。
江戸時代の中頃、荒川に野生していたサクラソウから本格的な栽培が始まりました。その栽培者の多くは、旗本や御家人などの武士階級の人々でした。種まきを繰り返しながら、白やピンク、紫、絞り模様などさまざまな色や大きさの品種が作られ名前が付けられるようになり、
江戸時代後半には、品種数がさらに豊富になったことから、花を持ち寄って品評会が行われるようになりました。明治維新後には衰退の危機もありましたが、、昭和の中頃にに愛好者のグループが全国各地に発足しはじめ、今も多くの愛好家たちによって育てられています。
このように昔から盛んに数多くの品種が作られた古典園芸植物でもあり、古典草花などと呼ばれることもあります。現在日本におけるその品種数は約300種類、世界に目を向けてみると約400種類にもなるなど、バリエーション豊かな花が楽しめる植物です。
サクラソウの特徴
サクラソウは多年草ですが、主な開花時期は4月~5月にかけてのあたたかい季節です。咲く期間が非常に短いことから、「青春のはじまりと悲しみ」、「運命を拓く」、「早熟と非哀」などといった花言葉を持っています。生育サイズは15cm~20cm、花自体は2cm~3cmほどと小さく、
白やピンク、紫などさまざまな花の色を見せてくれます。特に花の形が種類豊富で、最近では八重咲きのものも見られます。また、花びらの表と裏の色が異なった珍しい品種もあります。葉は浅く切れ込みの入ったしわの多い長楕円形で、葉や茎に白い軟毛が生えています。
根元から数枚葉を広げます。サクラソウはその生息地域の広さからも分かるように、さまざまな環境に耐えられる植物で、寒さに強いという特徴を持っています。しかし乾燥には少し弱い一面があります。そのため水が不足しないよう、水やりに関してはよく注意を払う必要があります。
また、暑さにも弱いため、夏など急激に気温が上がるような季節には、日陰に移動して育てるなどの配慮が必要になってきます。鉢植えではなく地植えする場合には、環境変化に強い野生種や、強いタイプの園芸品種を選ぶと、
スムーズに栽培が進みます。サクラソウは鉢植えにして階段状に飾ると見栄えがするので、趣味の花作りに適しており、初心者にもぴったりの植物です。また、大きな植木鉢やプランターにたくさん植えると、ボリューム感がありまた別の楽しみ方ができます。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:オカトラノオの育て方
タイトル:シランの育て方
タイトル:シャクヤクの育て方
-

-
グロキシニアの育て方
グロキシニアの科名は、イワタバコ科 / 属名は、シンニンギア属となり、和名は、オオイワギリソウ(大岩桐草)といいます。グ...
-

-
ネコヤナギの育て方
ネコヤナギの特徴は、なんといってもその見た目にあるでしょう。種類によって多少の違いはあるものの、ネコヤナギと聞けば誰しも...
-

-
モウセンゴケの仲間の育て方
まずは種類としてはウツボカズラ目、モウセンゴケ科になります。その他の名前としてはドロセラがあります。コケとなっている名前...
-

-
漬け菜類の育て方
アブラナ科の結球しない葉菜のことを漬け菜類と呼んでいますが、主な種類と分類と言うのは多種多彩であり、アブラナ類には春先に...
-

-
アストランティア・マヨールの育て方
アストランティア・マヨールは、中央・西部ヨーロッパが原産のセリ科の宿根草で、生息地は主にヨーロッパからアジアの西部にかけ...
-

-
オーストラリアン・ブルーベルの育て方
豪州原産の”オーストラリアン・ブルーベル”。白やピンクや青の花を咲かせるきれいな植物です。名前にオーストラリアンと付いて...
-

-
オカトラノオの育て方
オカトラノオはサクラソウ科の多年草で、その歴史としては中国を生息地としていたこの種類の植物が朝鮮半島を経由して日本に入っ...
-

-
きつねのぼたんの育て方
きつねのぼたんはキンポウゲ科の多年草です。分布は幅広く北海道、本州、四国、九州、沖縄や朝鮮半島南部にも存在します。原産は...
-

-
スカビオーサの育て方
別名を西洋マツムシソウといいます。英名ではピンクッションフラワーやエジプシャンローズ、スイートスカビオスなどあります。ス...
-

-
植物栽培の楽しみ方について。
私たちは、身近に植物が生息しているのを知っています。いわゆる雑草は、育て方を教えなくても、年から年中、切っても切っても生...




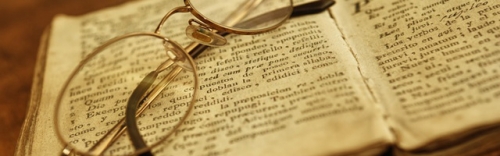





サクラソウとは、サクラソウ科サクラソウ属(プリムラ属)の植物で、学名をPrimula sieboldiiといいます。日本での生息地は北海道南部から本州、九州などの広範囲に分布し、林間の湿った土地や原野に群生する多年草です。