アンズの育て方

アンズの育てる環境について
日本のアンズの主産地は青森県です。プランド名のついたアンズも作られており、梅干しのように加工されています。主な栽培地は青森県、長野県、福島県、広島県、埼玉県で、どちらかというと北部の地域が多いです。
ちなみに、世界規模ではトルコ、イラン、ウズベキスタン、アルジェリア、イタリア、などで栽培が盛んです。冷涼な地域を好むため、熱帯では栽培できません。日本は温帯がほとんどで、栽培にはそれほど不向きでもありませんが、品種によっては暑さに弱くてやられてしまうものもあります。
東北以北ならば育てやすい気温と環境が揃っているといえるでしょう。暑さには弱いですが、日光を好む植物です。庭植えでは植え付け場所に注意して、十分な日光が当てられるようにします。鉢植えの場合には後から移動が可能ですからそれほど気にしなくても良いですが、
その場合には植え付け後の移動の管理をしっかりするようにします。水はけが良い場所を選んであげれば、それほど土にはこだわらなくても大丈夫です、庭の土をそのまま使うのが心配であれば、小粒の赤玉土:腐葉土=7:3の混合度を自分で作り、そこに植え付けてあげると良いでしょう。
この土の配分はほとんどの植物で使えます。品種によっては暑さに比較的強いもの、寒さにとても強いもの、虫や病気に強いもの、などがあるので、うまくいかない場合には品種を変えて、育てる場所の調整をしてみるとうまくいく可能性がアップします。
アンズの種付けや水やり、肥料について
種付けは12〜3月が一番適しています。春に花を咲かせる植物は、タイミングを守ることが上手に育てるための基本です。秋のあまり早い時期に蒔いてしまうと十分に成長できませんし、逆に遅すぎるとタイミングを逃して発芽できなかったり、形や姿勢が悪くなることが多いからです。
水やりに関しては、土の表面が乾いたらあげるという基本のあげ方でOKです。鉢植えの場合には下の穴から少し水が流れ出るくらいたっぷり目にあげても大丈夫です。庭植えであれば降雨に任せるくらいで大丈夫です。自分で特別水やりをしなくても、名駅や植え付け後も育ちます。
水やりに関しては庭植えはかなり簡単です。ただし、夏の暑い時期には土がカラカラに乾燥してしまわないようにだけ注意します。あまり乾燥してしまうと木の色が悪くなったり、結実しなくなる可能性もあります。肥料については、庭植えは2月と10月に与えます。
鉢植えは2月、5月、10月に与えれば良いです。与える肥料には有機性の肥料か、もしくは速効性の化成肥料を使います。庭木のような植物には緩行性の肥料を使うのが基本ですが、アンズは果実も採れる木なので、有機肥料や速効性の化成肥料が適しています。
速効性の肥料は栄養が回るのがとても早く、すぐに植物の体内にエネルギーを与えることが出来ます。元気が無くなってきたと感じたときにも、速効性の肥料を与えれば回復できる可能性もあります。水やりはほどほどに、速効性肥料を活用しましょう。
アンズの増やし方や害虫について
アンズの一番難しいところは、病気と害虫の被害の可能性が大きいところです。実に虫がついてしまうと食用に適さなくなってしまうので、十分に気をつける必要があります。病気には黒っぽい斑点ができる灰星病、黒星病、胴枯病、梢枯(しょうこ)病など、実に様々なリスクがあります。
これらの病気にかかると幹、枝、梢が枯てしまう恐れがあるので病気の予防に徹します。害虫も多く、シンクイムシ、アブラムシ類、コスカシバ、カイガラムシ、などがつく可能性が高いです。もっとも厄介なのは実中に入るシンクイムシです。
名前からも想像できるように、実中に入り込んで芯の部分を食べてしまいます。また、コスカシバは幹に入り込んでしまいます。アブラムシ類も厄介で、新しく出た梢を枯らしてしまったり、枝の汁を吸って病気にさせてしまうことがあります。
アブラムシ類の対策には、スプレーなどを活用するようにしましょう。高さはさほど高くないので、立ったまま噴霧しても十分駆除出来ます。それぞれの害虫が活動する時間にあわせて対処するようにしましょう。増やし方は休眠枝接ぎで、2月下旬〜3月中旬に行います。
台木には種を蒔いておいたアンズを使います。他にも、アンズと梅を掛け合わせた雑種の品種を使うことも可能です。芽接ぎは8月下旬〜9月上旬が適しています、台とする期は休眠枝接ぎと同じようにしてあげれば良いでしょう。害虫と病気に気をつけて、育て方を確認しましょう。
アンズの歴史
アンズはヒマラヤ西部からフェルガナ盆地にかけてを生息地としている、バラ科サクラ属の落葉小高木です。英名ではアプリコットとも呼ばれます。中国北部で形成された品種には、梅との交配種もあります。中国が原産で、日本には奈良時代の書物にすでにその名前が登場しています。
アンズは中国原産ですが、その後ヨーロッパで品種改良され、果実が甘くされているものもあります。これに比べるとアジア地域で栽培されている品種は酸味が強く、酸っぱさが残ります。中国では4,000〜2,000年以上も前から種の中にある杏仁(きょうにん)を採取するために作られていたとされています。
杏仁はそのまま食べるのではなく、漢方薬として使われることが多かったようです。その後中国からヨーロッパ、中東、アフリカといった諸外国に渡り、18世紀の初頭にアメリカに渡ったとされています。日本に入ってきた起源ははっきりしていませんが、
平安時代の書物に「唐桃(カラモモ)」という表記があることにより、その和名からこの頃にはすでに入り、栽培が始まっていたのではないかと考えられています。この時代は今のようにフルーツとして食べる目的ではなく、
中国のように漢方薬用として杏仁を取るために栽培されていたと考えられています。日本で本格的にアンズを食べ始めたのは明治時代からで、さらに大正時代に入ってからヨーロッパの食用に適した改良された品種が出回って食用になったとされています。
アンズの特徴
アンズはバラ科の植物で、アーモンド、梅、スモモの近縁種です。梅の果実は完熟しても甘くなりませんが、アンズは甘くなり、さらに種と実が離れるという特徴(離核性)があります。耐寒性の高い植物で、比較的涼しい土地で生育されています。
3月下旬〜4月頃に淡い紅色の花を咲かせて、夏には梅によく似た実をつけます。アンズは食用としてもよく使われますが、花が美しいために観賞用として用いられることもあります。果実は食用として使えて、そのまま食べる生食のほか、ジャムなどに加工されて長期間保存されることもあります。
そのほか、ドライフルーツとして食べられることもあります。種子の部分は杏仁(きょうにん)といって咳止めとして使われることもあり、風邪の時に使う生薬の一つとして使われることもあります。家庭用の果樹というイメージが強いですが、
温暖化の影響で近年は日本では育てにくい植物の一つになっています。本来は夏の植物で、雨の少ない冷涼な地域を好みます。基本的には自家結実しないとされていますが、品種によっては自家結実させやすいものもあります。形態は中高木で、そのため比較的手入れしやすいです。
収穫期は6中旬〜7月上旬で、暑さにはあまり強くないですが、寒さにはとても強いです。花と実のどちらも楽しめる植物として家庭用に使われていましたが、近年では温暖化の影響で園芸品種としてはやや難易度が高い植物という認識が定着しているようです。
庭木の育て方や色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も参考になります♪
タイトル:イヌツゲの育て方
-

-
オヒルギの育て方
オヒルギはマングローブを構成する植物の種類のうちの一つです。仲間の種類として、ヤエヤマヒルギやメヒルギなどがあります。自...
-

-
メギの育て方
メギはメギ科メギ属の仲間に入るもので、垣根によく利用される背の低い植物です。メギ属はアルカロイドという成分を含んだ種類が...
-

-
フリージアの育て方
フリージアは南アフリカ原産のアヤメ科の植物です。ケープ地方に10種類あまりが分布していますが、現在よく栽培されているもの...
-

-
オドントグロッサムの育て方
オドントグロッサムはラン科の植物で様々な品種が含まれています。オンシジウムに近い植物で花弁が大きくて、斑紋が入っているも...
-

-
ヘリオプシスの育て方
特徴としてはこの花は1年草になります。キクイモモドキの名前の元になっているキクイモに関しては多年草ですから、その面では異...
-

-
セリンセ・マヨールの育て方
セリンセ・マヨールは、セリンセの園芸品種です。セリンセはムラサキ科キバナルリソウ属の一年生です。「黄花瑠璃草」という和名...
-

-
ペラルゴニウムの育て方
和名においてアオイと入っていますがアオイの仲間ではありません。フクロソウ科、テンジクアオイ属とされています。よく知られて...
-

-
ハーデンベルギアの育て方
ハーデンベルギアはオーストラリア東部に位置するタスマニアが原産のツル性の常緑樹で、コマチフジ・ヒトツバマメ・ハーデンベル...
-

-
サンギナリア・カナデンシスの育て方
サンギナリア・カナデンシスとはケシ科サンギナリア属の多年草の植物です。カナデンシスという名の由来はカナダで発見されたこと...
-

-
ユリ(百合)の育て方
ユリに関しては、北半球のアジアを中心に広く分布しているとされています。亜熱帯から温帯、亜寒帯にかけても分布されている花に...




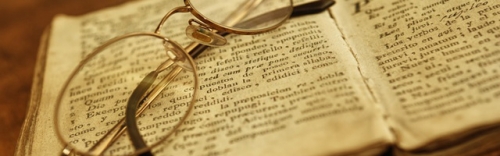





アンズはヒマラヤ西部からフェルガナ盆地にかけてを生息地としている、バラ科サクラ属の落葉小高木です。英名ではアプリコットとも呼ばれます。中国北部で形成された品種には、梅との交配種もあります。