サトウキビの育て方

サトウキビの育てる環境について
サトウキビの植え付けと言うのは、大きく分けて3つになります。夏植え、春植え、株出しと言う3つの種類であり、夏植えは翌年の冬に収穫するもので、春植えはその年の冬に収穫するもので、株出しは夏植え栽培の時に収穫後に出て来る地下株から再び出る芽を収穫するものです。
尚、海外での栽培と言うのは、植え付けを行った後は、刈入れを行うまでの間は人手による世話は行わないと言われていますが、日本国内においては植え付けを行った後は、雑草の防除、発根を促進させたり、地上部の倒伏を防ぐなどの世話を行いますし、
養水分の吸収を高めるために1~2度の培土を行うと言います。収穫を行う時には最初に葉を落としてから、茎部分を土の上で切り取り、倒れた茎を束にした状態で畑から運び出して行きますが、これらの作業と言うのは人力による作業であると言います。
最近は、収穫機械を利用して収穫を行う農家も増えており、従来と比べると収穫時期の仕事量が減ると言うメリットが有ります。尚、育てる環境と言うのは生息地からしてみても、気温が高く湿度が一定にある場所が好ましい環境となっていますが、
日本国内における産地と言うのは沖縄県(主に多良間島、小浜島、西表島、波照間島、与那国島、伊平屋島、粟国島などの7つの離島)や奄美群島、九州地方や高知県や愛媛県、徳島県、香川県などの地域でも栽培が行われており、比較的高温の気候を持つエリアで栽培が出来る植物と言われています。
種付けや水やり、肥料について
サトウキビはキビなどとも呼ばれていますが、キビの植え付けは夏と春と株出しの3つになります。夏植えや春植えは挿し木植えと呼ばれる育て方であり、サトウキビの枝を挿して栽培をしていくのが特徴です。夏植えでは1年半、春植えでは1年かけて育成をさせて、どちらの場合も春先に収穫を行います。
国内においては、水見まきをしてあげたり、培土を施してあげるのですが、海外においては植え付けを行って収穫を行うまでの間は特別な事をしないと言われています。しかしながら、日本のキビは世界の中から見ても、ミネラルやビタミンが豊富であり、
大地の恵みをしっかりと吸収させるためには世話をしてあげることが大切です。尚、株出しは収穫をした後の株から発芽させて育てる方法ですが、他力の低下が起きるため3年間ほど栽培を行った後は、紅芋などの農作物を植えて畑を休ませてあげることが大切で、
連作障害が有るので注意が必要です。また、畑を休ませた後は、夏場に挿し木植えを開始します。植え付けを行う時には茎を30センチ程の長さにカットをしてから横に並べて土に埋めておくことで、一定期間後に節部分から発芽します。
因みに、沖縄県などでは秋の風物詩としてキビの白い穂が畑一面を覆い尽くす光景を目にする事が出来ますが、この白い穂が出そろう事で収穫時期を迎えることになります。また、キビと言うのは気温が低下する事で成長が緩やかに変化をし、茎の中の糖分が増すと言われています。
サトウキビの増やし方や害虫について
春植えや秋植えはキビの枝を30センチほどの長さにカットしてから畑に並べて、土の中に埋めていきます。因みに、キビには株出しによる植え付けも有りますが、新しく植え付けを行わなくても3回から4回ほど収穫が出来るのは株出しを含めることが出来るからで、
収穫を終えた後はそのままにしておくことで節から発芽をして新しいキビを育てることが出来ます。そのため、植え付けによる労働力の軽減を図れると言うメリットが有ります。因みに、春植えの場合は3月から5月頃にに植え付けを行い、
翌年の1月から3月頃が収穫となり、6月から12月が管理時期となります。一方、夏植えの場合は植え付けが7月から9月頃、収穫時期は翌々年の1月から3月頃が収穫時期となり、夏植えの方が管理時期が長くなるのが特徴です。植付前に畑を耕しますが、
この時出来る限り深く掘りながら耕す事がポイントです。苗の植え付けの間隔は120cm~135cm程、深さは30cm程にし、植え付け前の肥料散布を行っておきます。この後植え付けを行うと、2~3週間ほどで発芽が行われ、この後に2回目の肥料散布を行います。
ある程度成長が行われたら培土を施して土寄せを行っておいて、定期的に除草や防除、灌水を施します。尚、サトウキビは農薬や除草剤を散布する事で害虫から守ることが出来ます。特にハリガネムシはサトウキビの芽を食し害を与えるので注意が必要です。また、出穂と呼ばれる白い穂が出て来たら収穫となります。
サトウキビの歴史
サトウキビはイネ科の多年草で、東南アジアや、インド、ニューギニア島などが原産と言います。また、インドの中でもガンジス川流域などが原産とも言われており、製糖作物として熱帯地域を中心に世界各地での栽培が行われており、日本国内においては沖縄県などが代表的な生息地と言われています。
サトウキビは紀元前4世紀頃に地中海地方で栽培が行われていたと言いますが、日本に伝来したのは江戸時代の初期頃であり、この時代に中国から渡来したと言います。熱帯や亜熱帯と言った気候を好むのが特徴で、茎の高さは2メートルから3メートルになり、節を含む茎部分で増殖をするのが特徴です。
尚、日本では中国から沖縄県などに伝わったと言いますが、現在栽培されている地域と言うのは、鹿児島県奄美諸島や沖縄県全域などであり、中でも南大東島や与那国島、宮古島などの島々で栽培が行われており、黒糖などの原料としての栽培が主流となっています。
尚、歴史の中には各地に広めた有名人が存在しているのが特徴です。例えば、薩摩藩は奄美大島諸島に広めたとしており、1695年の元禄八年に、サトウキビの値付け、栽培、そして製糖を監督する役人を奄美大島諸島に配置させ、1818年から1830年頃の文政の時代には、成人1人当たり約120kg以上の黒糖を納付させていたと言います。
また、サトウキビから取れる原料と言うのは焼酎の製造にも利用されていたと言いますが、奄美大島諸島での黒糖製造を薩摩藩は重要視していたことからも、サトウキビの収穫および製糖期などでは島民による焼酎製造を禁じていたと言われています。
サトウキビの特徴
サトウキビの茎と言うのは、高さが2メートルから3メートルに及ぶとされており、一見竹に似ているのですが、竹のように内側に穴があるわけではありません。また、丈の高さもさることながら、葉も広い線形になっておりトウモロコシの葉のように幅広い線計が特徴で、
サトウキビ畑を見ると解りますが、うっそうと茂る畑と言う感じになっています。尚、砂糖の原料や焼酎の原料などで利用されているのが特徴ですが、サトウキビは茎の汁液にショ糖と呼ばれる甘いエキスを含んでいるのが特徴で、これを煮詰めるなどして砂糖を作り出しているのです。
沖縄県などの代表的な名産としても知られており、お土産品なども黒糖などの商品は人気が高いものとなっています。熱帯や亜熱帯と言った気候を好むのも特徴で、砂糖以外にも搾り粕は燃料や飼料、パルプの原料などで利用されていると言われており、捨てる所が少ないのも特徴と言えます。
尚、サトウキビは別名「かんしょ」や「かんしゃ」(甘蔗)とも呼ばれていますが、呼び名は地域により様々であり、種子島などでは「おうぎ」と呼ばれ、奄美群島の中にある徳之島では「うぎ」、沖縄県などでは「ウージ」と呼ばれるなど、その地方独特の方言でこのように呼ばれているのも特徴です。
また、砂糖の原料にはテンサイが在りますが、サトウキビから作られる黒糖と言うのは、ビタミンやミネラル分などの栄養分が多く含まれていると言われており、大地からの恵みをたっぷりと含んでいるのです。
イネ科の植物の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:フェスツカ・グラウカの育て方
タイトル:ススキの育て方
タイトル:ダイコンの育て方
タイトル:スプラウトの育て方
-

-
コールラビの育て方
コールラビとは、学名をBrassica oleraceaと言い、英語名をKohlrabiと綴ります。その形は球根とキャベ...
-

-
ほうれん草の育て方
中央アジアから西アジアの地域を原産地とするほうれん草が、初めて栽培されたのはアジア地方だと言われています。中世紀末にはア...
-

-
緑のカーテンに最適な朝顔の育て方
ここ数年毎年猛暑が続き、今や日本は熱帯よりも熱いと言われています。コンクリートやアスファルトに覆われた環境では、思うよう...
-

-
イワギボウシの育て方
名の由来として、日本の昔の木造の付ける欄干や橋寺社などの手すりには飾りがあり、この欄干の先端にある飾りのことを擬宝珠と呼...
-

-
キワーノの育て方
キワーノはウリ科でつる性の植物です。名前については企業の商標登録によってつけられたものですのでこれが正式な名称ではないよ...
-

-
バナナの育て方
バナナの歴史は非常に古く紀元前10000年前には既に人間に認知されており、栽培もされていたと言われています。現在我々が口...
-

-
ヤブジラミの育て方
分類はセリ科でヤブジラミ属ですが、原産地及び生息地ということでは中国から朝鮮半島、台湾、日本言うことで東アジア一帯に生息...
-

-
カモミールの育て方
カモミールは、現在では色々な国で栽培されていますが、原産は西アジアからヨーロッパです。西アジアからヨーロッパを主な生息地...
-

-
セロジネの育て方
セロジネはラン科の植物でほとんどの品種が白っぽい花を穂のような形につけていきます。古くから栽培されている品種で、原産地は...
-

-
ウラシマソウの育て方
ウラシマソウ(浦島草)は、サトイモ科テンナンショウ属の多年草で、日本原産の植物です。苞の中に伸びた付属体の先端部が細く糸...




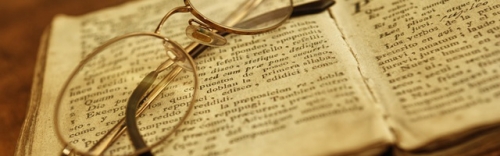





サトウキビはイネ科の多年草で、東南アジアや、インド、ニューギニア島などが原産と言います。また、インドの中でもガンジス川流域などが原産とも言われており、製糖作物として熱帯地域を中心に世界各地での栽培が行われており、日本国内においては沖縄県などが代表的な生息地と言われています。