エダマメの育て方

エダマメの育てる環境について
エダマメの生息地と言うのは、国内においては全国と言えますが、夏の野菜と言う事からも気温などが高い場所で良く育つ野菜となります。暖地などでは4月頃にポットまき、4月から5月の中旬ごろに直まきで、6月の中旬から8月の中旬頃が収穫時期となります。
寒冷地では、4月の下旬から5月の中旬頃がポットまき、5月の中旬から6月の中旬頃が直まきで、7月の中旬から9月の中旬頃が収穫時期となります。中間地では4月の中旬から5月の中旬頃がポットまき、4月の下旬から5月の下旬頃が直まきで、7月の上旬から8月の下旬頃が収穫時期となります。
育てる地域により種まきをする時期と収穫時期が異なりますが、4月から5月にかけて種まき、そして収穫時期は7月から9月頃が一般的と言えます。育てる環境と言うのは日当たりが良く、水はけが良い場所を選ぶ事です。
地植えでもプランターを利用しても成長をしてくれることや、初心者でも育てやすい品種が在ります。早生品種は生育日数が70~77日、極早生は大粒の実がつくエダマメで、奥原早生と呼ばれており、生育日数は70日程となり、収穫量が多い事や食味が良いと言われるビアフレンドは76日、
サヤが沢山実る白獅子は77日などの種類が在ります。これ以外にも、80日程度で収穫が出来る福成は中早生で家庭菜園に向いている種類で、エダマメと言っても色々な種類が在ります。尚、エダマメは連作障害を持つ野菜であり、同じ場所で2年間の作付けは出来ません。
エダマメの種付けや水やり、肥料について
エダマメを含む豆類と言うのは、根の部分に根粒菌と言われる窒素固定菌が共生をし、根粒を形成すると言った特徴を持ちますが、根粒菌は株からの栄養を吸収する代わりに、窒素分を株に還元しており、他の野菜のとは異なり肥料の量が半分ほどで済むと言う特徴があります。
そのため、普通の野菜と同じように肥料を与えてしまうと、ツルだけが伸びて実が付かないなどの結果に繋がるので注意が必要です。種まきをする2週間前に苦土石灰を1㎡あたり100gと、堆肥を3~5kgを混ぜて耕し、1週間前に有機配合肥料を80~100g入れて畝を作ります。
種は30センチぐらいの間隔て、3~4粒ずつまいていき、その後2センチほど土をかけます。本葉が2~3枚になったら、1~2枚を残して間引きをし、追肥を行います。また、エダマメの株から少し離れた場所に有機配合肥料20g(1㎡あたり)を追肥を行い、土と混ぜてから水やりをしておきます。
これを行う事で栄養を吸収し成長を促す効果を持ちます。また、背丈が20㎝ほどになったら土寄せを行い、土の表面を見て乾いている時などはたっぷりと水をあげ、花が咲いて実が大きくなるまでの間は乾燥した段階でその都度水をあげます。
尚、これは種を使っての育て方で有り、エダマメは苗を購入して育てる事も可能です。苗の場合も肥料を土に入れて準備をしておく事や土の状態を見て乾いているようであればたっぷり水をあげると言う事を行えば多くの実をつけることが出来ます。
エダマメの増やし方や害虫について
種を使って地植えで育てる場合は、4月から5月頃にかけて種まきをします。種をまく時には、2週間前に1㎡あたり苦土石灰100g、堆肥3~5kgを混ぜて耕し、1週間前に1㎡あたり有機配合肥料80~100g入れて畝を作り、畝に穴あきのポリマルチを張ってあげてから穴に種をまきます。
また、増やし方のコツとして間引きが必要です。葉が2~3本出た段階で間引きをしますが、こうする事で栄養を集中させ大きく育てることが出来ますし、花を多く咲かせることで多くのエダマメを収穫することが出来ます。
また、プランターやコンテナなどを使って栽培する事も可能で、市販の野菜用培養土、用土1リットル当たり、粒状肥料を4g混ぜ合わせて土を作り、20㎝の間隔で1か所あたり3~4粒の種をまいていきます。尚、エダマメは害虫だけではなく鳥害を受ける野菜でもあり、
本葉が出るまでの間は寒冷紗などを利用して保護してあげる必要が有ります。また、成長する事で鳥害を受けやすくなりますが、ネットなどを利用して防御しておくと安心です。害虫についてはアブラムシ、開花直後にはカメムシ、マメシンクイガなどの被害を受けることが在ります。
葉が食害されてしまい、被害が酷い時などは葉脈だけ残して食べ尽くと言う害虫がヨトウムシです。ヨトウムシはエダマメの葉などを食べてしまうので、何れの害虫を見つけた時は殺虫剤や殺虫殺菌剤などを利用して害虫の退治する事が大切です。
エダマメの歴史
エダマメは「枝豆」と書きますが、ビールには欠かせないおつまみとして人気が高い野菜です。そもそもエダマメと言うのは未成熟の状態の大豆であり、完熟すると大豆となり、醤油や味噌などの原料として利用されます。そのため、エダマメの歴史と言うものは、枝豆としての歴史と、
大豆としての歴史の2つが存在しており、枝豆については奈良時代や平安時代などで食されていたとも言われています。また、江戸時代の中期の書物の中には、大豆をサヤ葉の柔らかい状態で食べる、夏に枝豆売りをする人を町で見ると言った事が書かれていると言われています。
尚、枝豆という名前の由来と言うのは、庭先やあぜ道などで栽培していたため、古くは「畦豆(アゼマメ)」などと言われており、この畦豆が枝付きの状態で販売が行われた事や、食べられていたなどの理由から、「枝付き豆」と呼ばれるようになり、後に枝豆と言った呼び名に変化されたと言われています。
一方、大豆における原産地と言うのは東南アジアに自生していた野生種のツル豆が、中国の東北部で分化して出来たと考えられている反面、稲と同様に中国の南西部の雲南省であるとも言われており、どちらが正確なものであるのかは特定されていないと言います。
尚、枝豆も大豆もどちらも古くから食べられていた事や、江戸時代の書物の中には夏に食べると言う事が記されていた事からも、江戸時代の人々も現代人と同じく、お酒のおつまみとして枝豆を食べていた可能性も有ると言えるのです。
エダマメの特徴
未成熟の大豆がエダマメと言う事もあり、大豆同様に栄養価が高い野菜として知られています。どのような栄養を持つのかと言いますと、枝豆は豆と野菜の2つの栄養を持つと言う緑黄色野菜になります。大豆は畑の肉と言われていますが、
エダマメにおいても良質なたんぱく質、ビタミンB1、カリウム、鉄分、食物繊維などを含んでおり、大豆には少ないとされるβ-カロチンやビタミンCなどを含むのが特徴です。お酒のおつまみとして食べる人が多いのですが、これはアルコールの分解を促す効果を持つことや、
飲み過ぎ、二日酔いなどにおいての効果を持つことからもお酒を飲む時のおつまみとして食べることは良いと言われています。エダマメの栄養素の中には良質なタンパク質が含まれており、その中でもメチオニンと呼ばれる成分はビタミンB1やビタミンCなどと一緒に、
アルコールの分解を促す効果を持つ成分であり、枝豆を食べることで悪酔いなどと言われているのです。ビタミンB1は消化液の分泌を促し、糖質をエネルギーに変える働きが在り、疲労回復効果やスタミナ不足の解消などに役立てることが出来ます。
カリウムはミネラル成分の1つであり、身体の中の塩分を分解する効果や利尿作用を持ち、鉄分は貧血予防に役立てることが出来ます。尚、枝豆を茹でる時は塩を少々入れてゆでたり、茹であがった後に軽く塩を振りかけて食べますが、これは味を付けるという意味だけではなく、色を綺麗に見せるという緑黄色野菜の特徴と言われています。
野菜の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ソラマメの育て方
タイトル:トウガン(ミニトウガン)の育て方
タイトル:小カブの育て方
-

-
エゴノキの育て方
日本全土と中国、朝鮮半島を生息地とするエゴノキは、古くから日本人の生活になじみ深い樹木です。チシャノキやロクロギなどの別...
-

-
キンロバイの育て方
キンロバイの科名は、バラ科 / 属名は、キジムシロ属(キンロバイ属 Pentaphylloides)です。キンロバイは漢...
-

-
レオノティスの育て方
レオノティスはシソ科の植物になります。きれいなオレンジ色の花をたくさんつけるのですが、見た目も鮮やかでパワフルな感じのす...
-

-
キンカンの育て方
キンカンは、他の柑橘類と同じように、元々の生息地はインドや東南アジアだと考えられています。この地域のものが中国で栽培され...
-

-
アイノカンザシの育て方
アイノカンザシはユキノシタ科の植物ですが、別名をエリカモドキともいいます。植物の中でも呼び名がとても印象深く、イメージも...
-

-
エゾギク(アスター)の育て方
中国や朝鮮が原産の”アスター”。和名で「エゾギク(蝦夷菊)」と呼ばれている花になります。半耐寒性一年草で、草の高さは3c...
-

-
ミヤコササの育て方
ミヤコササは、イネ科でササ属の多年草です。北海道の南部から九州までの太平洋側に生息していますから、山地でよく見るササ類で...
-

-
ツンベルギアの育て方
ツンベルギアはヤハズカズラ属の植物でアジアの熱帯地方や亜熱帯地方とマダガスカルやアフリカの中南部などに約100種類以上が...
-

-
シラタマノキの育て方
シラタマノキは学名をGaultheriamiquelianaといい、ツツジ科のシラタマノキ属になります。漢字にすると「白...
-

-
モンステラ(Monstera spp.)の育て方
モンステラはサトイモ科に属するつる性の植物です。アメリカの熱帯地域を原産とし、約30種の品種が分布しています。深いジャン...




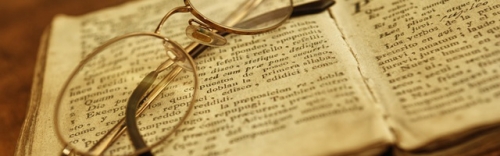





エダマメは「枝豆」と書きますが、ビールには欠かせないおつまみとして人気が高い野菜です。そもそもエダマメと言うのは未成熟の状態の大豆であり、完熟すると大豆となり、醤油や味噌などの原料として利用されます。