ギボウシ(ホスタ)の育て方

ギボウシ(ホスタ)の育てる環境について
ギボウシやホスタは、少し湿気がある環境が好きなので育て方としては明るい日陰や日陰を選ぶといいでしょう。それを知らずに日当たりの良すぎるところで栽培していると、ギボウシやホスタの葉っぱが焼けてしまって本来の美しさを楽しむことができなくなるので十分に気を付ける必要があります。
特に、気温も上昇しやすい季節でもある5月~9月まではこの現象が起こりやすいので、できるだけ日陰で栽培するようにするといいでしょう。葉っぱを傷めることなく栽培するには、気温が上昇する季節になったら日差しを遮断する機能を持っているネットを使って少しでも強い光を浴びせないようにすることが大切です。
実際に遮光ネットを使うことで5割から7割の光を遮断することができるとされています。さらに効果を強めたいという場合は、ちょっとした棚を作ってそこにギボウシやホスタを栽培するようにするといいかもしれません。ギボウシやホスタの葉っぱの美しさを楽しむためには、絶対に必要な対策であると言えます。
どうしても、鉢植えではなく地植えをしたいという場合は年間の日差しの当たり方などを考えながらどこに植えるかを慎重に決めていく必要があります。ギボウシやホスタは寒さに強いので特に心配する必要はありませんが、
あまりにも寒い場合は葉っぱが凍ってしまうことがあり、結果的に枯れてしまう恐れがあります。そのため、寒い地域では地面を腐葉土などで覆うか室内で栽培するのが一般的であるとされています。
種付けや水やり、肥料について
気になる水やりですが、週に2回行うことが理想であるとされています。鉢に植えている場合は土の表面が乾いたら十分に水やりをします。また、地植えの場合は表土が乾いて植物自体が少し元気がないなと思ったら十分に水やりをします。
どちらも、栽培をしている側が肉眼で確認することができるので水やりのタイミングも他の植物に比べると分かりやすいということが言えます。鉢に植えている場合は、大きくなる品種であると初めから分かっている場合は鉢が小さいと水やりをする時も大変になるので、できるだけ少し大きな鉢を選ぶといいかもしれません。
また、1年の中でも休眠期となる11~3月はできるだけ水やりも控えめにしておくといいです。そして、ギボウシやホスタの肥料は1年に2回与える必要があります。具体的には、3月と9月にそれぞれ1回ずつ与えるのが一般的です。
どんな肥料を与えればいいのかと言うと、固形の油かすを与えることで美しい葉っぱや花を咲かせることができます。植え付け時に緩効性肥料を土に混ぜておくとスムーズです。そして、9~10月にはお礼肥を与えると頑丈な植物に育ちます。
方法としては、それぞれの鉢の大きさに合った量を自分で考えながら固形の油かすを与えます。土の表面に指で押し込みながら丁寧に行います。この時、たくさん肥料を与えすぎるといけないので適量を守ることが大切です。また、鉢植えではなく地植えという場合は基本的に肥料を与える必要はありません。
ギボウシ(ホスタ)の増やし方や害虫について
この植物の増やし方は、株分けの場合が多いです。方法としては、一度掘り上げた株を1株に3個以上の芽が付くように作業がしやすいようなナイフなどで分けます。3個以上に分けた株は、新しい芽が地面に隠れるくらいの深さに植えます。
そうすると、しっかりとした株を増やしていくことができます。また、害虫としてはナメクジが近寄ってきやすい植物です。ナメクジがいると、新しい芽やせっかく時間をかけて咲かせた植物の花を食べてしまいます。そのため、できるだけ早期発見に努めることが大切です。
その他にも、ネコブセンチュウやアブラムシが挙げられます。ネコブセンチュウという害虫は、植物の根っこにこぶを作ってしまいます。その結果、植物の株の成長を遅くさせ衰えさせるということになります。場合によっては根っこの茎までも被害にあってしまうこともあるので注意する必要があります。
気づかずに長い間放置することで、植物への被害も大きくなるのでこの害虫を見つけたらすぐに対処しておくといいでしょう。もちろん、株の植え替えをする時には被害にあった根を切り捨てておく必要があります。また、アブラムシは植物の若い葉っぱや花の茎、や蕾などについて被害を及ぼします。
ウイルス病を媒介する害虫なので、これもまた同様に日ごろからしっかりと注意しておかなければいけません。一生懸命育てた株が害虫によって健康に育たなくなるのはとても悲しいことなので、対策は油断せずにしっかりとしておくといいでしょう。
ギボウシ(ホスタ)の歴史
ギボウシは別名、ホスタという名前で古から世界中で親しまれています。もともとは、ギボウシは日本の里山のあらゆるところに自生していました。それをたくさんの人が協力して、日本独自の改良を積み重ねて園芸品種としてギボウシが確立しました。
時代としては、江戸時代の中期から後期であると考えられています。その結果、当時の日本のたくさんの人々にギボウシの育てやすさや美しさが受け入れられ、人々の家の庭などに植えられるようになりました。また、人々にギボウシが広まる中でこれは珍しいということでヨーロッ パでもギボウシはホスタとして紹介されました。
ギボウシを紹介した人は歴史的にも有名なシーボルトらであるとされています。また、シーボルトらが持ち帰ったとされる日本のギボウシは見た目も決して派手ではなく、大人しい雰囲気のものだったのでそれをヨーロッパの人々の感覚に合った品種へと改良していった結果、鮮やかな葉っぱの品種もグンと増えていきました。
ヨーロッパなどの国で品種改良されたギボウシは、ホスタとして名前が付けられて次々に様々な品種が作られました。これを受けて、ガーデニングで古くから歴史のあるオランダやアメリカ合衆国でもホスタはすぐに話題となり、
世界的にもかなり人気の品種になりました。そして、結果的に品種の数も現在では日本で初めて改良されて園芸品種となった時に比べると、海外で品種改良されたホスタの数はかなり多くなりました。
ギボウシ(ホスタ)の特徴
ギボウシまたはホスタの生息地は東アジアです。原産はギボウシの場合は日本です。
アメリカ合衆国でもかなり人気のある植物です。毎年花を咲かせる多年草なので、初心者も育てやすいとされています。品種によって大きさが違うので前もって調べておくといいでしょう。
咲く花は筒状で、一番先が膨らんで咲きます。色は品種全体で見ると白や紫が圧倒的に多く、中には香りがするものもあります。せっかく良い香りのする花を咲かせる品種もありますが、花は1日でしぼんでしまいます。また、日本にはたくさんの種類のギボウシが生息しています。
種類はおよそ20~40種類とされていますが、常に新しい品種が作られています。品種の分布には差がありますが、品種改良をする際にほかの植物に比べると雑種も作りやすいので、新しい品種が毎日作られているといっても過言ではない傾向にあります。
さらに、ギボウシやホスタの品種は新種を作ることができる可能性がかなり高いからこそ、分類や系統分けもたくさん存在するので分かりやすく表現するのであれば、1つの図鑑ができるくらいの品種が存在するとされています。
1年間の流れとしては、湿気の多い梅雨から暑くなる夏にかけて花の咲く茎を長く伸ばし、先っぽに花を咲かせます。寒い冬は葉っぱが枯れて休眠してしまいますが、春になるとまた新芽が出てきます。品種も充実しているということで、全世界でリーフプランツとしてかなり人気の植物であると言えます。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ティアレ・タヒチの育て方
タイトル:ジギタリスの育て方
-

-
ジューンベリーの育て方
ジューンベリーの原産と生息地は北アメリカ北東部です。アメリカザイフリボクのザイフリボクというのは漢字で書くと采振木となり...
-

-
マユミの育て方
マユミはニシキギ科に属しますが、ニシキギという名称は、錦のような紅葉の美しさから名づけられたと言われています。秋になると...
-

-
セイヨウタンポポの育て方
セイヨウタンポポは外国原産でそういうところから持ち込まれたタンポポであり、今では我が国を生息地として生えているタンポポで...
-

-
アキノキリンソウの育て方
アキノキリンソウは、古くから日本にありました。キク科植物は世界中にありますが、その歴史は非常に古いです。約5千年前に南米...
-

-
マツカゼソウの育て方
松風草は、一般的には、マツカゼソウと表記され、ミカン科マツカゼソウ属に属しており、東アジアに生息するマツカゼソウの品種と...
-

-
アジュガの育て方
薬草や園芸観賞用の花として、アジュガはヨーロッパ、中央アジア原産で江戸時代に伝来した歴史があります。また、日本でも数種類...
-

-
レプトシフォンの育て方
この花についてはハナシノブ科、リムナンツス属になります。属に関しては少しずつ変化しています。園芸における分類としては草花...
-

-
モミジバアサガオの育て方
モミジバアサガオは和名をモミジヒルガオといい、日本で古くから親しまれてきたアサガオの仲間です。日本へ伝来したのは今から1...
-

-
ほうれん草の育て方
中央アジアから西アジアの地域を原産地とするほうれん草が、初めて栽培されたのはアジア地方だと言われています。中世紀末にはア...
-

-
ナスの育て方
インドが原産の植物といわれ、中国でも古くから伝わる植物でもあります。栽培の歴史は数千年を超え、農業に関する世界最大の古典...




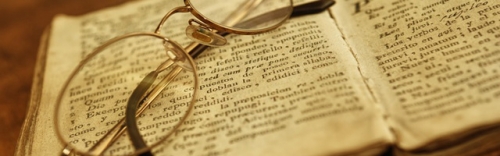





ギボウシは別名、ホスタという名前で古から世界中で親しまれています。もともとは、ギボウシは日本の里山のあらゆるところに自生していました。それをたくさんの人が協力して、日本独自の改良を積み重ねて園芸品種としてギボウシが確立しました。