マンリョウの育て方

マンリョウの育て方
もともとが温暖な気候の常緑樹林の林床で自生していますので、半日蔭や日蔭を好みます。そのため育てる時には、強い日差しや風が当たらないような、明るめの日蔭が適しています。乾燥を嫌いますので、腐植質を多く含んだ水はけのよい土壌を選びます。
サイクルとしては4月から5月に植え付けをし、7月に開花。白く小さな可憐な花を咲かせます。11月上旬から1月の終わりまでに結実します。気候によっても違いますが、大体5月までは実を楽しむことができます。
温度や直射日光、風などを避けると比較的環境に強い植物ですので、育て方は容易です。成長の遅い品種の場合には、挿し木や取り木などによって植え付けた時には、初年から花や実を楽しむことが難しいこともあります。
マンリョウの種付け
マンリョウは取り木や挿し木によって増やしますので、種付けから育てることはあまりしないという人も少なくありません。種付けから行う場合は、秋から冬に採取した熟した実の果肉だけを取り除き、タネを取りだします。乾燥すると発芽しなくなりますので、直ちに赤玉土小粒などに種付けします。
乾燥だけに気をつけていると、春には発芽を見ることができます。種付けを行わない場合には、取り木や挿し木によって増やすことになります。これはマンリョウの姿を美しく保つためにも必要です。マンリョウはもともと葉の数が少なく、他の葉の枚数を多くつける植物のように剪定をしないと姿が悪くなるといったことはありません。
長期間育てているうちに、下葉が落ちてゆきます。その後は上に伸び、腰高になってしまいます。これでは形状の見栄えがよくありませんので、仕立て直しを行います。葉が落ちてしまった幹の部分を使って取り木を行います。
5月から6月に幹や枝の部分にナイフなどで2センチから3センチほど切り込み、緑の部分を剥いで、白い部分を露出させます。そこにミズゴケなどを巻いてビニールシートなどで養生をし、上下をしっかりと縛ります。
このようにしておくと、2カ月から3カ月後には根が出ますので、親木に近い部分から上を切り取って、鉢などに植え替えを行います。この時の鉢の土は赤玉土の小粒を7割に対して腐葉土を3割といったものにし、半日蔭に置きます。ぐらつくようであれば、支柱などを立てましょう。
挿し木であれば、6月ごろをめどに3センチほどの長さの枝を切り、水揚げを1時間程度行います。その後挿し木用の土に指して、半日蔭で水分が不足しないように管理していると、3か月ほどで根が出てきます。挿す時に、切り口に植物成長調整剤などをまぶすと、更に発根を促します。
マンリョウの栽培の注意点
比較的温暖な地域であれば、庭植えは4月から5月に行います。根鉢の2倍程度かそれ以上の穴をあけて、腐葉土や粒状の肥料などを混ぜて、深植えに気をつけながら植えつけます。ぐらつくことがありますので、支柱をたてましょう。水やりは充分に行います。
鉢植えの場合には、温暖な地域では年間を通じて戸外でも栽培できますが、寒冷地の場合には11月から3月までの間は、室内に置くようにします。戸外におく場合には、直射日光を避け、冬場には冷たい風が当たらないように配慮します。
2年から3年で、鉢を一回り大きなものに植え替えを行います。中には生育の遅い班入りのような品種もありますので、その場合には根の様子を見て、根回りが少ないような時には、同じ大きさの鉢を使った植え替えても大丈夫です。
植え替えの時には根を切らないように気をつけます。細根が少ないため、根を切ってしまうとその後の成長に影響が出てしまいます。庭植えの場合には植え付ける場所の選定さえ間違っていなければ、特に水やりは必要ありません。
夏場など、極端に乾いているt期には、朝か夕方に水やりをします。鉢植えの場合には、春と秋は乾いてから水やりを行い、夏場はマメに、冬場は控えます。肥料は特別必要ありませんが、もしもっと株を大きくしたいという希望があるならば、2月の半ばあたりに粒状の肥料を与えます。
鉢植えでも同様ですが、その時は規定よりも若干少なめに与える方が良いとされています。害虫はほとんどつくことがありませんが、まれにカイガラムシなどが付いてしまうことがあります。幼虫の時期に殺虫殺菌剤などを撒いて防虫を行います。
マンリョウの歴史
江戸時代より日本で育種され、改良も重ねられた植物を古典園芸植物と称しますが、マンリョウもこのような古典園芸植物です。日本が園芸は西欧のような造園も含む立ち位置とは違い、芸道的な面が特化して発展してきました。精神修養や芸術的な側面も持つとはいえ、華道とは全く違う存在です。
マンリョウはそのような江戸時代の園芸の流行を支えた植物の一つに挙げられます。この時代に葉が縮れているものなどが、品種改良によって生まれています。十両と呼ばれるヤブコウジ、百両のカラタチバナ、千両のセンリョウとともに縁起植物になっています。
金額の違いは実の大きさや植物体そのものの高さや大きさによるものです。マンリョウは特に大きな実をつけ、おめでたい印象を見る人に与えています。更に実を大きくする品種改良を行った「宝船」などもあります。
冬に実が熟しますので、今でもお正月などにディスプレイされるのを良く目にします。赤色が日本独特の色彩にマッチしていますので、日本画や陶器のデザインなどに用いられることも多く、華やかさを添えています。
マンリョウの特徴
気候が温暖な東アジアからインドにかけて生息地とし、日本でも関東地方以西の四国や九州、沖縄地方に自生しています。原産地は日本、中国、朝鮮、インドです。繁殖力は強く、アメリカのフロリダにおいては外来有害植物になっています。
比較的寒さには耐えますので、庭木などにも用いられますが、品種改良によって班入りされた品種など冬の寒さに弱く、関東でも寒い日には屋内に入れるなどの工夫が必要です。ヤブコウジと大変似ていますが、ヤブコウジは高さが10センチほどにしか育たず、
マンリョウは30センチから1メートルほどになりますので、生えている様では区別が容易です。センリョウとの違いは実が上に向けて付くか、下に向いて垂れるか見分けます。下に垂れるのがマンリョウです。ヤブコウジ科として分類されることもありますが、
サクラソウ科のヤブコウジ属と分類されることが多くなっています。開花時期は6月の終わりから7月の終わりまでで、結実が11月の上旬から1月の終わりまで。これは気候によって左右されます。鑑賞記は12月から翌年の5月程度までとなっています。
互生葉序で、葉が膨れた部分に共生細菌が生息する部屋を形成しています。葉を光に透かすなどしてみると、黒い点を確認することができます。これは植物から栄養をもらう代わりに植物の育成を助ける細菌です。うどんこ菌のような「寄生者」ではありませんので、取り除く必要はありません。
また、品種は普通種のほかに実の白いシロミノマンリョウ、実が大きな宝船、葉が班入りの曙白鵬、白い実が大きな白大実などがあります。現在鉢植えなどで売られているものの品種のほとんどが宝船です。大変生育が旺盛で、株も大型です。
葉に班が入った曙白鵬は幼葉の時にはほとんど白色に見えますが、成長過程でだんだんと班が入ったようになり、最終的に縁以外はすべて緑色になります。実が白く大きな白大実は、初めは実も赤みを帯びていますが徐々に白くなり、最終的には黄色っぽいクリーム色になります。
庭木の育て方や色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も参考になります♪
タイトル:カラタチバナの育て方
タイトル:センリョウの育て方
-

-
エンジェル・トランペットの育て方
この花の特徴としては、ナスの種類になります。ナス目、ナス科、キダチチョウセンアサガオ属となります。この属の代表的な花とし...
-

-
ヒオウギの育て方
ヒオウギの名前を聞いて和歌を連想する人、京都の祇園祭を思い浮かべる人、様々ですが、原産国は東アジアとなっています。日本も...
-

-
クチナシ(実)の育て方
クチナシの特徴としては、やはり花の可憐さでしょうが、照り輝く白い色をしていて、まるで和菓子のような感じもしますが、最近は...
-

-
ハクチョウゲの育て方
ハクチョウゲの特徴は、何と言っても小さくて可愛らしい花を咲かせる事ではないでしょうか。生長が早い植物ですが、刈り込みもき...
-

-
カリフォルニア・デージーの育て方
科名はキク科であり、学名はライアであり、別名にライア・エレガンスという名を持つのがカリフォルニア・デージーであり、その名...
-

-
ガザニアの育て方
ガザニアはキク科ガザニア属で勲章菊という別名を持っています。ガザニアという名前はギリシャ人が語源とされており、ラテン語の...
-

-
マルメロの育て方
マルメロは、原産地を乾燥地帯が広がっていて遊牧などが盛んな大陸としている樹木ですが、我が国でも生息地としている都道府県も...
-

-
ヤシ類の育て方
ヤシ類の特徴としては、まずはヤシ目ヤシ科の植物であることです。広く知られているものとしてはココヤシ、アレカヤシ、テーブル...
-

-
トウワタの育て方
トウワタ(唐綿)とは海外から来た開花後にタンポポのような綿を作るため、この名前が付けられました。ただし、唐といっても中国...
-

-
シザンサスの育て方
シザンサスはチリが原産の植物です。もとの生息地では一年草、あるいは二年草の草本として生育します。日本にもたらされてからは...




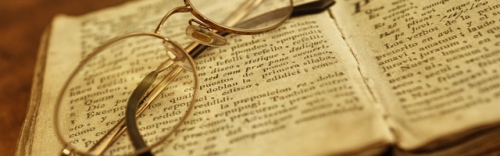





江戸時代より日本で育種され、改良も重ねられた植物を古典園芸植物と称しますが、マンリョウもこのような古典園芸植物です。