バオバブ(Adansonia)の育て方

バオバブの育て方
熱帯雨林のサバンナ気候に生息するバオバブは、日本の自然気候とは全く異なった環境に生育しています。そのため、日本本土で育てる場合冬は10〜15度以下にならないように室内で保護することが原則です。原産地では日陰のない強烈な日光が当たる地域に生息しており直射日光を好みます。
その一方湿度に弱いので風通しの良い場所で生育します。新葉展開後の春先から秋にかけてを雨季期間(成長期)と考え、土表面が乾燥したらたっぷりと水を与えるようにします。基本的に成長期は室内では徒長しやすく害虫がつきやすいと言う点から、風通しの良い屋外で育てると強くて丈夫な植物として成長します。
冬季は、気温が徐々に下がり始めるとともに、水やりを控えめにするようにします。すると、冬季に向かって葉がだんだんと黄色く変化し落葉しはじめます。日本本土で最も気温が下がる時期(12月〜2月)には耐寒性を高め根腐れを防ぐために完全に断水するか月1回程度水やりをするようにします。
南西諸島以南の亜熱帯性気候に属する地域は断水をする必要はありません。冬季に向けて水やりを控える事によって、幹が水分を蓄える為に肥大してきます。(幼木の頃は地下塊根に蓄えられます。)また冬季に全て落葉してしまった状態に土から出して日が当たらない室内の暖かい場所に保管しておき、
春先に土に上戻す方法もあります。春先になり気温が上昇してきても水やりを一気に再開すると根腐れの原因となります。自然に新葉が展開してくるまで待ちましょう。バオバブは成長するのに何年もかかる植物なので気長に栽培を楽しみましょう。
バオバブの種付け
バオバブの果実は大きく、種子も1cm前後と大きく硬い殻で覆われています。そのため発芽を促進させる必要があります。主に行われるのは、熱湯につける方法と種子の殻の一部に傷を付ける方法です。最初にバオバブの種は購入時に乾燥した果肉に覆われている場合があるので、少し水に漬け柔らかくなったところで水洗いをし種だけにします。
まず熱湯に浸ける方法です。70~80度の熱湯を種が入っている耐熱容器にたっぷり入れます。そのまま48時間放置しておくだけの簡単な方法です。熱湯は1~2時間程度で室温になりますが温め直す必要はありません。種子の殻の一部を傷つける方法は、鉄ヤスリやハンドナイフなどで種子の背側(ヘソ部分と反対側)を削ります。
そして、白い部分がうっすらと見えてきた時点で止めます。削り過ぎると、細菌やカビが侵入し種子を腐らせてしまう原因となるので注意します。そのまま8~24時間ほど水に浸けておきます。その後すぐに植え付けてしまうと種子が腐ってしまう事があるので、清潔な濡れティッシュかペーパータオルの上で発根を確認してから植え付けるようにします。
その際完全に乾燥してしまわないように十分注意しましょう。熱湯に浸けて発芽促進をした種は8mm~15mmほどの浅い位置に植え土をかぶせます。種子の一部を傷つけた種は、細菌などの腐敗を防ぐ為に種子の上部は土から出して植え付けるようにします。
発芽用にph調整が行われているビートモスなどを使用します。酸性の強い用土(鹿沼土、日向土、ph非調整ピートモス)は避けましょう。大体10~20日前後で発芽しますがなかなか発芽しない場合は、種を取り出しニッパーなどで傷をつけない様気をつけて皮を剥いてあげると発芽する場合があります。
バオバブの手入れ
バオバブの栽培のポイントは一年草のようにすぐに芽が出て開花に至るのではなく、気長に生育することです。自然環境では高さ40mにも成長する樹木なので、ある程度育ったらどのぐらいの大きさにどのような形で栽培したいかを検討します。そして剪定を行います。
剪定時期は成長期の9月頃までに行います。バオバブは種類によって萌芽力が異なります。アダンソニア・ディギタータは最も市販されているバオバブの種子で、萌芽力も強くどこで剪定しても萌芽します。そのため、剪定による失敗も少なく盆栽に適しています。
アダンソニア・ギボーサは萌芽力が弱く盆栽には適していません。アダンソニア・マダガスカリエンシスは葉も大きく枝ぶりも大柄なので盆栽風の作りより自然な作りに適しています。剪定以外のお手入れに肥料やりがあります。
バオバブには市販の油粕や骨粉の玉肥を月3回を上限として与えるようにします。また液体肥料の薄めたものを成長期に与えます。休眠期には与えないようにします。その他風通しが悪かったり、枝葉が混みすぎていると害虫が発生することがあります。
害虫は主に、アブラムシやガの幼虫、ナメクジによる被害が多く見られます。害虫を発見したら他の病気を発生させ植物を弱らせるのを防ぐ為に、すぐに薬を散布するようにします。真夏の成長期より、春の萌芽時期や秋の成長期が止まった頃に害虫が発生しやすいので注意しましょう。
バオバブの歴史
その名前は16世紀に北アフリカを旅したイタリア人植物者が「バ・オバブ」と記したのが始まりと言われていますが、元はアラビア語の「ブー・フブーフ」(種がたくさんあるものと言う意味)が由来とされている説もあります。
上と下を逆さまにしたような形が特徴で、年輪がないため樹齢を測定する方法は限られていますがアフリカにある大木は樹齢数1000年を超えると言われています。またアフリカのセネガルでは精霊が宿る木として崇められており、古い民話にも頻繁に登場します。
日本では近年観葉植物として栽培され、種類によっては盆栽として育てる事も可能です。サン・テグジュペリの「星の王子様」という物語のなかでは、星を破壊する巨木として登場し日本人にも良く知られています。
現在世界規模の異常気象で乾季が長く続くアフリカでは象が水分供給のためバオバブの樹木を食べたり、人間による宅地開発のための伐採からその数は減少しつつあります。
バオバブの特徴
バオバブはパンヤ科の植物でその種類は8種類あります。原産地は、マダガスカル、アフリカ、オーストラリアのサバンナ地域を生息地としています。バオバブの自生地の気候は、日本のように寒暖の差があまりなく年間最低気温でも10~15度を保っています。
そして、雨期と乾季がはっきりと分かれていて雨が全く降らない時期があります。バオバブの大木は10トンの水を蓄えることが出来ると言われ、乾季になると落葉し休眠する熱帯樹木です。育て方のコツの一つとして、休眠期と成長期のメリハリをはっきりとした生育が挙げられます。
ヘチマのように大きく垂れ下がった大きな果実は、ビタミンCやカルシウムなどの栄養分を多く含んでおり食用や調味料として使用されています。また種からは油分が採集でき柔らかい若葉は食用として使用可能です。その他、地元の人々に樹皮は煎じて解熱剤として用いられたり、
裂いて細かく編み頑丈なロープとして使用されています。アフリカのセネガルでは国のシンボルとして制定されており、バオバブの実はパンのような形から「サルのパン」と呼ばれています。また神様が植えた時に上と下を逆さまにして植林したとも言われています。
観葉植物の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:シェフレラ・アルボリコラの育て方
タイトル:ツピダンサスの育て方
-

-
カエデ類の育て方
カエデ類はカエデ科カエデ属の木の総称で、さまざまな品種が存在しています。日本原産の品種も20種類以上がありますし、生息地...
-

-
メラレウカの育て方
この植物は、フトモモ目、フトモモ科、メラルーカ属とされています。園芸として楽しまれるときは庭木、花木以外にもハーブとして...
-

-
ミヤマクロユリの育て方
このミヤマクロユリは多年草になり、直立した茎の上部に細長い楕円形の葉を2~3段に輪生させており、茎の先に2~3輪の花を下...
-

-
ワトソニアの育て方
ワトソニアは草丈が1m程になる植物です。庭植え、鉢植えにも適しています。花の色は、白やピンク、赤やサーモンピンクなどの種...
-

-
オカワカメの育て方
オカワカメと言うのは料理のレシピなどでもお馴染みの食材です。ワカメ名の付くことからも見た目がワカメに似ていたり、栽培する...
-

-
アレカヤシ(Dypsis lutescens)の育て方
アレカヤシという観葉植物をご存知でしょうか。園芸店などでもよく見かける人気のある植物です。一体どのような植物なのでしょう...
-

-
ディネマ・ポリブルボンの育て方
ディネマ・ポリブルボンは、中南アメリカ原産の小型のランです。主な生息地は、メキシコやグアテマラ、キューバやジャマイカで、...
-

-
カンガルーポー(アニゴザントス)の育て方
ハエモドルム科の植物で、生息地はオーストラリア南西部です。別名「アニゴザントス」とも呼び、咲いた花の形状がオーストラリア...
-

-
オカノリの育て方
オカノリの原産国は諸説ですが、中国が有力とみなされています。ある説ではヨーロッパが原産と考えられ、現在でもフランス料理で...
-

-
シシウドの育て方
シシウドの原産地は日本になります。別名をウドタラシと言うのですが、猪独活ともいった名前が付いているのが特徴です。夏の暑い...




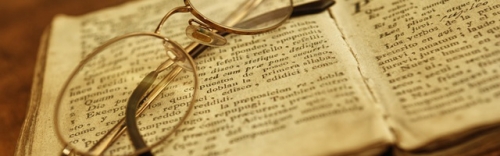





バオバブは古くから人類の歴史と深く関わり続けている樹木です。人類が2足歩行をする400万年前以前からフルーツや葉を食料として提供し、大きく成長した大木は強烈に照りつける日光からの避難場所となり、その幹は現在でも住居として利用され続けています。