ストケシアの育て方

育てる環境について
育て方としてはどのような環境に置くようにするのが良さそうかですが、基本的には日向になります。生息地は温暖で乾燥しているところです。1年を通して温かいところになります。太陽を浴びてどんどん咲きそうですが、あまり直射日光に当てすぎるのは良くないともされています。そのことから半日陰ぐらいが丁度良いようにも言われています。
日当たりについては花の付き方に影響してきますから、あまり暗いところは勧められないでしょう。少なくとも午前中いっぱいは日当たりになるようなところに置いておくようにします。寒さに対する強さですが、暖かいところが原産の割には比較的耐寒性があります。関東よりも西であれば戸外でも十分越冬することが出来るとされています。
北海道や東北、日本海側などの寒い地域においても工夫をすることで十分冬を越すことができます。マルチングをすれば土を凍ることを防げます。土が凍ってしまうと少し厳しくなりますが、そうでなければ問題は少ないと言えるでしょう。現地においては特に何かをしないと育てられないわけではありません。
雑草のように生えています。日本のタンポポに近い種類とされているので、日本のタンポポのように咲いているのでしょう。もちろん日本において同じように咲かせることが出来るわけではありませんが、比較的近いようには育てることが出来ると言えます。一旦植えてしまえば後はそれ程気にせずに育てていくことができそうです。
種付けや水やり、肥料について
栽培をするにあたっての用土としては水はけを重視するようにします。花が美しいのでできればきれいに咲かせるようにしたいです。その時には栄養分が必要になってくるので、腐植質の富んだ土を用意するようにします。鉢植えのときに良い配合としては、赤玉土を7割ぐらい、腐葉土を3割ぐらい混ぜた土などにします。
腐葉土の割合を少し増やしたりするのもいいかもしれません。水やりについては多湿に気をつけるように育てる必要があります。生息地は乾燥している地域です。そのために乾燥にはそれなりに強いです。その一方で多湿、過湿に弱いタイプになっています。水のやり過ぎで蒸れてしまうことがあります。
植木鉢においては土が乾いてきたときにしっかりと与えるようなタイミングで水やりを行うようにします。庭植えの時の水やりとしては、植え付け時においてはしばらくはしっかりと水を与えるようにします。目安としては2週間ほどです。それ以降いついては特に水やりの必要がないくらいです。
庭においては雨水などがある程度含まれるので、余程のことがない限り土が乾燥することがありません。日照りが続いたときに水を与えるようにすれば問題ありません。半日陰のような環境ならほとんど心配ないかもしれません。肥料についてはほどほどにを心がける植物とされています。あまり肥料が多いと生育が悪くなることがあります。多肥は好まないタイプですから、別途の肥料は与えないぐらいでもいいでしょう。
増やし方や害虫について
増やし方としては多年草ですからいくつかの方法を取ることができます。まずは株分けがあります。植え付けの時期として春と秋があり、植え替えも同じ時期に行うとされています。植木鉢においては2年に1回ぐらいは行うほうが良いとされています。根詰まりをすることがあるからです。根詰まりをする状態になるくらいだとかなり株も大きくなっています。
そのときに状況を見計らって株分けをするようにします。株を掘り起こした後に株の土をきれいに落とします。3つから5つの芽があるのを確認して、それが1株になるように分けます。株分けを行ったら休ませるわけではなく乾かさないようにすぐに植えつけるようにします。
花としては乾燥にそれなりに強いですが、根の部分はあまり乾燥させるのは良くありません。株分け以外の方法としては根伏せがあります。植え替えをする時などに太い根を探します。それを数センチの長さに切ります。5センチから10センチぐらいでいいでしょう。それを浅めのプランターの上に寝かせます。そして土を2センチほどかぶせておきます。
乾かさないように管理をしておくとそのうち芽が出てくるようになるのでその状態になると植え替えをします。種まきでも増やすことができ、春と秋に行います。病気であったり害虫においてはあまり心配する必要がありません。放任主義で育てるのが良いとされています。水のあげ過ぎ、肥料のあげ過ぎなど過保護にすると傷んでしまいます。
ストケシアの歴史
日本においてはキクを育てたり楽しむことが多いようです。国の花としても知られていていろいろなところで使われることがあります。一般的な花といえば花びらが数枚ついているタイプになりますが、キクは小さい花びらが沢山ついています。それがより花を豪快に見せたり、時には可愛らしく見せたりすることがあります。
キクの仲間の一つとして知られる花にストケシアと呼ばれる花があります。この花の別名としてはルリギクと付けられています。その他にはエドムラサキと呼ばれることもあります。原産地としては北アメリカの南西部になります。南カリフォルニア、フロリダ、ルイジアナなどです。比較的温暖で、乾燥している地域といえるでしょう。
歴史においては、日本への渡来は意外に遅いほうかもしれません。アメリカの花については早いものなら明治時代にどんどん入ってきています。この花については大正時代の初めに渡来してきたとされています。当初はキクのようだけども色があまり受け入れられなかったようですが、
昭和の初期になってくると逆に日本固有のキクにはない色として少しずつ人気が出てきたようです。花の名前の由来としては、イギリスの植物学者の名前が取られているとされています。ストークスさんと呼ばれる人が名前についています。種の小名としてはラエヴィスと付けられていますが、こちらについては平滑なとの意味合いになります。花の咲き方からつけられているのかもしれません。
ストケシアの特徴
この花は被子植物門、双子葉植物綱、キク亜目、キク目、キク科になります。タンポポ亜科になるのでタンポポに近い植物であることがわかります。多年草に属していて、草の高さとしては30センチ位から60センチ位になるとされています。花の咲く季節としては夏になります。6月くらいから咲き始めて、10月ぐらいまで楽しむことが出来る花とされています。
生息地は温暖な地域になっていて、冬にも花を咲かせることがあるようです。ですから日本では終わっている時期においてもきれいな花を楽しませてくれるとされています。ルリギクと言われるとおり青色、紫色が非常にきれいな花ですが、実際のところはもう少し色の種類があります。白や黄色、ピンクなどもあります。
栽培品種としてどんどん色の方も増えているようです。葉っぱに関しては広披針形をしています。互生に生えるタイプの葉っぱになります。花に関してはキク科の花らしく花びらが沢山ついています。ただし花びらの形が少し変わっていると言えるかもしれません。最も外側においては菊の花にしては少し大きめの花びらがついています。
その花びらの先端部分が少し切れ込みがあり、それによって一般的なキクの花びらのように見えることがあります。この花びら自体は10枚ぐらいがついています。中心には細かい糸のようにでていて、一般的には花の色と同じなので花の部分と同じように見えます。中心部分ややや白っぽく見えることもあります。
-

-
リューココリネの育て方
分類としてはヒガンバナ科になります。ユリ科で分類されることもあります。ユリのようにしっとりとしているようにも見えます。園...
-

-
アジアンタムの育て方
アジアンタムはワラビ科の観葉植物ですが、そのほかにも造花やプリザーブドフラワーとしても使用され、フラワーアレンジメントを...
-

-
スカビオサの育て方
スカビオサは別名西洋マツムシソウとも呼ばれるもので、同じ系統のマツムシソウは日本を生息地としていて古くから日本人に親しま...
-

-
ヘスペランサの育て方
ヘスペランサは白い花を持つ美しい植物でり、日本だけに留まらず多くの愛好家がいます。花の歴史も深く、大航海時代にまで遡る事...
-

-
ヒマラヤユキノシタの育て方
ヒマラヤユキノシタとは原産がヒマラヤになります。おもにヒマラヤ山脈付近が生息地のため、周辺のパキスタンや中国やチベットな...
-

-
銀葉アカシアの育て方
まず歴史的にもミモザという植物は、本来は銀葉アカシアなどの植物とは違う植物です。もともとミモザとはオジギソウの植物のこと...
-

-
マサキの育て方
マサキは日本、中国を原産とする常緑の広葉樹で、ニシキギ科ニシキギ属の常緑低木です。学名はEuonymusjaponicu...
-

-
パキフィツムの育て方
パキフィツムは、メキシコ原産の多肉植物です。ベンケイソウ科パキフィツム属の植物は、多肉植物の中でも、肉厚な種類として有名...
-

-
ボタンの育て方
牡丹の原産は中国の西北部だと考えられています。この地域では、もともとは観賞用ではなくて、薬として用いられていたそうです。...
-

-
ノースポールとハナナの育て方
クリサンセマムは可愛いキク属の花です。クリオスに金という意味が、アンセマムには花という意味があります。クリサンセマムと呼...




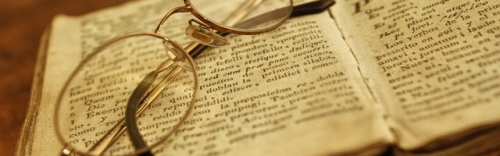





この花は被子植物門、双子葉植物綱、キク亜目、キク目、キク科になります。タンポポ亜科になるのでタンポポに近い植物であることがわかります。多年草に属していて、草の高さとしては30センチ位から60センチ位になるとされています。花の咲く季節としては夏になります。