レーマンニアの育て方

育てる環境について
育て方として、観賞用のエラータの場合は前の段落で書いたように温暖なところでも丈夫に生育しますが、温度が高く、湿り気が大いにあるところを苦手としているので育てる場合には風通しが良好で気温が低いところで育てるのがベターだとされています。暑さには弱いと言われている反面、寒さに強い特質を持っていますが、小さい苗の場合は寒いところだと傷んでしまう場合があるので、注意深く栽培するのが大切です。
使用する土は排水の機能に秀でていて、有機質に富んでいる土がベターだとされています。種子を植える場合は少し気を付けておかなければならない事項があり、種子の大きさが小さいので、植える際には土に埋めないでおくか、ほんの少し埋めるだけが適切だと言われています。
漢方薬の材料として使われている和名がアカヤジオウグルティノサの場合はエラータより栽培が難しいとされていて、育てていると知らない間に枯れてしまっているというケースも実在しているそうです。また和名がアカヤジオウのグルティノサは収穫量が少ないとされているので、国内総生産第2位の国では品種改良が行なわれるようになりました。
また、某製薬関連のカンパニーでアカヤジオウとカイケイジオウと呼ばれているプラントを交雑させたプラントを漢方薬として利用したケースも実在していますが、今のトレンドとしては、学名の一部にグルティノサが付けられているカイケイジオウがメインとして使われているそうです。
種付けや水やり、肥料について
レーマンニアエラータの育て方を見ていきますが、種子をまくシーズンは秋または春であり、そういうシーズンに済ませておくのが賢明です。また発芽するための温度も決まっていて摂氏15度から摂氏20度弱が適しているので、秋にまく場合には気温が低下しがちになるので気を付けておくのが大切です。
まき方については、前述に書いたように小さな種であるので土に埋めないようにしてまくか、埋めるとしてもミリ単位で埋めて種子をまくのがベターです。違う場所で植えかえるのであれば苗が手でつまめるほどの大きさにしてから行なうのが最も適しているタイミングです。水やりに関しては鉢植えでの栽培は、少し乾燥した様子にしておいて表面部分が乾いてきたら与えるようにしておきます。
地植えで栽培している場合には乾ききったら水を与えるようにするのが適しているとされています。肥料は過度に与えなくとも構いませんが、植え付けた後、または芽が生長するシーズンに与えるようにし、生長が盛んに行なわれている場合には10日に1度の頻度で肥料を与えるようにします。
日当たり、または少し日陰になっている場所を好むので、そういったところで育てるのがベターですが暑さ、湿気があるところを嫌うので暑いシーズンになれば少し日陰になっていて涼しいところに置くのが適しています。冬の管理ですが、寒さに強い特質を持っているので、暖かい地域で栽培している場合は外で越冬させるのも可能です。
増やし方や害虫について
繁殖の仕方としては種子をまいて育てる以外にも株分けという手段も実在しています。害虫に関してですが、基本的に害虫による被害は小さいとされていますが、気を付けておきたいのはナメクジなどされています。ナメクジはレーマンニアエラータだけではなく、そういった品種のプラント以外の園芸用のプラント、野菜に害を及ぼすとされていて、
殻はないですがカタツムリなどの巻貝の仲間に分類されています。我が国で見られるナメクジは我が国を原産としているナメクジだけではなく、外国から渡ってきた外来種のナメクジも棲息しています。ナメクジは栽培しているプラントを食い荒らしますが、駆除をする際には、疾患のもととなる菌を持っているので素手で触らないようにするのがベターです。
駆除をする手段はいくつか実在していて、例に出して言うならば、缶ビールの残りを置いておくという手段、塩または砂糖などを振りかけるという手段、駆除用の薬剤をかけるという手段などが列挙されています。缶ビールの残りを置くのが適切であるという訳は、ビールのにおいがナメクジを誘引して、缶に落ちて死亡するからだとされています。
ビールのにおいに強いナメクジも実在していますが、そういう場合に備えてビールに塩などを加えるのが有効だとされています。なお、ソーセージの国ではビールによるナメクジの退治法がメジャーだとされています。またガスバーナーの火を使って退治するという手段も実在しています。
レーマンニアの歴史
レーマンニアというプラントは国内総生産第2位の国を原産とするプラントであり、またそういうところに生息地としています。こういう名前を聞くと地黄という漢方薬をイメージする者もいるそうですが、漢方薬として使われているプラントはレーマンニアグルティノサという学名を持つアカヤジオウという品種のプラントであり、
観賞用として栽培されている品種はレーマンニアエラータという品種のプラントだとされています。エラータの方はどうやら薬として使用するのが不可能だそうです。なお、グルティノサは前に述べたように昔から漢方薬として使用されてきたプラントであり、使われている漢方薬としては八味地黄丸、六味地黄丸、炙甘草湯などが列挙されています。
紀元1世紀から3世紀にわたって成立した国内総生産第2位の国の文献にもそういうプラントを使った漢方薬に関する事項が記載されています。なお、14世紀後半から17世紀ぐらいまでの国内総生産第2位の国で出版された文献ではニラ、ネギといった野菜と一緒に摂取するのはタブーだと言われています。八味地黄丸の材料にして、服用した場合の効能は、
尿が頻繁に出てくるという症状、足腰が痛むという症状などを改善させると言われており、炙甘草湯の材料にして、服用した場合は動悸、息切れなどの症状に効果があるとされています。グルティノサのほうも主に血液の流れを改善させたり、鼻血などの出血を抑えたりする効果を持っています。
レーマンニアの特徴
観賞用として栽培されているエラータは葉っぱの形が楕円のような形をしていて、5月ぐらいか暑いシーズンになると、花茎が長い花を咲かせると言われています。こういう花の形はまるでキツネノテブクロとも呼ばれているジキタリスというプラントに酷似しているとされています。高さは1メートル程度であり、花が咲くシーズンには次々と咲いてくるとされています。
なお、寒さにやや強い特質を持っていますが、暑さに弱いところもあり、また湿度が高いところも嫌うと言われていますが、温暖なところでは育つとされています。アカヤジオウの和名を持っているグルティノサのほうは草の高さが20センチか、30センチ程度であり、エラータより低いとされていて、花の色も薄いピンク色をしています。
なお、エラータは濃いピンク色をしています。また茎などには毛が生えていて、地下茎と呼ばれている部分は太く、赤っぽい褐色をしていて横へと這っていくという特質を持っています。実にも少し変わった特質を持っていて、熟していくと下の部分が破れていって、実に実在している種子がばらまかれるという特質です。
前に記述しているようにグルティノサは薬用をメインとして栽培されていますが、和名としての名前の由来は根っこの色、あるいは国内総生産第2位の国の大陸で使われていた土が黄色を帯びていたという由来から名づけられたとされていますが、仲間のプラントであるシロヤジオウと区別する為に名づけられたとも言われています。なお、シロヤジオウも学名の一部にグルティノサが付けられています。
-

-
カキの育て方
カキは日本の文化にも深く根ざした樹木で、たとえば正月になると干し柿を鏡餅に飾ること空も分かると思いますし、若にもたびたび...
-

-
ゲイソリザの育て方
ゲイソリザはアヤメ科の植物で原産地は南アフリカとなっています。生息地を考えると乾燥している熱帯の地域なので育て方が難しい...
-

-
ダイアンサスの育て方
ダイアンサスは、世界中に生息地が広がる常緑性植物です。品種によって、ヨーロッパ・アジア・北アメリカ・南アフリカなどが原産...
-

-
ワイヤープランツの育て方
ワイヤープランツは観葉植物にもなって家の中でも外でも万能の植物です。単体でも可愛くて吊るして飾っておくとどんどん垂れてき...
-

-
温州みかんの育て方
みかんは、もともとインドやタイ、ミャンマーなどが原産だと考えられています。生息地は、現在では世界各国に広がっていますが、...
-

-
ペンタスの育て方
この花については、アカネ科、ペンタス属となっています。和名の方をとってクササンタンカ属とすることもあります。熱帯植物に該...
-

-
ヒベルティアの育て方
ディレニア科ヒベルティア属は、害虫被害に遭いにくい植物です。原産地をオーストラリアとするヒベルティアという花は、種類にも...
-

-
デルフィニウムの育て方
デルフィニウムはキンポウゲ科の花で、5月から6月頃に様々な色の繊細で美しい花を咲かせます。背が高い茎に小さな花をたくさん...
-

-
サクランボの育て方
栽培の歴史はヨーロッパでは紀元前から栽培されており、中国に記述が残っていて3000年前には栽培されていました。日本には江...
-

-
カスミソウの育て方
カスミソウの原産地は地中海沿岸から中央アジア、シベリアなどで、生息地は夏季冷涼なところです。カスミソウの属名ギプソフィラ...




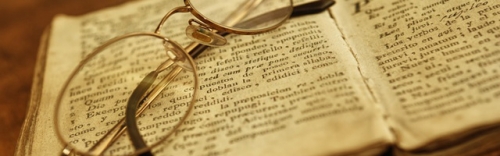





観賞用として栽培されているエラータは葉っぱの形が楕円のような形をしていて、5月ぐらいか暑いシーズンになると、花茎が長い花を咲かせると言われています。こういう花の形はまるでキツネノテブクロとも呼ばれているジキタリスというプラントに酷似しているとされています。高さは1メートル程度であり、花が咲くシーズンには次々と咲いてくるとされています。