マネッティアの育て方

育てる環境について
マネッティアの育て方になりますが、これは亜熱帯の植物ということでわかるように、耐寒性のない植物になります。温度では13℃を切ると成長が止まってくるので、7℃以下になると落葉して枯れてしまいます。そういった成長を考えると、やはり寒いところでは最低でも10度は切らないように気をつけるようにしたほうがいいです。
もし冬越を考える場合には、最低7~8℃の気温が必要になるということを頭に入れておくといいです。室内で育てるには、基本的にはどれも生育適温の18~26℃ならよく育ちます。この温度設定というのは、人間が快いと感じる温度とほぼ同じになっているからです。特に温かい地方で栽培されているような植物や花では、人が暮らす室内と同じように
、温度に関する条件は一緒にしていた方が良いです。冬の室内は暖房をしていくために、暖房費がかかりますが、夜に暖房を切ると室温はかなり下がっても大丈夫なようにビニールハウスを作って、暖房を逃げないようにすることができます。室内でマネッティアを育てるには、その他にも明け方の最低気温を確かめたほうがいいです。
植物によって耐寒力が異なりますが、枯れないように配慮することが必要になります。冬は室内の日の当たる窓辺で育てるのも方法のひとつです。冷え込むようならば、対策は必要ですが日当たりの良い場所で育てることで元気になります。季節では春から秋の生育期は、できるだけよく日の当たる場所で育てたほうがいいということです。
種付けや水やり、肥料について
マネッティアの種付けや肥料については、この植物は肥料を好みます。肥料には三大要素と呼ばれる大切な成分がります。観葉植物にどの肥料を与えればよいか知っておくと、育成させるのも何がいいのか分かるようになります。これだけは覚えておいてください、春から秋の生育期は2週間に1回程度、液体肥料を与えることです。
そうすることによって、花のエネルギーが肥料と共にいきわたるので、生物がイキイキとしてきます。肥料の成分である窒素によって、植物に重要なタンパク質を与えることでき、根や茎を育てることできるので植物の形を作ってくれます。そして花の実を育てるのは、リン酸の成分が必要になり、肥料によって与えることができます。
マネッティアの栄養にはこういった肥料から与えていくことによって、育ち方が変わってきます。しかし、いつまでも肥料を与えていた方がいいのかというと、秋から冬にかけては気温の低下とともに生育も鈍るので、肥料を与える必要はありません。そして植物を育てる上で最も重要なのは、水を与えることになります。
しかし、その植物の特性をよく知らなくては、ただ水をあげるだけでは成長を遅くさせることもあります。もし、自分の育てているマネッティアが水をあげていても、成長がおきない場合には、あげるタイミングや量を考えてみることです。植物の微妙な変化を見逃さないようにして、特性に応じた適切な処置をとれるかどうかが上手に成長させるコツになります。
増やし方や害虫について
このように成長が大事になりますし、もしマネッティアを増やしていきたいならば、さし木で増やすことができます。まずマネッティアのつるを15cmほどの長さに切ります。そして先端についている、細くてやわらかい部分は切ってしまいますが、あまり切りすぎないようにした方が良いです。
その後に、湿らせた土や川砂を入れた鉢に入れるのですが、この時にグラつかないようにすることがコツになります。さし穂を下から1/3くらいの位置までしっかりと土に挿していき、その後に陽の当らないところでなるべく乾かさないように管理するといいです。葉が多いと呼吸などが活発になっている為に、葉がしおれやすいので、
葉が多い時には数を減らしていくことも大事な作業になります。そんなにマネッティアの葉は大きなものはありませんが、あまり大きな葉のものは、葉をくるくると丸めて紐などで括ると上手に増やすことできます。このようなマネッティアの作業の時期は、温かくなる4月~9月頃がベストだといえます。害虫についても注意が必要です。
天敵なのは「オンシツコナジラミ」が育成過程で発生することがあります。体調は数ミリですが白い羽の生えた小さな虫で、マネッティアの葉裏についていることがあります。風に揺られて飛んでいくことがありますが、すぐに戻ってきて葉を悪くするので、油断をしない方が良いです。栄養を奪い取って弱らせるので、見つけたら薬剤を散布して駆除することです。
マネッティアの歴史
花の美しさがわかるようになるには、感性が重要になります。反対にいえば感性を養うには、美しいものを感じることができるようになると、人間の心が育てられるということです。子供のうちから、花や植物に触れるような生活環境にすることによって、暮らしを豊かにすることが望ましいといえます。花の中でも熱帯アメリカに広く分布しているのが、
マネッティアになります。日当たりの良いところで育てることが重要な花になりますが、これは生息地に関係があります。原産国はパラグアイやウルグアイになりますが、南米でも代表的な花になります。日本とは違い南米大陸の中央に位置するパラグアイは、中央を流れるパラグアイ川があります。そして東部と西部に分けられているので、
植物なども地方によって違いがあります。東部パラグアイは森林丘陵地帯になっており、西部パラグアイは大草原となっているので、雄大な大地と自然が広がっています。気候は亜熱帯性になっており、平均気温は17~24.5℃もあるので常に暖かい気候になっています。このような環境の中で育っているマネッティアは、
アカネ科の、別名ではアラゲカエンソウとなっています。名前の由来というのは、18世紀のイタリア医師マネッティの名前にちなんでいるといわれています。生息地が温かいところになるので、オレンジ色と黄色の色合いのある花は、とても温かさを感じてマネッティアの良さを引き立たせているというのがわかります。
マネッティアの特徴
マネッティアの特長としては、花は濃いオレンジ色になっており強いオレンジ色というよりも、優しさにあふれる色になっているので、見ている人を和ませます。そして花の先端が黄色という色合いも、黄色の持っているパワーを感じることができるので、心の癒しの他にも生きる勇気を与えてくれます。
こういった綺麗な色合いの中でも、非常に目立つツートンカラーになっているので、パラグアイやウルグアイなどでは人気のある花になっています。そして花の形は筒状になっていて、一瞬小さなつぼみかと感じるくらいの佇まいをしています。これは控えめな感じですが色がオレンジと黄色という点を考えると、それくらい控えめでも目立つようです。
そして長さ2~3cmと小さいので余計にたくさんの花を見ることができるということでは、素敵な花の雰囲気がわかります。花付きも、まばらですが存在感や印象は強く残るのも南米のラテンなイメージと明るい印象がそうさせるといえます。そしてマネッティアの花は、やや肉厚で表面に粗く毛が生えているので、先端が4つに裂けて開いているのが特徴です。そ
の花の姿に「アラゲカエンソウ」という日本では和名が付けられています。鉢植えは支柱につるを絡ませて作るので、クリスマスシーズンに活躍するイルミネーションで飾られたクリスマスツリーを彷彿させてくれるのも、嬉しいところです。通常であれば自然の環境下で育てていると、春から秋にかけて花を付けますが、温室では周年花を咲かせることができます。
-

-
ハクサイの育て方
ハクサイは漬物や鍋の中に入れる野菜、中華料理の食材や野菜炒めなどでもお馴染みの野菜です。色々な料理に利用出来る万能野菜と...
-

-
ドゥランタ・エレクタ(Duranta erecta)の育て方
ドゥランタ・エレクタは南アメリカ原産の植物ですが、日本でも容易に栽培できるのが特徴です。植え付けをする際には肥沃で水はけ...
-

-
センニンソウの育て方
センニンソウの特徴は、扁桃腺治療などに用いられる薬草としての役割も多いのですが、仙人の由来ともなった、仙人のヒゲのような...
-

-
カカオの育て方
そんなカカオの特徴はどのようなものなのでしょうか。前途のように、チョコレートの原料として使われるので樹そのものよりも、果...
-

-
シバザクラ(芝桜)の育て方
シバザクラは北米を原産とするハナシノブ科の多年草です。春先にサクラによく似た可愛らしい花を咲かせますが、サクラのような大...
-

-
ドクゼリの育て方
ガーデニングなどの植物を育てるということは、本来自然にある自生の植物を自分の所有する庭に囲い込み、好みに合わせた箱庭を作...
-

-
トリカブトの育て方
トリカブトは日本では”鳥兜”または”鳥冠”の由来名を持っています。この植物の花の形が舞楽で被る帽子の鳥冠に似ている事から...
-

-
セツブンソウの育て方
節分の頃に花を咲かせるセツブンソウは、キンポウゲ科セツブンソウ属の多年草のことを言います。日本原産の植物で関東地方以西に...
-

-
ホースラディッシュの育て方
アブラナ科セイヨウワサビ属として近年食文化においても知名度を誇るのが、ホースラディッシュです。東ヨーロッパが原産地とされ...
-

-
センブリの育て方
センブリはリンドウ科センブリ属の二年草です。漢字で「千振」と書き、その学名は、Swertiajaponicaとなっていま...




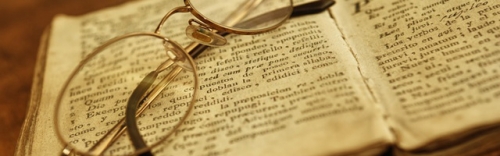





マネッティアの特長としては、花は濃いオレンジ色になっており強いオレンジ色というよりも、優しさにあふれる色になっているので、見ている人を和ませます。そして花の先端が黄色という色合いも、黄色の持っているパワーを感じることができるので、心の癒しの他にも生きる勇気を与えてくれます。