ヒマラヤ・ハニーサックルの育て方

育てる環境について
ヒマラヤ・ハニーサックルは、原産地であるヒマラヤ山脈のように寒冷な気候で、良く生育しますが、かなり広い適応力が備わっており、育て方が容易です。ヨーロッパの寒冷気候にも適しています。その一方で、強い日差しの条件下でも、よく生育します。ヒマラヤ山脈地方を始めとして、中国西部やチベットに生息地が多いですが、高山地方ならではの過酷な自然環境化にも耐えられる強さを備えています。
日本は、高温多湿な夏が心配されることが多いものの、健康に生育します。湿度が過剰になるような梅雨の季節でも、花を咲かせて、実をつけます。ただし、土壌は、やや排水性を強めておいたほうが良いでしょう。雨天が続いたときに、水溜りが発生しやすい土壌よりも、排水性が高くて水溜りができにくい場所に植えておいたほうが、実の付きが良くなる傾向にあります。
排水性を高めるためには、土に小石や砂を混ぜるのも良い方法です。鉢植えであれば、一般的に市販されている培養土や腐葉土と一緒に、鹿沼土や赤玉土も混ぜておくと良いでしょう。小石は園芸用に高温殺菌処理されているものが安心です。砂であれば、川砂を選びましょう。
庭木として栽培する場合は、近くに何を植えるのかにも注目すると良いでしょう。初夏に咲く花は、バラの開花とも季節が近いです。近くにバラを植えておくと、バラの開花後の追肥が、土壌を伝って周辺の植物にも浸透し、吸収されていきます。バラ向けに調整されている培養土や肥料が、ヒマラヤ・ハニーサックルの花と実にも合います。
種付けや水やり、肥料について
ヒマラヤ・ハニーサックルが花を咲かせて、実をつけたら、実を採取して種子として利用することも可能です。実を種子として利用する場合は、実のまま乾燥させておくのがコツです。採取したものを風通しの良い場所で乾燥させます。乾燥したら、紙袋などのように透湿性の備わっている物に入れておくと良いでしょう。
成長した低木としては病害虫に強いのですが、収穫した実は、過剰な湿度で傷んでしまうことがあります。実を収穫しておいた容器も、容器内の温度と外気温の差が大きくなりすぎてしまうと結露が発生する場合があります。透湿性の備わっている容器であれば、結露が発生しにくく、夏でも冬でも、健康な状態で種子を保存できます。
実のままで土に蒔いても発芽しますが、季節は春にしましょう。地中、およそ数センチメートルくらいに埋めておくのも良い方法です。地表面ではなく、やや地中に埋めておくことで、夏の高温と冬の冷気から守られます。生垣や庭木のように地植えにしていれば、自然の雨水だけで大丈夫です。意識的に水やりをする必要は、ありません。
鉢植えやプランターで栽培している場合は、土の表面が乾燥してきたなと感じてから、たっぷりと水やりしましょう。鉢底から水が流れるように水やりするのがポイントです。たっぷりと水やりしたのに、鉢底から水が出てきにくい場合は、
土の保湿性・保水性が高い証拠です。土に川砂や小石を混ぜて、排水性を高くしましょう。肥料は与えなくても良いのですが、花と実が多いときは追肥を与えておくと良いでしょう。栄養素の配合は、パラ用の肥料が合いますので、参考にしましょう。液体肥料でも、粒状の化成肥料でも合います。
増やし方や害虫について
ヒマラヤ・ハニーサックルは、挿し木で増やすことが可能です。実を収穫し、種子から発芽させても良いのですが、挿し木のほうが簡単です。水に挿して発根させるよりも、清潔な土に直接挿したほうが発根がスムーズです。ただし、発根するまでは、屋外よりも屋内のほうが管理しやすいです。耐寒性に優れており、
日本の高温多湿にも強さを発揮しますが、挿し木にして発根させるときだけは、比較的に涼しい場所を選びましょう。初夏であっても、日中の最高気温が30℃を超えてしまうような環境下の場合は、エアコンを使用したほうが安心です。屋内で、昼と夜の気温差が少なく、ほぼ一定に涼しい場所であれば、スムーズに発根します。
挿し木に使用する土は、鹿沼土もしくは赤玉土を選びます。培養土や腐葉土は混ぜません。発根させるときだけは、栄養分は与えなくて良いです。鹿沼土または赤玉土に、川砂を混ぜておいても良いでしょう。液体肥料も与えません。発根が確認できて、別の鉢やプランターに移し変えられるようになってから、培養土や腐葉土と混ぜ合わせます。
ヒマラヤ・ハニーサックルは病害虫に強いのが特徴です。ただし日本の高温多湿な夏や、梅雨の季節には、地植えにしてある環境によっては、カイガラムシが葉の裏面に付着していることがあります。
もともと他の植物に繁殖していたカイガラムシが、風などで運ばれて付着することがあるからです。枝と葉が混み合ってきたら、剪定して風通しを改善しましょう。風通しが良い環境に整えておくと、カイガラムシなどが付いても、繁殖しにくい環境にできるからです。
ヒマラヤ・ハニーサックルの歴史
ヒマラヤ・ハニーサックルは、スイカズラ科スイカズラ属の植物です。落葉性の低木です。原産はヒマラヤ山脈で、中国西部からチベット地方に生息地が分布しています。スイカズラ科スイカズラ属の植物を代表するものにはスイカズラがありますが、スイカズラは常緑性であり、つる性植物です。
ヒマラヤ・ハニーサックルは落葉性で、低木ですので、古くから生垣として利用されることが多く、現在でも花を観賞できるタイプの生垣として利用されています。低木なので、背丈が高くなりすぎる心配がありませんし、つる性のように住居などの建物に巻きついて成育する心配がありません。
ちなみにハニーサックルとは、スイカズラ科スイカズラ属の植物を指す英語名です。スイカズラが、砂糖の代わりとしても使用できる甘い蜜を蓄えていることに由来します。カクテルの一種であるハニーサックル・カクテルの由来にもなっています。砂糖の原料となるサトウキビの原産は南太平洋ですが、インド原産という説もあります。
インドでは古代の叙事詩であるラーマーヤナに、砂糖の記述があります。そんなインドで古くから砂糖の代わりとして親しまれていたのが、ハニーサックルでした。新大陸発見の時代には、インドやチベットを訪問する欧米人が増え、
ヒマラヤ山脈地方に多くのヒマラヤ・ハニーサックルの生息地が発見されました。つる性のハニーサックルとは別の品種ですが、花が美しく観賞用に好まれ、欧米に持ち帰られ、観賞用として栽培されるようになりました。耐寒性に優れており、ヨーロッパの寒冷気候にも適していたこともあり、広く普及していきました。
ヒマラヤ・ハニーサックルの特徴
ヒマラヤ・ハニーサックルは観賞用に栽培されることが多く、生垣用にも利用されています。庭木としても栽培されることが多いです。基本的に、花が観賞用として好まれるのが特徴です。生垣として利用する場合も、観賞用の花の咲く生垣として好まれています。ヒマラヤ・ハニーサックルの花は、赤色や紫色をしていると指摘されることが多いのですが、正確には白い花が多いです。
これはヒマラヤ・ハニーサックルの花が、房状の形状をしているからです。房の全体は、赤色や紫色をしています。明るめのワインレッド色と言って良いでしょう。明るめのワインレッド色の房に、小さく白い花が咲きます。房の雰囲気は、南国果実のドラゴンフルーツにも似たところがあり、独特で個性的です。
明るめのワインレッド色も、ドラゴンフルーツの果皮の色とよく似ています。花が咲き終わる頃には実が付きます。実がつくことで、房の色が濃くなります。明るめのワインレッドから、暗めのワインレッドに変わり、落ち着いた雰囲気を放ちます。実は、白い花と同様に小さく、かわいらしい雰囲気です。高山植物のような可憐さが感じられます。
花が咲くのは、日本では初夏です。ちょうど梅雨の季節とも重なります。原産がヒマラヤ山脈地方というのもありますが、耐寒性に優れている植物であり、病害虫の被害に合いにくいのも特徴です。その一方で、日本のように高温多湿な環境でも生育します。湿度が高くなり、日照時間が少なくなることが多い梅雨でも、病気にならずに成長するのが嬉しいポイントです。
-

-
ネズミモチ(プリベット)の育て方
ネズミモチ(鼠黐・Ligustrum japonicum)は、モクセイ科イボタノキ属の樹木です。 生長すると樹高が4~7...
-

-
イヌマキの育て方
イヌマキはマキ科マキ属の常緑針葉高木で原産は関東から四国、九州、沖縄、台湾の比較的暖かいところの沿岸部を生息地にしていま...
-

-
ステビアの育て方
ステビアは、パラグアイをはじめとする南アメリカ原産のキク科ステビア属の多年草です。学名はSteviarebaudiana...
-

-
ムシトリスミレの仲間の育て方
この花については、キク亜綱、ゴマノハグサ目、タヌキモ科となっています。その他の名前としてはピンギキュラと言われていて、ピ...
-

-
ナツメ(実)の育て方
この植物は繁殖している地域も、日本中何処ででも見られますので、その点でも栽培では、初心者に適していますが、味の方も食べる...
-

-
モミジバアサガオの育て方
モミジバアサガオは和名をモミジヒルガオといい、日本で古くから親しまれてきたアサガオの仲間です。日本へ伝来したのは今から1...
-

-
リューココリネの育て方
分類としてはヒガンバナ科になります。ユリ科で分類されることもあります。ユリのようにしっとりとしているようにも見えます。園...
-

-
メランポジウムの育て方
メランポジウムはメキシコや中央アメリカを原産としていて、その用途は鉢植えや寄せ植え、切り花などに用いられています。なお、...
-

-
ミラクルフルーツの育て方
小さな赤い果実のミラクルフルーツは、あまり甘くなく、食した後、しばらくは、酸味のあるものを食べると、甘く感じ、とてもおい...
-

-
シラネアオイの育て方
シラネアオイの原産地は、日本で日本固有の壱属一種の多年草の植物ですが、分類上の位置が二転三転してきた植物でもあります。昔...




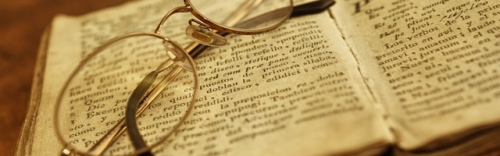





ヒマラヤ・ハニーサックルは、スイカズラ科スイカズラ属の植物です。落葉性の低木です。原産はヒマラヤ山脈で、中国西部からチベット地方に生息地が分布しています。スイカズラ科スイカズラ属の植物を代表するものにはスイカズラがありますが、スイカズラは常緑性であり、つる性植物です。