バーゼリアの育て方

育てる環境について
バーゼリアの育て方について書いていきます。ポイントとしては、この植物の耐暑性や耐寒性という性質を把握して、置き場所をきちんと考えることが重要です。まずは、その性質についてです。耐暑性が非常に強いので、戸外でも育てることができます。この植物は日光を非常に好みますので、日当たりの良いところに安置しておくと、よく育ちます。
また、日当たりの良いところでなくても十分に育ちます。半日陰でも全く問題ありません。半日陰というのは、1日でずっと日光が当たるのではなく時折あたるような環境のことを指します。ただし、真夏の時期になると、直射日光を毎日あたると頃においていると、さすがに耐暑性が強いとはいえ、ダメージを受けます。
葉が焼かれてしまって、枯れてしまうことがあります。あまりにも日光が強い日が続く場合は、室内で飼育した方が良いです。生息地が南アフリカということもあって、非常に暑さには強いです。また、耐寒性もかなり強い植物です。そのため、秋から冬にかけて室内で生育する必要は基本的にはありません。
風があたらない場所でなくても越冬はできます。ただし、東北地域や北海道では他の地域に比べて気温が低いです。そのため、冬を越すのが難しいので、室内で飼育することが基本です。耐寒性としては、気温が0度になっても耐えることができます。ただし、霜には注意が必要です。そのため、霜や気温が心配な人は室内に取り込んで生育するのが無難なやり方です。
種付けや水やり、肥料について
栽培方法としてポイントになるのが、水やり、肥料、種つけの3つです。肥料について書いていきますが、水はけの良い用土を使って適宜与えることが重要です。その際は固形肥料ではなく液体肥料を使うと良いです。最適な置き場所としては、水はけがよくて日当たりの良いところに置くのがベストなのですが、乾燥気味になるのには、注意が必要です。
春から秋にかけて戸外で育てることが一般的ですが、乾燥にはくれぐれも注意が必要なので、しっかりと状態を定期的に見ることが大切です。そのため、管理がなかなか難しい場合は、室内での生育がもっとも無難なやり方です。その際は、バーゼリアは陽光を非常に好みますが、室内の中でも特に日当たりの良いところを見つけて安置してください。
水やりについては、乾燥気味の状態がずっと続くとドライになってしまい、枯れてしまうことがよくあります。土の表面が乾いてきたと思ったら、水をたっぷりと与えることが肝要です。ただし、冬になったら水やりを控えます。これは、植物が休眠活動に入るからです。
休眠活動中に水をよく与えてしまうと、活性化してしまい、開花時期が早まってしまうこともあります。通常は春頃に開花しますが、1月や2月など冬の時期に花が咲いてしまうことがあります。その場合は、よわよわしい花がついてしまうので、注意が必要です。種付けについては、他の植物と同じで花と花をくっつけさせて受粉させるのが一般的です。
増やし方や害虫について
バーゼリアの害虫と増やし方について書いていきます。害虫は特にありませんので、特別な対策は必要ではありません。しかしながら、夏頃になると、アブラムシが発生することがあります。アブラムシは繁殖力が非常に強く、毎日数匹から10数匹もこどもを生みます。そのため、数匹だけでも発見したら、何日か経ったら大量に発生してしまうことがあります。
アブラムシが発生すると、外観を損ねますし、なによりも植物に大きな被害を与えてしまいます。アブラムシは葉を食べたりすることはありませんが、植物の液を吸って被害を与えます。そのため、大量発生すると、大量の液を座れることになりますし、吸うときにウイルスを媒介してしまうことがあります。
駆除方法としては、殺虫剤を散布したり、牛乳をかけて駆除することができます。増やし方については、挿し木を行うのが一般的です。挿し木のやり方としては、新しい枝を用いることがお勧めです。新芽が伸びる前の枝先を用いることがベターです。古すぎる枝では発根しにくいです。挿し木の長さとしては、10センチ程度でかまいません。
葉は取り除いておきますが、むしるのではなくハサミを使って切り取ってください。挿し木には水はけのよい用土を用いてください。直射日光など当たらない場所へ置き発根するまで、こまめに水を充分与えます。乾燥にはくれぐれも注意して、発根の状況を見ながら日光に当てると良いです。最初から直射日光に当てるのは生育上よくありませんし、たっぷりと水を与えることが大切です。芽や根が伸び始めたら液体肥料を徐々に与えていきます。
バーゼリアの歴史
バーゼリアは南アフリカを原産地としています。この南アフリカからヨーロッパに移って日本に渡来しました。南アフリカで生息していたものをヨーロッパに持ち込まれて、イギリスのヴィクトリア朝時代でもっとも人気を博しました。これは、開花したときに咲く白い花が非常に可愛らしいところが人々に愛されたからです。
他の植物と比較すると、ボンボンの花に似ています。開花したときの香りもすばらしいです。現在は、主にオーストラリアで栽培されて日本に輸入されることが多いです。また、花言葉は「情熱」、「小さな勇気」です。丸くて可愛いらしい姿が、心の中に芯を持っているような印象を与えることから、「情熱」という花言葉が名付けられています。
「小さな勇気」という花言葉は、白い花がたくさん咲く様子から名付けられました。つまり、花の色は白くて「情熱さ」や「勇気」とは少し印象が違うように思われるかもしれませんが、白い小さな花がたくさん咲く様子をたとえたものと言われています。さらに、バーゼリアという名前の由来はスウェーデンの化学者のイェンス・ヤコブ・ベルセリウスに因んでいます。
ベルセリウスは、近代科学において大きな功績を残した化学者です。特に元素研究においては、現在の科学においても通用する理論を数多く残しています。この化学者の名前がなぜこのバーゼリアの名前と関係するのかは、現在においてはわかっていませんが、昔から伝えられている有名な話です。
バーゼリアの特徴
バーゼリアのいくつかの特徴を挙げていきます。植物としては、常緑低木に分類されます。開花時期としては、春頃です。4月から5月にかけてが最も咲く時期です。晩秋になると、つぼみがつきます。その状態がしばらく続いて春になってそのつぼみがふくらみます。そうして、花が開くわけです。花の形は、ボンボンに似ています。
白色の小さな花をたくさんつけます。バーゼリアは、時期によって色が変わります。つまり、蕾の時は緑色で花が咲くと白色に変わります。植物学上の分類としては、ブルニア科ベルゼリア属に属します。このベルセリア属の植物は、非常に種類が多くて、その数は10種以上あります。用途としては、ドライフラワーとしてよく使われています。
ウェディング・ブーケにもよく使われています。原産地は南アフリカです。草丈については、小さいものであれば50センチ程度です。大きいものになると2メートルから3メートルまで達します。葉については、杉に似ていて非常に細かいです。来歴としては、南アフリカからヨーロッパに輸入されて、そこで人気が高まり、
日本にも輸入されました。現在においては、ヨーロッパではなくオーストラリアで栽培されたものが、日本に入ってきています。そのため、最近は鉢植えでもよく見かける程になりました。育成上の性質としては、耐暑性はもちろんですが、耐寒性も非常に強いです。そのため、夏でも冬でも戸外で生育することができます。
-

-
植物の育て方について
タイトルにもあるように、私達に生活に溶け込んでいる植物ですが、育て方や栽培方法はどのようにすれば、良いのでしょうか、一般...
-

-
ミカン類の育て方
ミカンというのは柑橘類とも言われます。柑橘は、カラタチ属やミカン亜科のカンキツ属、キンカン属やミカン科の総称です。この中...
-

-
シュウメイギクの育て方
シュウメイギクは中国が原産とも言われています。中国では根を解毒・解熱に使用されてきました。日本でも古くから本州、四国、九...
-

-
ミズナの育て方
水菜の発祥地は静岡県小山町阿多野といわれており、JR御殿場線、駿河小山駅近くに水菜発祥の地を記した石碑が立っています。静...
-

-
マンションで育てて食べよう、新鮮な野菜
皆さんは野菜はスーパーで買う方が多いと思います。とくに都会に住んでいる方はなかなかとれたての野菜を食べる機会は少ないと思...
-

-
クリンソウの育て方
被子植物で、双子葉植物綱に該当します。サクラソウ目、サクラソウ科、サクラソウ属になるので、かなりサクラソウに近い花といえ...
-

-
ユーコミスの育て方
この花はユリ科に属します。その他にキジカクシ科に属するとの考えもあります。更にヒアシンス科としていることもあります。園芸...
-

-
ラッセリアの育て方
この花については、オオバコ科、ハナチョウジ属とされています。科としてはゴマノハグサ科に分類されることもあるようです。原産...
-

-
コメツガ(米栂)の育て方
コメツガは、昔から庭の木としても利用されてきましたが、マツ科のツガ属ということで、マツの系統の植物ということになります。...
-

-
イヌツゲの育て方
イヌツゲはモチノキ科のモチノキ属の常緑性の木です。一般的には庭木に活用されていることが多いため、低木で知られていますが、...




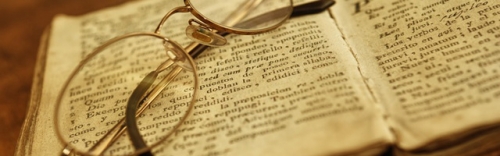





バーゼリアのいくつかの特徴を挙げていきます。植物としては、常緑低木に分類されます。開花時期としては、春頃です。4月から5月にかけてが最も咲く時期です。晩秋になると、つぼみがつきます。その状態がしばらく続いて春になってそのつぼみがふくらみます。そうして、花が開くわけです。花の形は、ボンボンに似ています。