ディエラマの育て方

育てる環境について
育て方としてはどのような環境に置くようにすればよいかです。生息地は南アフリカの南部になります。アフリカといいますと砂漠や、熱帯のイメージがありますが、こちらについては比較的涼しい気候のところもあります。南半球になり、海の向こうには南極大陸があるところです。
かと言って寒いわけではありません。咲くところとしては日当たりの良い所で、あまり周りに木々などがないところが中心になります。となると日本において育てようとするときにもそういった環境を作ったほうがよいでしょう。花が咲く時期が6月から7月ですから、花が咲く時期までにはきっちり日光が当たるところに置いたほうが良さそうです。
一方で花が終わった8月ぐらいとなると日差しが暑くなってきます。この頃になるとあまり日差しを当てるのは良くなくなります。植木鉢での管理が可能であれば少し日陰の辺りに寄せるようにするなどの工夫をしたほうがよいでしょう。この花に関しては耐暑性、耐寒性に関してはあるとされていますが、かと言ってどのような暑さにも耐えられる、
寒さにも耐えられるわけではありません。日本においてはかなり寒くなる地域もありますし、霜がおりるようなところもあります。場合によっては冬には中で管理をしたほうがいいこともあります。あやめといいますと水辺で咲くことが多いですが、その仲間としてこの花についても水分が少しあるような湿ったような土のほうが育ちやすいとされます。
種付けや水やり、肥料について
栽培においては植え付けの時期がいつ頃になるかです。日本で言えば3月くらいから4月ぐらいに植えつけるのがよいとされます。管理としてはほとんど日向に当てるところです。土に関しては水はけ、水もちを考慮した配合をするのが良いとされます。一般的に使われる花と野菜の土においては水はけも良く、それなりに栄養分も入っていますから使い勝手は良さそうです。
それに水持ちの良くなる成分をいれておけば、水やりにおいては管理がしやすくなるかもしれません。水持ちの良い土にしておけば、水を与える頻度については一定間隔で行えば済むようになります。植木鉢であれば表面が乾いたときに与えるようにします。地植えなど庭に植え付けをするときには通常は水やりの必要はありませんが、
夏に雨が降らない時期があるときにおいては少し水を与えるようにします。庭植えの場合は植木鉢の管理とは水分の状況も異なることがあるので、水分量を調節しながら与えるようにします。多年草ですが、夏前には花を落とすようになります。一応は冬でも屋外においておくことができるくらい強いです。
ただ寒い時期になると活動も弱くなるので、水分量に関しては減らし気味にするのがいいでしょう。全く減らすわけではありません。肥料についてはどのようにするかですが、植え付けのときに腐葉土やそれに該当する成分が入っているならそれで十分とされています。特に育ててる途中で与える必要は無いので、そのままにしておきます。
増やし方や害虫について
増やす方法としては株分けをすることができます。時期としては花が終わって落ち着いた頃の秋、もしくは春の芽が出る前などがいいでしょう。この頃は植え替えをする適期としても知られています。株が増えているかどうかを確認しながら行うようにします。この花に関しては球根ですから、木子が増えているかどうかを見ることもあります。
木子があればそれを外して育てるようにします。小さい状態の時は植えたとしてもすぐに花がさくわけではありません。一般的な球根の大きさにならないと花をつけませんから、数年は球根を太らせるようにして、太ったときにようやく花がつくようになります。種からも増やすことができますがその時も同じ考えになります。
花のあとに種を取り、秋や春にまきます。種から芽が出てすぐに花がさくことはなく、球根の状態に成長しないといけません。そうなるには数年がかかることがあるので、かなり時間がかかる場合もあります。ただし分球などに比べると種をたくさん取ることができれば将来的には一気に増やすことが出来る場合があります。
じっくり派になりますが、大きく増やしたいなら種からもいい選択肢になるでしょう。病気であったり害虫などについては特に心配する必要はないとされています。冬に関しても耐寒性が強いので問題は少ないですが、寒い地域の場合は一定の処置をしておきます。マルチングをすることで冬の寒さを乗り切ることが出来る場合があります。
ディエラマの歴史
想像上の動物や存在があります。神様と言いますと非常に難しい存在です。かつて人であった人を神様のように信仰することがあります。それ以外においては自分の中だけでその存在を持つようなこともあります。想像上の動物としては龍であったり麒麟などが知られています。ユニコーンも実際にいそうですが想像上と言われています。
神様に近い存在として天使と言われる存在があります。神様がおじいさんのような雰囲気を持っているのに対して、天使は子どものような、赤ちゃんのような存在です。背中に羽をつけていて、頭の上には輪を浮かべています。天からの使いとのことで、亡くなったときには天使に連れられて天の方に行くと想像されています。
そんな想像上の存在ではありながら、いろいろな名前において付けられることがあります。その一つとしてあるのがディエラマと呼ばれる植物になります。この植物は原産としては南アフリカのケーブ地方南部とされています。こちらにおいて45種類近くがあるとされています。ディエラマの意味としては古代ギリシア語から来ていて漏斗を意味するようです。
確かにそのように見えないこともありません。その他に英名としてあるのがエンジェルズフィッィングロッドとあります。天使の釣り竿です。なんとも可愛らしいといいますが、神々しい名前が付けられています。その他にも妖精の杖であったり、杖の花などとされています。あまり見ることができない花として付けられたのかもしれません。
ディエラマの特徴
いろいろな名前がついている花ですが、アヤメ科になります。球根によって生育をしていく植物で、多年草として楽しむことができます。草の高さとしては1メートル50センチぐらいになるものがありますが、1メートルぐらいのものが多くなるかもしれません。花が咲く時期としては6月から7月くらいとされています。
あやめがその頃に花を咲かせていますから、ちょうど重なる時期です。葉っぱに関しては常緑で、花の色は紫、ピンク、白色などがあるとされています。この花に関してはまずは比較的丈夫な茎が生えています。この茎は曲がったりすることなくまっすぐ上を向いています。ただし花がたくさん付いているときはやや曲がったようになります。
そしてこの茎の途中から花がつく枝が伸びます。この枝が非常に細いです。主要な茎は緑色ですが、花がつく枝は紫色の針金のようです。そしてその先に大きな花がついています。これを見ると天使の釣り竿と言われる理由が少しずつ分かります。つまり花が釣り上げた魚で、花の枝が釣り糸、茎が釣り竿のように見えます。
いくつも花が付いているとまるで魚が沢山ついているようにも見えます。これだけ細い枝なので、茎から出る段階で枝は下を向いています。当然ながらその先についている花も下を向いています。花びらが何枚かついていますが、その花びらが開ききるのは難しいようです。筒状のまま下を向いて咲くことになります。いくつも花が重なることがあります。
-

-
ラナンキュラスとコカブの育て方
ラナンキュラスは小アジア原産の小球根植物であり、花は花弁が重なり合って明るい光沢があり、ふっくらとした華やかな魅力を持っ...
-

-
ナンテンの育て方
ナンテンはメギ科ナンテン属の常緑低木です。原産は日本、中国、東南アジアです。中国から日本へ古くに渡来し、西日本を中心に広...
-

-
パンジーの育て方について
冬の花壇を美しく彩ってくれる植物の代表格は、なんといってもパンジーです。真冬の街にキレイな彩りを与えてくれる植物としては...
-

-
コヒルガオの育て方
コヒルガオの大きな特徴は、その花の咲き方です。アサガオやヒルガオと同じ様な咲き方をしています。またヒルガオと同様、昼ごろ...
-

-
チューリップの育て方
チューリップといえば、オランダというイメージがありますが、実はオランダが原産国ではありません。チューリップは、トルコから...
-

-
ライチを育ててみましょう。
ライチという果物はよくレストランなどで食べることができますが、日本で食べることができるのはほとんど冷凍のものであり、生の...
-

-
キュウリの育て方について
キュウリは、夏を代表する野菜であり、カリウム・ビタミンC・カロチンなどの栄養素が豊富に含まれた野菜です。浅漬けにしたり、...
-

-
セントポーリアの育て方
セントポーリアの原産はアフリカです。アフリカに進出していたドイツが、現在のタンザニアあたりを生息地としていた花を見つけた...
-

-
ミニヒマワリの育て方について
一言で「ミニヒマワリ」といっても、品種改良が行なわれ、中小輪の矯性品種まで、数多くのミニヒマワリが存在しています。大きな...
-

-
ナバナ類の育て方
ナバナ類と人類との歴史は古く、その関わりは現代でも続いています。地中海沿岸が原産の野菜であり、最初の利用は麦畑を生息地と...




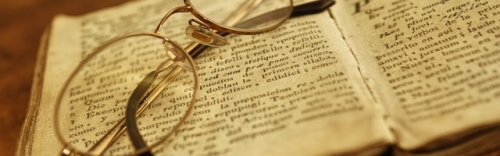





いろいろな名前がついている花ですが、アヤメ科になります。球根によって生育をしていく植物で、多年草として楽しむことができます。草の高さとしては1メートル50センチぐらいになるものがありますが、1メートルぐらいのものが多くなるかもしれません。花が咲く時期としては6月から7月くらいとされています。