チコリ、トレビスの仲間の育て方

育てる環境について
チコリは寒さに強く、暑さに弱い植物です。地中海沿岸で盛んに作られていることからも分かる通り、高温多湿は苦手です。どちらかというと涼しく風通しが良い場所を好みます。そのため育て方のポイントとして、夏の暑さ対策をしっかり行う必要があります。夏は日当たりは良いが日陰も出来る場所を、最初から選ぶと安心です。
湿気が苦手なだけあって、土の水はけが良い場所が向いています。根の部分を使いたい場合は、なるべく深く土を耕すと良いでしょう。耕すことで、根の生育も良くなります。土はアルカリ性が適しています。日本の場合、雨が多いので土の中にあるカルシウムが水で流されることがよくあります。また、野菜の栽培などで酸性の肥料を多く使います。
そのため、土が酸性化しやすいです。チコリが好むようなアルカリ性の土にするためには、消石灰や苦土石灰を撒いて対策を取ります。土壌改良対策は、種を蒔く2週間くらい前には実行しておきます。ただ、土地によって土の性質は違います。今までも野菜を育てていた場所とそうでない場所、酸性土壌を好む植物が生えている場所など、それぞれ石灰の量が違います。
栽培する場所の土はどうか、よく見極める必要があります。トレビスやその仲間であるヴェローナも同様に、日当たりや水はけが良い場所を好み、強い酸性の土壌は不向きなので石灰での中和が欠かせません。水はけを良くするために、
あらかじめ堆肥も撒いておきます。石灰で土壌改良を行い、数日後に堆肥を撒いて環境を整えます。堆肥の他、必要に応じて化学肥料も同時に使います。どちらも石灰と同じように、選んだ場所によって使う量が異なります。栽培を成功させるために、育てる環境づくりはしっかりと行いたいところです。
種付けや水やり、肥料について
野菜として利用するチコリは、主に軟白化させた葉の部分です。しかし薬用では軟白化を行いません。一定温度での栽培など、初心者にも少し難しいかもしれません。軟白化を行うには、初夏に種を蒔いて育て、秋に作業をします。秋になったら掘り起こして、根から30センチぐらいの所で切り落とします。
それを、あらかじめ腐葉土を混ぜてある土の入った深めの場所に植え付けます。植える時は根が完全に隠れるようにします。できるだけ10℃位に保ち、上から段ボールや黒いビニールシートで覆いをかぶせます。芽が出たら、10から20センチぐらいになるまで育てます。こうすることで、葉が白く軟らかくなります。
軟白化は2年目から行った方が良いとする指導書もあります。確実に成功させるなら、しっかり育った2年目の方が良いかもしれません。軟白化を意識しない場合は、春と秋、両方で種付けが出来て、夏から秋の間は花が見られます。そのため、1年中楽しめる植物でもあります。一般には暑い夏を避け、秋の栽培が主流です。
株は成長すると1メートル以上になるため、支柱を用意しておきましょう。株と株との間は20から30センチほど空けます。本葉が出たら間引きを行い、株間に余裕を持たせます。水は土の表面が乾いたら与えます。ジメジメと湿った状態にしないよう、土の状態をこまめにチェックすると良いです。
追肥は植えてから2週間後、化学肥料を軽く与えます。追肥の回数は毎月一回とする場合もあれば、全体で3回程度とする場合もあります。追肥は、栽培に利用している土地の状態を見て判断するのがベストです。
トレビスやヴェローナは軟白化しなくても食べられます。水はけや日当たりが良い場所を好むのは、チコリと同じです。栽培時期も同様で、暑さを避けて秋から栽培を始めるのが主流です。ただ、冬はビニールのトンネルなどで寒さ除けをすると良いです。
増やし方や害虫について
チコリもトレビスやヴェローナも、もともと病害虫被害は少ない植物です。しかし主な生息地が暑すぎず快適な場所のせいか、暑さには弱いという弱点があります。あるデータでは、気温が28℃になると、湿気と暑さから根が腐りやすくなるという結果が出ています。根腐れを避けるには、やはり秋から栽培を始めた方が良さそうです。
水のやり過ぎや梅雨時の雨の多い時などは、カラッとした気候が原産地の植物にはダメージがあります。アブラムシは、これらの植物に付きやすい害虫の一つです。秋から冬に育てた方が、寒いこともあって虫もつきにくいです。害虫や根腐れを避けるには、秋の栽培が一番良いでしょう。
秋から育てた場合は、初心者が栽培しても病気にもかからず、虫も特につかないという例が多いです。増やしたい時も、秋から行うと良いです。ただ、チコリは根がまっすぐで、根が傷ついたりすると枯れてしまいます。一度きちんと植えたら移植は出来ないと思った方が良いです。そのため増やすには、株分けではなく新たに種から育てます。苗状になったものが秋になると出回ります。
一番簡単な方法は、苗を購入して新たに栽培することです。チコリの場合は苗を購入しやすいのですが、トレビスやヴェローナは、まだまだあまり見かけません。増やす時は種からが主流です。トレビスには暑さに比較的強いレッドストーンという品種があります。湿気にも通常より強めで栽培しやすいので、初めて作る時に適しています。
チコリ、トレビスの仲間の歴史
チコリはキク科キクニガナ属の植物で、和名はキクニガナと言います。フランスではアンディーヴと言う名の野菜で、広く生産されて知られています。特に料理に詳しい人は、どちらかというとアンティーヴという名前の方に馴染みがあるかもしれません。原産地はヨーロッパからシベリアにかけてのユーラシア大陸と北アフリカにかけての地域です。
日本で知られるようになったのは比較的最近ですが、歴史の古い野菜です。現に、古代ローマの書物にも登場しています。記述によると、当時既にサラダの素材として食べられていたうえ、薬草としても使用されていたようです。実際に今でも生薬が主原料の薬には、チコリが入っていることがあります。
近縁種のエンタイブは江戸時代にやって来ましたが、チコリが日本に導入されたのは明治に入ってからです。しかし、当時はあまり普及しませんでした。近年、今まで馴染みがなかった西洋野菜も家庭菜園で気軽に作る人が増えました。その中で、徐々に認知されるようになっています。西洋ハーブの普及とも関係がありそうです。
同時に、家庭菜園愛好家の間で知られるようになってきた植物に、トレビスがあります。トレビスはチコリが変容したもので、イタリアのトレビス地方で盛んに作られているため、こう呼ばれています。現地ではラディッキオと言う名で親しまれています。
トレビスの仲間には長く伸びるものや丸く成長するものなど、様々な種類があります。日本でよく見るのは、赤キャベツのような外観をしたタイプで、本来はレッドチコリと呼ばれています。近年になって普及した物で、いずれは他の品種も日本で広まるかもしれません。
チコリ、トレビスの仲間の特徴
チコリの特徴は、サラダ野菜や薬用ハーブとして、昔から口に入れるために利用されてきたという点です。食用にしているという点では、トレビスの仲間も同様です。食用ではありますが、花を咲かせた姿は可憐で、観賞用としても役立ちます。青紫色をした花や若葉は、そのまま収穫してサラダとして食べられます。
若葉以外の葉はそのままでは食べられず、軟白化を行ってから食用に用います。軟白化後に収穫した物は、少し苦くて独特の香りがあります。ヨーロッパではサラダの他、グラタンや煮込み料理などで使われています。薬用として利用するのは、主として根の部分です。葉が茂ってくる時は、土の下で根も大きくなっています。
大きくなったら株を掘り起こして根の部分を切り取り、乾燥させると薬用になります。乾燥させた後に刻んだ根を煎ることで、代用コーヒーとしても利用できます。他のハーブと合わせ、ハーブティーとして飲んでも良いでしょう。利尿作用があるのでむくみ対策への効果が期待できるほか、貧血や気管支炎にも効くと言われています。
一方トレビスの特徴は、何と言っても赤いキャベツのような外観です。外側の葉は苦いので、使うのは何枚か剥がした実の部分です。外側を剥がすと、キャベツよりも柔らかく独特の苦みがあり、中は白いです。サラダなどの生食に向いています。最近は、白菜に似た形状をして葉の部分が赤いヴェローナも、西洋野菜として日本で見かけるようになりました。ヴェローナはトレビスの仲間です。
-

-
西洋クモマソウの育て方
原産地はヨーロッパ北部といわれています。漢字で書くと雲間草で、ユキノシタ科の植物です。雲に届きそうな高い山間部に生息する...
-

-
エピスシアの育て方
エピスシアはメキシコの南部からブラジル、コロンビア、ベネズエラなどを原産地としている植物で生息地は基本的には熱帯地方なの...
-

-
レナンキュラスの育て方
レナンキュラスはキンポウゲ科・キンポウゲ属に分類され、Ranunculusasiaticsの学名を持ち、ヨーロッパを原産...
-

-
ザクロの育て方
ザクロの歴史は非常に古く、古代ギリシャの医学書では、すでにザクロの効能が書かれていました。また、パピルスに記されているエ...
-

-
アグロステンマの育て方
アグロステンマは原産地が地中海沿岸で、日本に渡来したのは1877年のことでした。渡来した当初は切花として利用されていたの...
-

-
クワズイモ(Alocasia odora)の育て方
涼しげな葉で人気のクワズイモですが、その名はサトイモに似た葉からつけられました。サトイモに似てはいますが、イモに見える茎...
-

-
アボカドのたねは捨てずに育てよう
「森のバター」とも呼ばれている果実をご存知でしょうか。これは、アボカドの事を指しますが、栄養価が高く、幅広い年代に人気の...
-

-
リクニス・ビスカリアの育て方
リクニス・ビスカリアの歴史はそれほど解明されていません。実際語源はどこから来ているのかははっきりしていませんが、属名のリ...
-

-
花壇や水耕栽培でも楽しめるヒヤシンスの育て方
ユリ科の植物であるヒヤシンスは、花壇や鉢、プランターで何球かをまとめて植えると華やかになり、室内では根の成長の様子も鑑賞...
-

-
ウコンの育て方
ウコンという名前は知っているものの、現在では加工されて販売されていることがほとんどのため、実際にはどのような植物であるか...




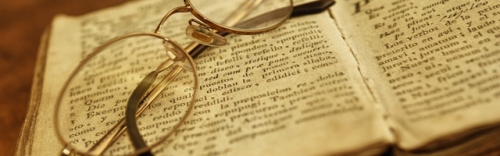





チコリはキク科キクニガナ属の植物で、和名はキクニガナと言います。フランスではアンディーヴと言う名の野菜で、広く生産されて知られています。特に料理に詳しい人は、どちらかというとアンティーヴという名前の方に馴染みがあるかもしれません。原産地はヨーロッパからシベリアにかけてのユーラシア大陸と北アフリカにかけての地域です。