セロペギアの育て方

育てる環境について
セロペギアの育てる環境に関しては、やはり日当たりがよくて、気温が高いことが一番成長にいいです。セロペギアの置き場所に関しては、一年を通じて日当たりの良い場所がいいです。そして日当たりがいい場所で育てることによってつぼみをたくさんつけてくれます。また室内で管理していたセロペギアを春になってきたら屋外に移動させてあげます。
屋外に移動させてあげるタイミングに関しては、夜間が15℃以上になったら日当たりのいい場所に置いてあげます。そして夏に関しては、明るい場所で育てます。日陰でも育つことはできますが、成長がしにくくなってあまりたくさんの花が咲かなかったりします。だから午前中だけでも日当たりがいいところに移動させてあげると花もたくさん咲いてくれます。
花のためにも、日に当ててあげることが大事になってきます。そして秋になったら早めに屋内に取り入れてあげます。そして室内の明るい窓辺などで管理します。そうすることによって、秋でも最低温度が15℃ぐらいになるまでは室内で咲いてくれます。そして冬になってくると冬越しし易いように管理してあげます。
多肉の性質を持っている植物になるので、水はあまり与えなくても育てることができます。あげすぎてしまうと、根ぐされの原因になってしまうので乾燥気味です。そして冬越しをすることができるように10℃以上で管理できるようにしてあげることによって、また春に花を楽しむことができますので、冬は温度に気をつけます。
種付けや水やり、肥料について
セロペギアを植木鉢で育てる場合はあまり頻繁に土が乾かない状態で与えるのではなく、しっかりと乾いた状態になったら与えるようにします。そのときは乾いた土にたっぷりと垂れるまで与えてあげます。そして受け皿などには水は貯めないようにしないといけないです。どうしても水を貯めておいたりすると、蒸れの原因になってしまったりします。
しっかりと乾いたらそのつど水は与えてあげるようにしていきます。そして冬の水やりに関しては、土が乾いてすぐに水を与えてあげるのではなく、1日や2日ぐらいは置いてから水を与えてあげるといいです。あまり与えすぎないように気をつけてあげます。水を与える回数などは多くなくて済む植物です。そして育ち方は横に茎が伸びていきます。
だから土のところなどに花が枯れてしまったりと、どうしても土のあたりが枯れ葉が出来てしまったり、雨水がたまったりと、蒸れてしまう原因になってきます。だから土の当たりはしっかりとお手入れをして、汚れないようにしてあげるといいです。そして風通しをよくして育てます。また肥料の与え方に関しては、ある程度与えるほうがいいです。
しかし他の植物よりも肥料を好むものではないので、あまり与えすぎなくてもいいです。少し少なめに春から夏に与えてあげるようにしておけばいいです。置き肥料などを置いておくのもとても便利です。簡単な肥料を与えておくだけでいいので管理はとても簡単にして育てることができます。
増やし方や害虫について
セロペギアは比較的簡単に増やすことができる植物です。セロペギアの性質として、横に茎が這っていって成長していきます。だからどんどん横に這っていって育っていきますので、這って行ってるところを隣の鉢に伸ばして茎の節を土をかぶせておきます。そうすることによって、隣の鉢に根を出してそこで育ってくれます。
ある程度しっかりと隣の鉢に根が出てきたら、適当な場所かた切ってしっかりと育ててあげます。また剪定してきり戻したりするときに切った茎を葉を数枚残して挿し木で増やすこともできます。だから要らなくなった茎などを挿し木にしてあげてもいいですし、また這わせて根を出させてあげても育てることができます。
どちらの増やし方にするかはそのときによって決めるといいです。這わせて根を出させる方法のほうが確実に根を出すことができたりしますのでおすすめの方法です。隣の鉢以外でも、その場で根が出てるのを切って植えるという方法もあり、比較的簡単に増やすことが可能になっています。
また害虫に関しては、セロペギアは特にほとんど心配することはないです。しかし夏になってくると、蒸れてしまったり葉っぱが乾燥してしまいます。そういったときに、害虫の被害にあいやすいです。だから害虫の被害にあわないようにするためにも、葉っぱを葉水をしたりして乾燥をしないように予防することが大事になってきます。そして風通しのいいところにおいて、できるだけ乾燥や蒸れを防ぎます。
セロペギアの歴史
セロペギアはガガイモ科の植物です。横に這うように茎が伸びて成長していきます。そして原産はカナリア諸島やアフリカやマダガスカルやインドや中国南部などに生息地として栽培されています。その中で一種がニュージーランドとオーストラリアで栽培されています。比較的暖かいところを好む植物になっていて、育て方も寒くならなければ丈夫で育てやすい植物です。
白い花とつるのように伸びていきますので、這わせて育てることができます。そして暖かければ周年花が咲いてくれる植物です。多肉性の常緑多年草つる植物ですので、長い間楽しむことができます。管理も簡単で、肥料もあまり与えないでいいですし、また水やりなどに関しても、
乾いたら与えるようにしておけばそんなに頻繁に与える必要がないのでおすすめです。冬が寒い地域で育てないといけない場合に関しては、寒い冬の間は室内に移動させてできるだけ暖かい環境で育ててあげるようにしておくことが大事です。あまり日本ではなじみのない植物になっていますが、しっかりと暖かく育てておけば花をいつまでも楽しむことができますし、
また育てやすい植物です。害虫の被害などもほとんどなくて、夏の蒸れやすい時期や乾燥してしまうときなどには葉の裏などに害虫が発生してしまうことがでてきたりしますので、注意が必要です。できるだけ風通しをよくしてあげることが大事です。どうしても這って育つ植物になりますので、土の近くなどは蒸れやすくなってしまいます。
セロペギアの特徴
セロペギアは日本であまりなじみのある植物ではないです。だから育て方に正解がまだはっきと解ってるものではないですが、比較的暖かいところで育てるようにしておくといいです。そして開花する花がしおれてしまうまでは短くなってしまいます。しかし温度に気をつけて、日当たりをしっかりとしておくと、一年中咲いてくれる性質があります。
だから上手に育てることができたら、かなり長い期間楽しむことが可能な植物です。そして花の咲く時期に関しては、常温の場合で花が咲き始めるのは5月頃からです。そして10月下旬位まで外でしっかりと咲いてくれます。だからその月下旬以降になってくると寒くなってきますので、室内に移動させてあげるといいです。
できるだけ花を長い間楽しみたいという場合は、温度が高めでしっかりと根を張って大きくなってくれると、どんどん花も咲いて楽しむことができます。だからセロペギアは日当たりと温度をしっかりと管理して育てていったらいいです。日当たりがいいことがたくさんの花を咲かせてくれる条件になってきます。肥料に関しては、
あまり与えなくてもいい植物になりますが、与える時期は張るから夏にかけての成長期になります。成長期にあまり与えすぎない程度に与えておくとよく育ってくれます。そして水やりに関しては、土が乾いたら与えるようにして、土が湿った状態のときに水を与えてしまうと、蒸れの原因になってしまったりします。乾き美味が一番いいです。
-

-
オルキスの育て方
このような面白い形の植物は、ラン科に多いのですが、やはりこのオルキス・イタリカもランの一種で、オルキスとはランのことで、...
-

-
ジギタリスの育て方
ジギタリスの原産地は、ヨーロッパ、北東アフリカから西アジアです。およそ19種類の仲間があります。毒性があり、食用ではない...
-

-
植物を育てたことがない人でも簡単に収穫できる大葉の育て方
大葉は日本の風土でよく育つ植物です。育て方も簡単で家庭菜園初心者でも簡単に収穫を楽しむことができます。また、ベランダに置...
-

-
キルタンサスの育て方
キルタンサスの科名は、ヒガンバナ科 / 属名はキルタンサス属になり、その他の名前:笛吹水仙(ふえふきすいせん)、ファイア...
-

-
セイロンベンケイの育て方
セイロンベンケイというのは、ベンケイソウ科リュウキュウベンケイ属の植物で別名トウロウソウと呼ばれることがあります。ベンケ...
-

-
ヨツバシオガマの育て方
ヨツバシオガマ(四葉塩竈)学名Pedicularisjaponicaは、初夏から夏の、北海道から本州中部の高山の湿地を生...
-

-
メコノプシスの育て方
ヒマラヤの青いケシと呼ばれる、メコノプシス・グランディスは、その名の通り、原産地がヒマラヤ山脈かチベット、ミャンマーなど...
-

-
アボカドの種を植えて観葉植物にしよう
アボカドというと、「森のバター」や「バターフルーツ」と呼ばれ、高脂肪で栄養価が高いことで有名です。脂肪分の80%以上が不...
-

-
ヘーベの育て方
ヘーベの特徴は次のようになっています。オオバコ科のヘーベ属に分類されており、原産地はニュージーランドになります。分類は常...
-

-
パフィオペディラムの育て方
パフィオペディラムはランの仲間です。熱帯から亜熱帯アジアに約70種が分布しており、東南アジアから中国南部、インド、インド...




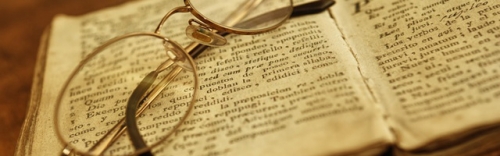





セロペギアはガガイモ科の植物です。横に這うように茎が伸びて成長していきます。そして原産はカナリア諸島やアフリカやマダガスカルやインドや中国南部などに生息地として栽培されています。その中で一種がニュージーランドとオーストラリアで栽培されています。比較的暖かいところを好む植物になっていて、育て方も寒くならなければ丈夫で育てやすい植物です。