レティクラツム・オウァリウムの育て方

育てる環境について
育て方としては環境が大事になってきます。日当たりが必要になります。半日陰においても何とか育てることができますが、日照不足になると葉の色に影響してくるとされています。この花としては葉っぱを楽しむ部分もありますから、葉っぱの色が十分出ないのは少し不満が残ることになるでしょう。更には花つきが悪くなることもあります。
葉っぱも立派ですが、花も非常にきれいですからそれを楽しめないとなると非常にもったいないでしょう。そのようにならないためにも日当たりをできるだけ確保するようにします。葉っぱに斑の模様が入ってしまうのは日当たりが足りないからの場合があります。鮮やかな模様が出るのが普通ですが、ぼやけたような模様になります。
観葉植物の場合はどうしても日当たりに当てるのが難しくなることがあります。そのことからも置き場所を考える必要が出てきそうです。空気としては湿り気がある所が良いとされます。これは日本においては夏などには湿度が高くなりますから良い環境になるかもしれません。暖かいところ、暑いところにおいては特に問題がないので、
春から秋にかけては窓際、ベランダなど日当たりの良い所にしっかりと置くことができます。しかし耐寒性がありません。10度以上だと安心して育てられるとされます。最低5度ぐらいなので屋外で置くのは少し無理でしょう。温度そのものが5度以上でも乾燥した冷たい風にあたることで傷むことがあるので、屋内が安全です。
種付けや水やり、肥料について
栽培をするときに植え付ける場所の用土としては湿り気を考慮した配合にします。水はけがあまり良すぎると水分不足になってしまうkとがあります。赤玉土の小粒タイプの場合であればそれなりに湿り気を維持することができるので良いかもしれません。配合例としては、赤玉土小粒を7割、腐葉土を3割などにしておきます。
水やりとしては、春から秋においては生育期になります。この時期においては土の表面の様子をよく見ておきましょう。手で触って見て水分がつかないようであれば乾燥していますからこの時には水分をしっかり与えるようにします。土自体は水分をキープしやすくなっていますから、表面が乾いていると中の方もかなり乾いてきている可能性があります。
乾いた状態ですぐに水やりをしてもまだ大丈夫です。湿り気を好みますが、乾燥に弱いわけではありませんから、多少水をやらないからすぐに弱ることはありません。でも元気良く育てるならいい環境が必要になります。室内管理としても冬になるとどんどん気温が下がってきます。それとともに生育も鈍ってきます。
そうなると水分についても吸わなくなってきます。秋の終わりに近づいてきたら、徐々に水の回数、あげるタイミングを変えます。肥料は、春から秋の成長期に与えます。チッソ、リン酸、カリの三要素が等量含まれるタイプを置き肥しておきます。花の種類によってはリン酸の量を調節したほうが良いこともあるので、種類を確認しておきます。
増やし方や害虫について
増やし方としては挿し木を行うことができます。時期は5月から8月です。健康な枝に対して、10センチぐらいに切ります。それをバーミキュライトであったり鹿沼土などにさしておきます。根が張ってくれば通常の土に植え替えをするようにします。この植物に関しては植え替えを定期的に行うようにします。2年から3年に1回ぐらいの頻度で行います。
株が大きくなっているときは鉢の大きさを変える必要があります。変えないと根が伸び切れなくなります。一回り、二回りぐらい大きな鉢を用意しておきます。サイズを変えずに植え替えをしたい場合、5月から6月において枝葉を切り詰めるようにします。この時は、枝葉が3分の1から2分の1程度が残るくらいまでです。
その時の土においては、元々の土が3分の1ぐらいになるまで一旦減らします。そして新しい土を加えてうえるようにします。そうすることで植木鉢自体は変えなくてもスッキリと植え替えをすることができます。樹形において間延びしてくると形が良くなくなります。植え替えの時か10月に冬越をする前などに剪定をします。
葉っぱがついている枝についてはそのまま残して、間延びしている枝を切るようにしていけばよいでしょう。病気についてはありませんが、冬の管理で当たったり、水分の管理に気をつけるようにします。害虫としてはカイガラムシが出ることがあります。枝葉が増えすぎたときに発生するので、ある程度剪定が必要になります。
レティクラツム・オウァリウムの歴史
最近は動物園や水族館などが人気のようです。動物の種類だけでなく、どのように動物を見せるかに注目したところが多くなっていて、あまり人が集まらないような地域でも来場者を増やしているとされています。動物を見せるところだけでなく植物を見ることが出来るところである植物園と言われるところもあります。
動物園などと同様に市区町村が運営することもあれば、大学に併設されているところ、民間のところなどもあります。こういった植物園においては大抵は温室と呼ばれるところがあります。真冬に行っても中は暖かく、湿気もあります。熱帯地域の温度を再現しているようです。
そういったところには熱帯や温帯を生息地とする植物が沢山展示されています。レティクラツム・オウァリウムと呼ばれる植物も原産地としては世界の熱帯から亜熱帯になっていますから、植物園で展示をされるのであれば温室などで管理されることになるでしょう。この花については、名前がたくさんあります。
まず和名としてあるのがマルバルリハナガサモドキがあります。漢字だと丸葉瑠璃花笠擬きとなります。その他にはプセウデランテムムがあります。プセウドについてはギリシア語においては否定を意味するとされています。
この花についてエランテマム属の植物に似ているけども実際は異なるとしてこのような名前が付けられたとされています。和名についても似ているけども違うのでモドキとありますから似たような付け方になります。
レティクラツム・オウァリウムの特徴
この花についてはキツネノマゴ科、プセウデランテムム属となります。園芸上の分類としては熱帯植物です。また暖かいところに生息している植物なので、日本において冬に屋外で管理するのは難しいでしょう。そのことから観葉植物としての利用もあります。咲く形態としては花よりも木としてなので低い木として知られています。
木の高さとしては2メートルぐらいになります。花が咲く時期としては4月から10月と比較的長く花が楽しめる植物になります。花の色としては紫色の花や白っぽい花があります。熱帯なので耐暑性につてはありますが耐寒性についてはあまりない植物です。常緑性なので、冬に室内で管理をしておけば葉っぱを楽しむことが出来るようになっています。
花の特徴としては開く部分と筒状になった部分があります。半分以上は開きますが、その他は筒状のまま維持されています。開いたときに花びらのように開きますが、実際は花びら自体はもう少し大きいのでしょうが、それ以上は開かないようになっています。紫のタイプの花になると全面的に紫の花になりますが、白っぽい花の場合は、
中心部分が多少紫色っぽくなっていることがります。花びらのように分かれるときは4枚から5枚に分かれて開きます。それぞれは重なり合いません。葉っぱに関しては非常に大きいです。花に比べるとかなり大きく、葉っぱの鑑賞のために育てることも多いです。幅の広い楕円形で、和名にあるとおりに丸い葉に見えます。
-

-
パンジーの育てかたについて
スミレ科のパンジーは、寒さには強いのですが、暑さに弱く、5月前後に枯れてしまいます。ガーデニング初心者の方には、向いてい...
-

-
ダボエシアの育て方
ダボエシアは学名でDaboeciacantabrica’bicolor’といいますが、分類で言うとツツジ科ダボエシカ属に...
-

-
ネムノキの育て方
ネムノキは原産地が広く、日本や朝鮮半島、中国、台湾、ヒマラヤ、インドなどが代表的なものとなっています。このほかにもイラン...
-

-
シラネアオイの育て方
シラネアオイの原産地は、日本で日本固有の壱属一種の多年草の植物ですが、分類上の位置が二転三転してきた植物でもあります。昔...
-

-
ニオイバンマツリの育て方
ニオイバンマツリはナス科の植物で南アメリカが原産となっています。生息地はブラジルやアルゼンチンなどの南米の国々となってい...
-

-
アプテニアの育て方
この花については、ナデシコ目、ハマミズナ科となっています。多肉植物です。葉っぱを見ると肉厚なのがわかります。またツヤのあ...
-

-
オオバハブソウの育て方
オオバハブソウはオオバノハブソウとも言われ、古くから薬用として珍重されてきた薬草です。江戸時代に渡来した当時は、ムカデ・...
-

-
ドラキュラの育て方
ラン科の植物は、非常に美しく奇をてらった造形の花が多いのですが、それが美しさに起因しているので、その美しさからガーデニン...
-

-
ライチを育ててみましょう。
ライチという果物はよくレストランなどで食べることができますが、日本で食べることができるのはほとんど冷凍のものであり、生の...
-

-
アイスランドポピーの育て方
ポピーというケシ科はなんと26属250種も分布しており、ケシ科ケシ属でも60種の仲間が存在します。ケシ科は麻薬成分モルヒ...




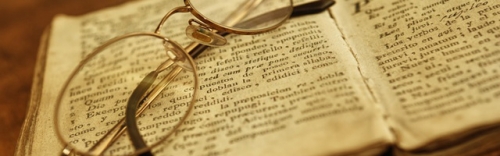





この花についてはキツネノマゴ科、プセウデランテムム属となります。園芸上の分類としては熱帯植物です。また暖かいところに生息している植物なので、日本において冬に屋外で管理するのは難しいでしょう。そのことから観葉植物としての利用もあります。