ルリマツリの育て方

育てる環境について
主に日当たりのよい場所で育てます。日照不足になると極端に花付きが悪くなるので注意が必要です。地域にもよりますが、鉢植えの場は5月上旬頃から徐々に屋外に出して育てるようにするのが一般的です。4月ごろから売られている開花中の株は、冬の間も加温しているので開花が早くなっていますが、
屋外で冬越しさせた株の場合は気温の上昇とともに5月頃より枝を伸ばし始め気温が開花温度に達する6月から7月ごろから花を付け始めます。暑さの厳しい国を生息地としている種ですので夏の暑さや強い日光には非常に強いですが、やや乾燥に弱い傾向があります。真夏の、乾燥がひどい時期は、鉢植えは半日陰に置くようにします。
特徴にもあるように、低温下ではほとんどの葉が落ちてしまいますが0℃以上あれば冬越しさせることが可能です。関東地方より西の暖地であれば、南向きの暖かい場所に早めに植え寒風や霜に気をつけることで屋外での冬越しをさせることもできます。熱帯や亜熱帯原産の半つる性植物は暑さに強く寒さに弱いことが特徴とされていますが、
その中でも「ルリマツリ」は耐寒性が強い植物です。寒さに当たると落葉してしまうものの木自体が枯れてしまうことが少ないため、寒さが厳しい場合は地表をワラ等で覆うか、株元に盛り土をすることでより丈夫な状態で冬越しさせることができます。
寒冷地や山間部でも霜が下りる前に室内に移動させ冬越しをさせることで、栽培が可能です。また、早く開花させたい場合は屋外で冬越しをさせずに室内で葉を残したまま管理するか、冬から春にかけてビニールなどで株を覆い開花温度に早く近づけることで早期開花を見込めます。
種付けや水やり、肥料について
植え付けは5月から7月に行い、赤玉土と腐葉土を6:4の割合で混ぜた用土か、市販の花・野菜用の土に植え付けます。種で出回ることは滅多になく、株単位で鉢植えで出回っているものを植え替えることが一般的です。根詰まりした株は鉢土を三分の一ほど落としてから植え替え、枝も半分ほど間引きます。
せん定は開花後に間延びしたり、大株になって全体的なバランスが乱れた際に行います。適湿を好み、強い乾燥を嫌うため春から秋の生育期は土の表面が乾きはじめたら鉢の場合は鉢底から水がしみ出すまでたっぷりと水を与えます。極度の乾燥は葉を痛めたり、開花している場合は花の寿命を縮めてしまう可能性があります。
また、真夏の乾きやすい時期には朝夕の2回を目安に水を与えるとよいです。それでも土が乾くようであれば、鉢の場合は半日陰に移動すると水切れ防止になります。冬の間の水やりは鉢が凍るのを防ぐため天気の良い午前中に済ませるようにするのが理想的です。冬の低温な環境では成長が止まるので、水やりの回数を徐々に減らしていき乾燥気味に管理します。
とくに低温期は多湿による病気が発生しやすいので土が常に湿っているような状態にならないよう気をつける必要があります。暖かい気候と日光が多く当たる環境では非常に生育旺盛なので、よく枝を伸ばし花つきも早くなります。そのため1週間に1回、液体肥料を与えるようにします。固形肥料を施す場合は月1回を目安に施します。
増やし方や害虫について
せん定した切り枝は、その年に延びた枝なら挿し木が可能で、一度根付かせることが出来ればどんどんふやすことが可能です。適正時期は5月から7月で、先端の一番柔らかい所と木質化した所を避け、それ以外の枝を10cmほどの長さに切り、土に挿します。この時、市販の発根剤等を用いるとより活着率がよくなります。
根が出てきてから生長をはじめるまでは明るい日陰に置き、乾かさないように管理します。気温の高い時期ならよく根付き、成功率が高いです。害虫はアブラムシ、アオムシ、ヨトウムシなどに注意する必要があります。これらは発見しやすく、少数なら自力で駆除することが可能ですが、このほかに高温時には、ハダニ類とスリップス類が付くことがあります。
これらは「ルリマツリ」に限らずほとんどの植物につき、大変小さいために発見が遅れることがあります。そのため日頃の観察が大切です。注意して観察する点としては、葉の色が急に悪くなっていないか、葉の形に異常がないか、の2点です。上記の点が見られた際は葉の裏側などもよく観察し、市販の殺虫剤で対応してください。
(古い葉の裏に白い粉状の物が付く場合がありますが、これは植物の性質上の物で病気や害虫ではありません。)また、低温多湿の環境では様々な病気が発生します。ポピュラーなものとして菌核病があります。この病気は株元近くの茎が腐ったように軟らかくなり黒く変色して株が枯れてしまう病気です。他の植物にも伝染するので発生した株は早めに処分する必要があります。
菌核病の予防として、発生する前に殺菌剤を散布することが有効的です。次に、灰色カビ病というものが発生しやすいです。灰色カビ病は菌核病に似ており低温多湿で発生し茎や花に灰色のカビが生えたのち、他の箇所にも広がります。発生する環境を作らないのが一番の予防策なので枯れた花や葉はこまめに取り除き、風通しをよくしておくことが大切です。
ルリマツリの歴史
「ルリマツリ」は、南アフリカ、オセアニア原産のイソマツ科プルンバゴ属常緑小低木です。半つる性の熱帯植物であり別名「プルンバーゴ(正式名称=プルンバーゴ・アウリクラータ)」とも呼ばれ、学名を「プルンバーゴ・アウリクラータ」、英名を「Capeplumbago」といいます。
「プルンバーゴ」はラテン語で「鉛」を意味する「プルンバム」に由来しています。この植物の一種が鉛中毒の解毒に効果があったことによるといいます。また、「ルリマツリは」しばしば「瑠璃茉莉」と漢字で書かれることもありますが、すべて同じ種族の植物です。和名の由来は、ジャスミンの一種である「茉莉花(マツリカ)」に似た青い花を咲かせることからきています。
「茉莉花」はジャスミンティーに使われるジャスミンの一種「アラビア・ジャスミン」の和名です。「ルリマツリ」にはジャスミンのような香りはありません。生息地は世界的に広く熱帯から寒帯まで分布しており、原産国の環境により乾燥や塩分に強い性質を持ちます。地中海沿岸や中央アジアの乾燥地、あるいは海岸にも多く生息しています。
現在では、熱帯から亜熱帯地方の庭園に広く植栽されており、日本でも全国的に植栽されている植物の一種です。近年では庭園型の欧風ガーデニングのほか、日本庭園や盆栽として植栽されることも多く、多彩な魅力を持つその姿形や初心者にも
管理しやすい育て方からから多くの人に親しまれています。主に鉢物として出回っておりフラワーショップやホームセンターから手軽に購入でき、切り花には不向きであるため市場に切り花として出回ることはほとんどありません。
ルリマツリの特徴
歴史についての文章でもあるように、「ルリマツリ」はイソマツ科プルンバゴ属常緑小低木です。半つる性の低木で本来は常緑性ですが、もともと温かい地域に生息している植物ですので、日本では冬の寒さで一気に葉が枯れ落ちてしまうことがほとんどです。反対に、真夏の直射日光や高温多湿の厳しい環境の中でも美しい満開姿を見ることができます。
日本では4月頃から鉢物として市場に出回り、開花時期は夏から秋が一般的です。主にブルー系の花を咲かせ、中には白の花を咲かせる株もあります。茎はしなやかな半つる状で、支柱等があれば高さは最大で2.4メートルにもなります。成長すると枝先に柄のない花が房状に均等につき、花径2センチほどの淡い青色の花をたくさんつけることで知られています。
花弁の形状はロウト状(筒状)で、花弁の先が5つに裂け、横に開花します。葉は長い楕円形でしなやかな質感と光沢があり、互い違いに生えていくのが特徴です。葉の先端は丸く、縁は波打つような形状になっています。花の後にできる実はさく果といい、熟すると下部が裂け、種子が散布される果実です。
これらは腺毛から出る粘液によって「ひっつきむし」となり他の動植物によって散布されることで、開花時期が終わるとしばしばやっかいなのも特徴の一つです。同じルリマツリ属の仲間に白い小さな花をつける「セイロンマツリ」(別名「インドマツリ」)や赤い花をつける「ルリマツリモドキ」と呼ばれるものもあります。
「〇〇マツリ」とつく植物には他にも、ジャスミンに似た芳香を放つ「ニオイバンマツリ(匂蕃茉莉)」と呼ばれるものもあります。その香りと白から紫への花色の変化で「ルリマツリ」と同様に人気があります。
-

-
ヤマユリの育て方
ヤマユリは、ユリ科、ユリ属になります。和名は、ヤマユリ(山百合)、その他の名前は、エイザンユリ、ヨシノユリ、ハコネユリ、...
-

-
キングサリの育て方
キングサリの科名は、マメ科 / 属名は、キングサリ属です。キングサリは、ヨーロッパでは古くから知られた植物でした。古代ロ...
-

-
ストケシアの育て方
この花は被子植物門、双子葉植物綱、キク亜目、キク目、キク科になります。タンポポ亜科になるのでタンポポに近い植物であること...
-

-
家庭菜園の栽培、野菜の育て方、野菜の種まき
家庭菜園ではプチトマトやゴーヤなど育てやすい野菜を育てるのが人気です。ですが、冬野菜でもある大根の栽培でも、手軽にするこ...
-

-
リナム・グランディフロムルの育て方
リナム・グランディフロムルは、アマ科アマ(リナム)属の植物です。リナム属はロシアのカフカス地方から中東にかけての地域が生...
-

-
ペラルゴニウムの育て方
和名においてアオイと入っていますがアオイの仲間ではありません。フクロソウ科、テンジクアオイ属とされています。よく知られて...
-

-
エクメアの育て方
エクメアはパイナップル科のサンゴアナナス属に属します。原産はブラジルやベネズエラ、ペルーなどの熱帯アメリカに182種が分...
-

-
ドクダミの育て方
ドクダミは、ドクダミ科ドクダミ族の多年草であり、ギョウセイソウやジゴクソバ、ドクダメとも呼ばれています。
-

-
シモツケの育て方
シモツケ/学名:Spiraea japonica/和名:シモツケ、下野/バラ科・シモツケ属、シモツケ属は約70種が北半球...
-

-
ヘレボルス・フェチダスの育て方
特徴としてはキンポウゲ科、クリスマスローズ属、ヘルボルス族に該当するとされています。この花の特徴としてあるのは有茎種であ...




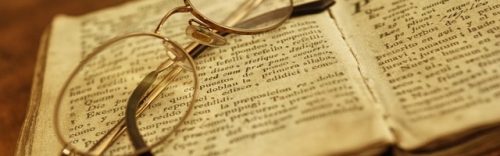





「ルリマツリ」は、南アフリカ、オセアニア原産のイソマツ科プルンバゴ属常緑小低木です。半つる性の熱帯植物であり別名「プルンバーゴ(正式名称=プルンバーゴ・アウリクラータ)」とも呼ばれ、学名を「プルンバーゴ・アウリクラータ」、英名を「Capeplumbago」といいます。「プルンバーゴ」はラテン語で「鉛」を意味する「プルンバム」に由来しています。