マルバタケブキの育て方

育てる環境について
マルバタケブキは寒冷な気候で育てるのが理想的です。自生している尾瀬の湿原のように、長年にわたり群生している場合には、大きく深く広く根が張っていますので、日当たりの良好な環境でも生育します。しかし根が弱いうちは、日陰で生育することが多く、山岳地帯や高原では、樹高の高い木の下で生息することが多いのも特徴です。
基本的に湿った環境を好みます。湿潤な気候であれば、昼間の日差しで暑くなっても大丈夫です。自宅で栽培するときは、鉢植えやプランターの場合と、庭に地植えさせるのとで対応が変わります。鉢植えやプランターの場合は、保水性を高めるように配慮しましょう。園芸用の水苔やピートモスを、たっぷりと土と混ぜ合わせておきます。
水やりして、水苔やピートモスが膨らむくらいにしましょう。水分が多ければ多いほど、育て方は簡単になります。ただし睡蓮鉢などのように、水だけで栽培すると、かえって弱ってしまうことがあります。適度な土の存在が不可欠だと言えます。庭に地植えする場合は、湿潤な土壌になるように調整しましょう。
ただし日陰にすることが可能であれば、それほど湿度にこだわらなくても大丈夫です。鉢植えやプランターは土そのものの量が限られているため、保水量も限られてしまいます。限られた保水量を有効活用するために、水苔などの保水性を利用します。
庭土の場合は、土の量が多く、自然な雨水だけでも潤いやすいのがポイントです。地上にしている場合は、晴天が続いて土の表面が乾燥してきたら、たっぷりと水やりすれば、しっかりと育ちます。保水量は土の量そのもので左右されることを覚えておくと、育て方は簡単に感じられます。
種付けや水やり、肥料について
マルバタケブキは多年草ですから、一度、植えてしまえば、自然に繁殖していきます。鉢植えやプランターで栽培している場合は、その年に生育した茎を、冬に刈り取っておくと良いでしょう。冬に茎を刈り取っておくことで、春の発芽を促進させられます。春に新しい茎が伸びてきて、伸びた茎に葉の新芽が出てきます。
根生葉ですから、土の中から茎が生えてくるようなイメージで生育します。鉢植えやプランターで栽培している場合は、春にたっぷりと水やりを行いましょう。夏の開花の前に、しっかりと水やりしておくことがポイントです。茎の高さが低いうちは、日陰で栽培するのが適切です。鉢植えやプランターは、日陰に設置します。
地植えにしている場合は、梅雨入り前に夏日が続くようであれば、日陰を設置すると安全です。日陰は園芸用の、わらぶき傘などで大丈夫です。日陰を作れる庭木が植えてあれば問題ありません。野生に自生しているときと違って、住宅の庭に地植えしているときは、土壌の質に注目しましょう。住宅用に土壌改良が行われて、排水性が良くなっていることが多いからです。
マルバタケブキを植えた場所だけに限定して、茎の根元部分に水苔を被せるように置くことで、部分的に保水性を備えさせることができます。夏の花を楽しみたいときは、冬のうちに油粕を地表面に撒いておくと良いでしょう。緩効性の肥料のほうが、高山植物類には最適です。花が咲いている期間であれば、即効性の液体肥料が良いでしょう。追肥は冬になってからで大丈夫です。
増やし方や害虫について
マルバタケブキは多年草ですから、湿度が適切な土壌さえ維持できていれば、自然に増えていきます。自分で増やしたいときは、挿し木にします。挿し木は、茎で切ってから、土に挿す方法です。茎の切り口から発根して、根付いていきます。マルバタケブキは病害虫に強いので、根付いてしまえば育て方は簡単です。
発根を早めたいときは、市販の発根促進剤を使用すると良いでしょう。土の中に含まれている微生物による菌の影響を受けさせないために、高温殺菌消毒してある赤玉土を使用すると、挿し木の成功率は高くなります。庭の日陰であれば、庭土に直接挿し木をしても、発根することがあります。
他の庭木からカイガラムシやハマキムシが付着することがありますので、通気性は確保するようにしましょう。害虫というよりも、自然に生息している蝶や蛾がマルバタケブキの葉を、コガネムシの幼虫が根や茎の株元を食べることがあります。ネズミなどの害獣は、茎や葉に含まれている毒性が危険なので食べません。
コウチュウ目コガネムシ科の昆虫は、毒性を気にせずに寄ってくることがあります。腐葉土の下に生息する昆虫類にとっては、保水性の高い土壌は生育しやすい環境でもあるため、葉に虫食いが多く見られるようになったら、殺虫剤を散布すると良いでしょう。
殺虫剤は濃度が薄いタイプでも効き目が現れます。鉢植えやプランターで、室内で栽培している場合は、他の観葉植物からのカイガラムシに注意しましょう。丸い葉を、濡れた雑巾やキッチンペーパーで両面を拭き掃除すると、カイガラムシの被害は予防できます。
マルバタケブキの歴史
マルバタケブキはキク科メタカラコウ属の植物です。原産が日本です。漢字による表記は、丸葉岳蕗です。生息地は日本と中国に分布しています。日本では、東北地方と中部地方に多く自生しています。どちらかというと山岳地方に多く群生しています。尾瀬の湿原に自生している群生が有名です。
マルバタケブキは山野草に分類できることもあり、尾瀬のハイキングコースなどでも有名です。ただし毒をもっている植物です。有名な山野草のひとつですが、食用にはできません。山菜として食用にするのは厳禁な植物です。マルバタケブキは、古くより、鹿が食べない植物として知られてきました。
鹿は山林で、多くの山野草を食べてしまいますが、毒の成分を持っている植物は一切食べません。鹿が食べない山野草であることから、鹿が多く生息している山岳地帯では、逆にマルバタケブキが大繁殖してしまっているケースもあります。日本では、昭和の頃に、鹿による食害の影響で、多くの高山植物が減少してしまった時期があります。
食害で高山植物が激減してしまった地域として知られているのが南アルプスの山岳地帯です。現在では、鹿による食害の心配のないマルバタケブキが、群生しているのが見かけられます。マルバチョウリョウソウという別名もあります。チョウリョウソウという植物に似ていることと、丸い葉をしていることかせ名づけられています。チョウリョウとは古代中国の武将で軍師の張良が名前の由来になっています。
マルバタケブキの特徴
キク科のマルバタケブキは多年草です。茎の高さは、40センチメートル以上あり、大きく成長すると120センチメートルから140センチメートルほどに達します。丸くて大きな葉が特徴です。やや楕円形になっている葉も多いです。葉は根生葉であり、長い柄が特徴です。葉の縁は、ギザギザの鋸葉のようになりますが、柔らかいです。
夏になると黄色い花が咲きます。黄色い花は、ややオレンジ色がかって見えることがあります。夏の行楽シーズンに、高原や山岳で見かけられますので、高山植物として撮影されることも多いです。尾瀬の湿原の群生が有名です。花の特徴は、黄色い頭花です。茎の上部で、散房状に頭花が複数個つくのがスタイルです。
頭花は、長さが10センチメートル前後です。草丈が100センチメートルほどで、黄色い花が10センチメートル前後の植物としては、トウゲブキにも似ています。トウゲブキとの決定的な違いは、苞が存在しないことが挙げられます。苞というのは、つぼみを包む葉のことです。花あるいは花序の基部に存在していて、つぼみを包んでいる葉です。
苞が存在しないことで、明確に冠毛が観察できます。あらわになっている状態の冠毛は、赤い褐色の色合いをしており、黄色い花を美しく際立たせています。動物に食べられてしまわないように、自分の身を守るために毒を備えているのも特徴です。群生して繁殖すると、人が立ち入ることが困難になってしまうほどの、混み合った状態になります。
-

-
ザクロの育て方
ザクロの歴史は非常に古く、古代ギリシャの医学書では、すでにザクロの効能が書かれていました。また、パピルスに記されているエ...
-

-
ライラックの育て方
ライラックの特徴としてあるのはモクセイ科ハシドイ属の花となります。北海道で見られる事が多いことでもわかるように耐寒性があ...
-

-
野生ギクの育て方
特徴としてはキク目、キク科の植物になります。のじぎくと呼ばれるキクに関しては非常によく見られるタイプかも知れません。こち...
-

-
ディーフェンバキアの育て方
ディーフェンバキアは原産と生息地は熱帯アメリカで、名前の由来はドイツの植物学者であるエルンスト・ディッフェンバッハです。...
-

-
ヒメヒオウギの育て方
現在の日本国内で「ヒメヒオウギ」と呼ばれる植物は、正式名称を「ヒメヒオウギズイセン」と言います。漢字では姫の檜の扇と書き...
-

-
リンゴの育て方
リンゴの特徴として、種類はバラ目、バラ科、サクラ亜科になります。確かに花を見るとサクラとよく似ています。可愛らしい小さい...
-

-
シェフレラの育て方
シェフレラは台湾や中国南部を原産としたウコギ科の常緑低木です。手の平を広げたような可愛らしい葉が密集して育ちます。ドイツ...
-

-
チャボリンドウの育て方
チャボリンドウは、アルプスやピレネー山脈の草地原産の常緑の多年草です。チャボといえば、茶色を基調とした鶏の色をイメージす...
-

-
ガザニア・リゲンスの育て方
ガザニア・リゲンスの特徴について言及していきます。まずは花言葉から書きます。花言葉は「あなたを誇りに思う」です。植物の分...
-

-
ナンテンの育て方
ナンテンはメギ科ナンテン属の常緑低木です。原産は日本、中国、東南アジアです。中国から日本へ古くに渡来し、西日本を中心に広...




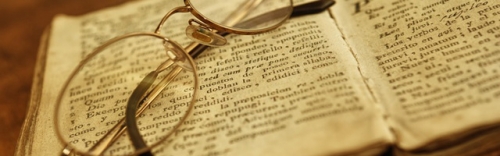





マルバタケブキはキク科メタカラコウ属の植物です。原産が日本です。漢字による表記は、丸葉岳蕗です。生息地は日本と中国に分布しています。日本では、東北地方と中部地方に多く自生しています。どちらかというと山岳地方に多く群生しています。尾瀬の湿原に自生している群生が有名です。