ヒナガヤツリの育て方

育てる環境について
ヒナガヤツリは湿気の多い土壌であれば、どこでも自生できる強い繁殖力を備えています。野生で自生させるのではなく、自分で栽培する場合は、保水性の高い土壌にしましょう。水田や沼の土が参考になります。排水性が悪いくらいの、保水性の高さがポイントです。地下茎がありませんので、水草のように栽培することも可能です。
鉢植えやプランターで栽培するのであれば、水苔を土に混ぜて、保水性を高めるようにしましょう。ピートモスを混ぜるのも良いでしょう。水草のように栽培するときは、睡蓮鉢が参考になります。メダカなどの小さな魚と共生させることも可能です。睡蓮鉢を使用して、メダカと共生させれば、水質を衛生的に維持管理しやすいです。
基本的に、湿度が高ければ高いほど、育て方が簡単です。注意したいのは、保水性が高くなることで、土の表面に虫が発生しやすくなってしまうことです。野生の自然環境と異なり、自宅の鉢植えやプランターで栽培していると、ボウフラが育つこともあります。過剰な湿度の状態は、ヒナガヤツリにとっては好ましい状態なのですが、蚊が発生しやすくなります。
睡蓮鉢にメダカと共生させていると、メダカがボウフラを捕食してくれますので、蚊の発生を抑制できます。ボウフラが育ちにくい睡蓮鉢であれば、水質も比較的きれいなままで維持されますので、悪臭を放つこともありません。単独で栽培しようとするよりも、他の水草や、メダカと共生させたほうが、衛生的に育てられます。
種付けや水やり、肥料について
ヒナガヤツリの花が咲き終わったら、果実を収穫しておくことで、翌年の春に発芽させることが可能です。もともと繁殖能力が高く、生命力も旺盛な植物ですから、自然に果実が拡散されて繁殖することが多いです。ただし一年草ですから、必ずしも毎年同じ場所から発芽するとは限りません。
自然の雨水に流されてしまう量も多いため、大発生する年と、あまり見かけない年があるなどの、生育状態の差が生じることもあります。ただし、一度生育した場所には、果実が拡散している状態ですから、たとえ繁殖している量が減ったとしても、湿度の条件が好転すれば、たちまち大繁殖します。花が咲き、果実がつきますが、肥料は与えなくても大丈夫です。
一年草ですから、枯れた草が腐葉土として、さらに土の栄養分になっていきます。保水性の高い土壌では、枯れた後に自然な腐葉土になっていきますので、天然の肥料としての機能が働くことになります。注意したいのは、睡蓮鉢などで水草のような育て方をしているときです。睡蓮鉢は水深がありますので、花が咲いた後の果実は、底に沈んでしまいます。
果実は軽量なので、しばらく水面に浮いていますし、浮いている間に風によって吹き飛ばされてしまうことも多いです。基本的に、拡散されやすい果実です。睡蓮鉢から翌年に発芽するというよりも、睡蓮鉢の近くの地面で発芽しやすい傾向にあります。地下茎がありませんから、地面で発芽したものを、そのまま睡蓮鉢に入れて栽培すると良いでしょう。
増やし方や害虫について
ヒナガヤツリは、一度生息した場所には、果実が自然に拡散されますので、自然に繁殖していきます。ただし土壌が乾燥気味になると、発芽が少なめになります。拡散された果実が、種子となり、翌年の春に発芽します。土壌が乾燥気味になって、発芽しなかった種子は、土の中に蓄積されていきます。水辺であれば、水に流されます。
自然の雨水で、流されてしまうことも多いです。それでも、一度生育した場所では、翌年も発芽するようになります。ヒナガヤツリを狙って害虫が寄ってくることは、あまりありません。ただし、水田や沼のように水量が豊富な環境では、ボウフラが発生します。ボウフラを捕食してくれるメダカなどの水中生物がいれば、ボウフラは少なくなります。
自宅で栽培するときは、睡蓮鉢を使用して、メダカも飼育することでボウフラ予防ができますので、育て方は簡単です。可憐な姿をしていますので、睡蓮鉢の彩りとしても素敵な存在感を放つことができます。睡蓮鉢のような水のある環境ではなく、土を主体とした環境で栽培する場合は、あらゆる害虫を考慮したほうが良いでしょう。なぜならば、保水性の高い土壌は、虫そのものが好む環境だからです。特に注意したいのは蛾の幼虫です。
蛾の幼虫のなかには、土の中で成長するタイプがいるからです。表面的には害虫が発生していないように見えても、蛾の幼虫が夜に地表に出てきて、ヒナガヤツリを餌にしてしまうことがあります。朝になると蛾の幼虫は土の中に戻りますので、どの虫が食べたのか分かりにくくなります。殺虫剤を地表に散布することで、駆除することは可能です。
ヒナガヤツリの歴史
ヒナガヤツリは、カヤツリグサ科カヤツリグサ属の植物です。ヒナガヤツリの原産地は北アメリカですが、主な生息地はオーストラリアや東アジアに分布しています。太平洋側に面している地域で、温暖な気候の地域が自生しやすい環境です。日本では本州の南部を中心に生息地が分布しています。東アジアの稲作地帯での繁殖が確認されています。
湿った環境を好みますので、田園地帯や湖沼の周辺を好みます。稲作が行われている田園地帯では、あぜ道を中心に広まりました。稲作に適した温暖で湿潤な自然環境に適応しやすいため、稲作の技術が伝わるのと同じ頃には、日本にも上陸していたと言われています。稲作の伝来は弥生時代ですので、日本では古くから親しまれている植物のひとつです。
稲作は東アジアから九州地方へ伝来しました。日本国内で稲作が広まり、田園地帯が増えるにしたがって、生息地も東へと広がっていきました。寒冷な気候には適応しにくく、本州では関東地方よりも西で生息しています。稲作の技術は、稲の品種改良に伴って東北地方でも栽培されるようになりましたが、
東北地方よりも北の地域には、ヒナガヤツリは広まりませんでした。現在では稲作は北海道でも可能ですが、ヒナガヤツリが生息している田園地帯は、関東地方よりも西の地域です。四国と九州では、田園地帯に限らず、川原や湿地帯などに多く生息しています。稲作のための溜池が作られている地域では、溜池の周辺に自生するようになりました。
ヒナガヤツリの特徴
ヒナガヤツリは一年草です。湿地帯を好む植物です。水田の中にも自生できます。地下茎がないことが最大の特徴です。地下茎がないので、水田の中や、沼のほとりなどでも自在に繁殖できます。地下茎がないので、茎からたくさんの枝を出して伸びていきます。茎の根元部分から、どんどん枝が放射される形状をしています。
茎は柔らかく、田園で繁殖しても除去することが簡単です。地下茎がありませんので、水の流れにのって下流へと流されることも多いです。夏から秋にかけて、花が咲きます。花の色は白く見えることがありますが、全体的に淡い緑色をしています。ヒナガヤツリは、葉も茎も枝も花も、全体的に淡い緑色をしているのが特徴です。
花の先端からは、小穂が成長します。小穂は、複数が集まって固まるような形状を構成します。小穂は楕円形です。かなり扁平形で、鱗片が付着しています。鱗片は、先端がとがっていますので、複数が集まって固まるような形状を構成することで、ギザギザして見えます。草丈は25センチメートルほどまで伸びますが、地下茎がありませんので横方向へと伸びる性質があります。
横方向へ伸びていきますので、地面や水面を這うように成長します。水田に自生すると、足首ほどの高さが限界であることが多く、踏まれやすい植物とも言えます。花が咲き終わると、果実がつきます。とても小さな果実で、卵のような形状です。卵形の果実の上の部分は、三方向に分裂します。果実は拡散し、翌年の春に発芽し、繁殖していきます。
-

-
レモンバームの育て方
レモンバームとはメリッサとも呼ばれるハーブの一種です。南ヨーロッパが原産で、地中海近くが生息地とされています。レモンバー...
-

-
チューリップの育て方
チューリップといえば、オランダというイメージがありますが、実はオランダが原産国ではありません。チューリップは、トルコから...
-

-
ラディッシュの育て方
ラディッシュとは、ヨーロッパ原産の、アブラナ科ダイコン属に分類される野菜です。ダイコンの中ではもっとも小さく、そして短期...
-

-
アロエの育て方
日本でも薬草として人気のあるアロエはアフリカ大陸南部からマダガスカルが原産地とされており、現在ではアメリカのテキサス州や...
-

-
植物を栽培するに当たって注意しなければならない事。
何かの植物を栽培したり、種から育てたりするのはとても楽しい事です。それは娯楽や趣味にもなりますし、その結果できた物を収穫...
-

-
ノウゼンカズラの育て方
ノウゼンカズラの歴史は古く、中国の中・南部が原産の生息地です。日本に入ってきたのは平安時代で、この頃には薬用植物として使...
-

-
セイヨウムラサキの育て方
セイヨウムラサキの特徴について書いていきます。日本を本来の生息地とするムラサキと比較してみると、茎に特徴があります。茎が...
-

-
ナゴランの育て方
この植物の歴史ついて書いていきますが、まずは名前の由来についてです。ナゴランの名前は原産地でもある沖縄の「ナゴ」に由来し...
-

-
小松菜の育て方
小松菜の原産地は、南ヨーロッパ地中海沿岸と言われています。中国などを経て江戸時代の頃から小松川周辺から栽培が始まり、以降...
-

-
ガザニアの育て方
ガザニアはキク科ガザニア属で勲章菊という別名を持っています。ガザニアという名前はギリシャ人が語源とされており、ラテン語の...




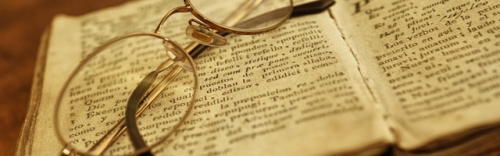





ヒナガヤツリは、カヤツリグサ科カヤツリグサ属の植物です。ヒナガヤツリの原産地は北アメリカですが、主な生息地はオーストラリアや東アジアに分布しています。太平洋側に面している地域で、温暖な気候の地域が自生しやすい環境です。日本では本州の南部を中心に生息地が分布しています。