ザゼンソウの育て方

育てる環境について
座禅草の分布は、カナダのノバスコシア州とケベック州南部からアメリカ合衆国ミネソタ州の北アメリカ東部にかけてから、南限はノースカロライナ州とテネシー州、また北東シベリア、中国北東部および日本等の北東アジアまで広がっています。日本国内における南限は、滋賀県高島市となっています。
伊那山地の守屋山を代表する花の一つとして『花の百名山』に記載されており、『新・花の百名山』では北信五岳を代表する花の一つとしてされています。また長野県諏訪市の有賀峠付近には「ザゼンソウの里公園」があります。兵庫県美方郡香美町においては座禅層の開花時期に合わせて「ザゼンソウ祭り」が開催されている他、
様々な群落や公園が存在しています。山地の湿地が栽培適地なので、それにあった栽培環境を用意してあげると良いでしょう。座禅草の高さは10から20センチ程度まで生長します。仏炎苞と呼ばれる茶色の部分には、内側に無数につく黄色い部分があってこれが花です。葉は花が終わる頃から伸び始めて、だいたい長さ40センチくらいにまで伸びていきます。
庭植えする時には、明るい半日陰の湿った場所に植えると良いでしょう。なるべく湿気のある川辺、湧水の上、池の周囲で、なるべく涼しい場所が理想的です。鉢植えする場合には、明るい半日陰で、できれば根は水の中にいるようにすると良いでしょう。大きい容器に水を張って鉢の半分程が常に浸る状態にするのが良いでしょう。
種付けや水やり、肥料について
育て方としては、種子からでも可能です。種子はよく水洗いしてから乾かさずに播いて、そのまま乾燥させないようにします。開花するまで数年かかります。ある程度育ってきたら植え替えます。鉢植えする場合には、6から8号の大き目の深い鉢の底部に、くず炭を少し混ぜた5から10ミリの大き目の赤玉土を敷きます。
その後、上から赤玉土、桐生砂に腐葉土を2~3割混ぜた用土で入れて、排水をよくした状態で植えつけを行います。水鉢や瓶などに直接植えても良いですし、植えた鉢ごとを水に入れ、用土の表面近くまで浸しておくのでも構いません。いずれにせよ風通しの良いところで管理するようにしましょう。
水に浸けている場合は水温が上がらないように、3日に1度くらいの頻度で水の入れ替えをします。湿地に生える植物なので、それに近い環境で育てるように心がけると良いでしょう。肥料を好みますので、有機質の固形肥を施します。花が咲き終わった時点で、油かすや緩効性肥料を与えてあげてください。その後は月に1度以上の置肥を行います。
ただし夏は肥料を与えないほうがよいでしょう。涼しくなってきたら、葉の枯れる12月までに株に充分な栄養を与えるようにします。花が咲き終わるまでは追肥はしないでください。また日に当てるようにすることで、花よりも葉が伸び過ぎてしまうことを防ぎます。特に9月中旬からはよく日に当てるようにしてください。水に浸けている場合、冬に凍らないのであればそのままでも大丈夫です。凍結する地方においては、水を捨ててください。
増やし方や害虫について
増やし方としては、種から育てる他に株分けで増殖することもできます。病気や害虫については、あまり心配することはありません。適切な水の入れ替えや、風通しを良くするなど、基本的な注意をしていれば、特に問題になることはないでしょう。ただし、種子については、野ネズミによって食害されることがあります。
自然界においては、その一部が野ネズミの貯食行為によって運ばれ、種子はそれによって散布され、被食を逃れて発芽することが出来という仕組みになっています。寒さには強い耐寒性の植物なので、特に防寒する必要はありません。とはいえ、強い霜や凍結、あるいは乾燥は避けるようにしてください。
花が早く見たい場合にも、株分けを行うと良いでしょう。早春頃に根を洗い流して、必ず分けた株に根が付くようにハサミなどで切断し、新しい用土に植え替えます。ハサミ等の刃物は、切断する前に火等を使って、殺菌しておくようにしてみましょう。植え替えのタイミングとしては大体2から3年ごとの早春に、赤玉土のみを使って、深めの鉢に植えて腰水にするようにします。
その際、鉢底に炭を数個入れておくと、腐敗を予防することができるようになります。もし地植えするという場合には、落葉樹に囲まれた浅い池や、あるいは人工的に作った湿地などに植えるようにすると良いでしょう。その際には、地下水を汲み上げてかけ流せれば理想的な環境となります。名前の由来でもある、座禅を組んだ達磨大師にも見える花の姿をぜひ楽しんでみてください。
ザゼンソウの歴史
ザゼンソウは、ザゼンソウ属サトイモ科の多年草の草木です。学名はSymplocarpusfoetidusで、漢字では座禅草と書きます。北海道や本州中部以北の山地や湿地を生息地としています。座禅草の花の形はミズバショウに似ています。仏像によく見られる光背のような、仏焔苞という紫褐色のラッパ状の大きな苞が、まるで僧侶が座禅を組む姿に見えることから、
座禅草と呼ばれるようになったと言われています。同じように、花を達磨大師の座禅する姿に見立てて、達磨草と呼ぶこともあります。開花する際には、肉穂花序で発熱が起こります。これによって周囲の氷雪を溶かし、いち早く顔を出すことが特徴で、その場面がよく写真の題材として使われることがあります。
またザゼンソウが放つ特有の腐敗臭により、この寒いには数の少ない昆虫を独占的に呼び寄せることで、受粉の確率を上げるということをしています。ただこの臭いは、人間側からすると酷い悪臭であることから、アメリカでは「スカンクキャベツ」などと呼ばれています。根茎部分には毒があり、
そこに含まれているシュウ酸カリウムによって下痢、嘔吐、不整脈、呼吸麻痺等の症状を引き起こす場合があります。しかし有効活用することも可能で、19世紀米国の薬局方では、ドラコンティウムという名で呼吸器系疾患、神経症、リューマチ、浮腫の治療にも用いられていました。北アメリカとヨーロッパでは、北米先住民はザゼンソウをよく薬草、調味料、魔術的なお守りとして用いられていました。
ザゼンソウの特徴
ザゼンソウは原産は日本やアジア等で、冷帯、および温帯山岳地の湿地に分布していますが、その開花時期は1月下旬から3月中旬頃になります。日本で見られるものはザゼンソウ、ヒメザゼンソウとナベクラザゼンソウの3種で、開花する際に肉穂花序で発熱が起こって約25度まで上昇します。
発熱する部分はラグビーボール状の花のみで、花びらや葉については発熱しません。温度は、気温が大きく変化したとしても20℃程度の一定の温度に保たれています。早朝の気温がマイナス10℃でも花は20℃程度に発熱します。この発熱現象は、開花している時期に1週間くらい続きます。雪が残る群落地に行ってみると、
発熱することによって周りの雪が溶け、雪の中で穴を開けて顔を出している座禅草を見つけることもがきます。この発熱細胞には豊富にミトコンドリアが含まれていることが明らかになっているのですが、その発熱における詳細な分子メカニズムについては、現在のところ解明されていません。動物における発熱には、脱共役タンパク質が関係していることがわかっていますが、
このタンパク質は、発熱しない植物にも幅広く存在しているため、ザゼンソウの発熱に関与しているかは現時点では不明です。発熱する植物は、この他にもいくつかあります。その1つはハスで、初夏に開花した際に、花托という花の部分が発熱します。もう1つはヒトデカズラで、お風呂の温度と同じくらいの、およそ40度にまで上昇します。植物に触るとはっきり発熱していることを感じることが出来るほどです。
-

-
家庭菜園の栽培、野菜の育て方、野菜の種まき
家庭菜園ではプチトマトやゴーヤなど育てやすい野菜を育てるのが人気です。ですが、冬野菜でもある大根の栽培でも、手軽にするこ...
-

-
ナゴランの育て方
この植物の歴史ついて書いていきますが、まずは名前の由来についてです。ナゴランの名前は原産地でもある沖縄の「ナゴ」に由来し...
-

-
グミの仲間の育て方について
グミと言うとお菓子を連想する人は多いものですが、お菓子のグミと言うのは、グミの仲間となるものを原料として、果汁を搾りだし...
-

-
唐辛子の育て方
中南米が原産地の唐辛子ですが、メキシコでは数千年も前から食用として利用されており栽培も盛んに行われていました。原産地でも...
-

-
オヤマリンドウの育て方
オヤマリンドウの特徴は名前の由来にもなっておりますように、ある程度標高の高い亜高山や高山に咲くことが大きな特徴です。そし...
-

-
タッカ・シャントリエリの育て方
原産地はインドや東南アジアで、タシロイモ科タシロイモ属の植物です。和名はクロバナタシロイモで漢字では黒花田代芋と書きます...
-

-
小かぶの育て方
原産地を示す説はアジア系とヨーロッパ系に分かれており定かにはなっておりません。諸説ある中でも地中海沿岸と西アジアのアフガ...
-

-
お洒落なハーブの育て方
お洒落なハーブを自分で育てることが素敵だと思いませんか?最近はお家でハーブを育てている人が多くなっています。ハーブと聞く...
-

-
ナツズイセンの育て方
このナツズイセンですが、面白いのは植物の系統ではヒガンバナ科のヒガンバナ属ということで、彼岸花の親戚でもあります。また別...
-

-
ゲッケイジュの育て方
英語ではローレル、フランス語ではローリエ、日本語では月桂樹と呼ばれています。クスノキ科の常緑高木植物で地中海沿岸の原産と...




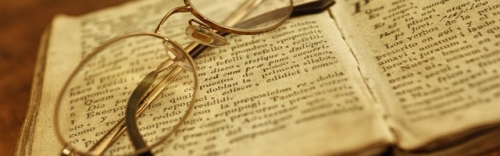





ザゼンソウは、ザゼンソウ属サトイモ科の多年草の草木です。学名はSymplocarpusfoetidusで、漢字では座禅草と書きます。北海道や本州中部以北の山地や湿地を生息地としています。座禅草の花の形はミズバショウに似ています。