クレソン(オランダガラシ)の育て方

育てる環境について
生息地は、ヨーロッパをはじめ、北アメリカ、南アメリカ、日本を含むアジア、オセアニアとなっています。水耕栽培に向いており、特に弱アルカリ性の水を利用すると非常に育ちが良くなります。耐寒性は強く冷涼な気候を好みます。夏場になると水温が上がり過ぎて弱ってしまうことがあります。
日本では品種はありませんが、イギリスではいくつか品種が存在しています。自家栽培ベランダなどで水耕栽培したり、プランターを使って育てることもできます。水耕栽培の場合、水没したままの葉は枯れることがあります。しかしそうなってしまった場合でも、水面より上の部分が健全であれば問題はありません。
夏は半日陰で水温が高くならないところに置いておくと、茎の節から発根してきます。暖かいところに置くと冬でも芽が伸びてきます。食品にする場合については、衛生上の観点から時々水を換えるようにします。湿った畑等においても簡単に育っていきます。庭植えの場合、湿った庭で水やりを頻繁にすれば成長が早くなりきれいなクレソンが食べられるようになります。
高温には弱いので、夏場の暑い時期には遮光するとよく育つようになります。有機物を多く含む、肥えた土であれば無肥料であっても栽培できます。また常に湿り気のある畑でも栽培できます。用土の例として、畑土単用、あるいは赤玉土:3、黒土:3、川砂:1、あるいは赤玉土:3、腐葉土:1,パーライト:1,川砂1で混ぜたものを使います。
種付けや水やり、肥料について
育て方としては、クレソンはタネから増やすことも出来ます。しかし水差しでもすぐに根が出てくるほどよく根付くため、用土を入れた鉢に直接挿し芽をして、それをそのまま水を入れた容器に沈めるだけで発根させることができます。もともと水辺に住む植物なので、水耕栽培でも簡単に育てることが可能なのですが、
この場合基本的には、新鮮な水が供給される流水が最も適しています。他にも方法としてハイドロカルチャーや水を張った容器でも、十分栽培することもできます。あるいはプラスチックのざるやバスケットなどに砂を入れて株を植え付け、水を張った他の容器にバスケットを浸す方法でも良いです。
容器についてはボールや発泡スチロールのトロ箱などを利用すると良いでしょう。水は汚れ具合を観察しながら、時々入れ替えるようにします。特に夏場においては傷みやすいのでこまめに替えた方が良いでしょう。肥料も時々与えるようにします。夏は涼しくて、冬は暖かく、水温15~20℃程度の、水流のあるところがベストです。
他にもスイレン鉢に直接植え込むか、水を入れた容器に鉢を沈めて、栽培することも可能です。水量は鉢の縁がかぶるくらいが良いでしょう。この時クレソンの葉が水に浸らないように注意してください。プランターの場合には、
底穴を塞いで水を入れて、4号鉢に植えたものを3~4鉢沈めて育てるのが良いです。茂ってくると、中の鉢が見えなくなって、まるでプランターそのものに植え付けたように見えてきます。水場で育てる場合、水中で崩れにくく、水が濁らない水生植物用の土を使用するのが良いです。肥料肥料は、水に液肥を溶かし込んで与えます。
増やし方や害虫について
クレソンは摘めば摘むほど新芽の成長がよくなってきます。葉茎が増えてきて根本部分が不安定になったってきたら増し土をすると良いでしょう。やや密生させて柔らかく育てるとのも良いです。茶色になった古い根はむしり取っておくようにしてください。葉が小さくなったら根が混み合ってきた証拠です。白い根が少なくなった場合は全部抜き取り、
はじめから植え直し更新するようにしましょう。暑さに弱いので夏の直射日光には注意です。ベランダ等で栽培する場合には熱がこもってしまうことがあるので、十分に気をつけて管理する必要があります。夏の直射日光に当てすぎると枯れてしまう可能性があります。水の管理としては、水耕栽培の水は多少汚くても育ちますが、
虫などが発生しますので、こまめに入れ替えましょう。クレソンは強健で比較的病気は少ないです。しかし害虫には狙われやすいので、十分に気をつける必要があります。クレソンの場合は、病害よりも虫の害が多いというのが実態です。例えばアブラムシやコナガ、ハムシ、カブラバチ、カタツムリ等の害虫が発生します。
ベランダや室内であれば、ある程度害虫を防げますが、心配であればカバー等をかけておくと良いでしょう。もし、発見した場合には逐次捕殺するようにしましょう。大量発生してしまうと殺虫剤等で駆除する必要が出てきますので、食用に育てるのであれば、早期発見と逐次駆逐が大切です。他にはハダニ類は葉の裏側に寄生して葉の汁を吸います。
吸われた部分の色が抜けて白い斑点が生じます。その数が少ないときは気が付きにくいですが、多くなってくると白さが目立つようになります。被害が進行すると、葉色が悪くなり生育も悪くなってしまいます。これらは園芸用のでんぷんスプレーといった殺虫剤で駆除することが可能です。
またアオムシモンシロチョウ、アゲハチョウなどの幼虫にも注意してください。夏の始めに幼虫が葉っぱを食べ尽くしにかかりますので、適時に捕殺するようにしましょう。コナガアブラナ科野菜に寄生して葉を食べてきます。卵が葉に産みつけられるようになり、
ふ化した幼虫は葉にもぐって葉肉内の組織を内側から食べてきます。幼虫は淡黄色から緑色へと変化してくると大量の葉を食害します。ひどくなると葉脈だけが残る状態に。数が少ないうちからまめに手で駆除していきましょう。大量に発生しているような場合には躊躇わず、殺虫剤を利用します。
クレソン(オランダガラシ)の歴史
クレソンは、日本では和蘭芥子(オランダガラシ)や西洋ぜりと呼ばれています。英語ではウォータークレスといいます。水中または湿地に生育するアブラナ科の多年草です。古代ギリシア時代からの最古の薬用野菜として知られていました。ギリシャの哲学者で、医学の父や医聖、疫学の祖とも呼ばれているヒポクラテスが作った病院で、このクレソンが処方されていました。
ヒポクラテスは、クレソンの効能を刺激、去痰と著書に記しています。中国では肺病の排熱をさまし、咳止めなどに用いられています。また欧州では結核や体内腫瘍、貧血、壊血病などの民間療法や予防薬として用いられてきた。血液、組織中に存在する毒素を体外に出す解毒作用があるとされています。
実際に、薬理作用は多く、種子中に含まれるアリル‐イソチオアナートに強烈な刺激性があって、その抽出液が大腸菌を抑制します。さらにニコチンを分解するはたらきも知られています。クレソンの葉や茎にちょっぴり辛みがありますが、これは山葵や大根などと同じカラシ油配糖体のシニグリンという物質です。
この辛味が胃を刺激させて胃液の分泌を促進し、食欲を増進させる効果があります。酵素の働きで抗菌性の強い成分となります。クレソンは栄養価も高く、カルシウム、リン、鉄分などの無機質やビタミンC、カロチンが豊富に含まれています。原産地は欧州で、現在は世界各地に帰化植物として野性化しています。日本には明治3-4年ころ輸入移植し野性化した帰化植物です。
クレソン(オランダガラシ)の特徴
クレソンは抽水・沈水植物で、繁殖力は極めて旺盛です。切った茎は水に入れておけば簡単に発根するうえ、生長が非常に速いです。一般に清流にしか育たないという俗説は誤りです。汚水の中でも十分生育させることが可能です。日本でも川や溝に野生化・雑草化しているのがよく見られます。葉は奇数羽状複葉です。
5月になると、茎の先に白い小花を咲かせます。霜にあたったクレソンは、葉が赤黒くなるが味は甘みが増すのですが、これがイスラエルの過ぎ越しの祭りの料理に使われたとされています。欧州の中部から南部一円で野生化している多年生植物葉は互生し、卵形または楕円形の小さな葉が集まっています。茎は低くはい、草丈は50センチほどに伸び、柔らかいです。
ほかのアブラナ科植物と同じく、辛味のシニグリンという抗菌性の物質が含まれています。ラットによる動物実験では、日常的な摂食は血圧上昇抑制や、脂質代謝改善に有効であると言われています。ホウレンソウやルッコラなどと共に香味野菜として、サラダや若い茎と葉が肉料理の付け合せに等によく利用されます。
お浸し、ごま和え、天婦羅、漬物、味噌汁の具、鍋物などにもよく使われています。最近になるとスプラウトとしても利用されていることが多くなってきました。また様々なところでよく自生しているのですが、日本において最初に野生化したのは、東京上野のレストラン精養軒で料理に使われた茎の断片が、排水によって不忍池に流入したことにより根付いたと伝えられています。
-

-
植物の育て方について述べる
世の中に動物を家で飼っている人は多くいます。犬や猫、爬虫類などを飼って家族と同然の扱いをして、愛情深く飼育している場合が...
-

-
ウツボグサの育て方
中国北部〜朝鮮半島、日本列島が原産のシソ科の植物です。紫色の小さな花がポツポツと咲くのが特徴です。漢方医学では「夏枯草」...
-

-
エロディウムの仲間の育て方
フウロソウ科エロディウム属に属する品種なので、厳密には異なります。和名ではヒメフウロソウと呼ばれており、良く似た名前のヒ...
-

-
苺の種まきや苺の育て方や苺の栽培について
冬になると、苺がスーパーなどで店頭に並ぶため、苺の種まきは夏に行っていると思う人も居るかも知れませんが、ハウス栽培でなけ...
-

-
ヒヨドリジョウゴの育て方
ヒヨドリジョウゴの特徴は外観と有毒性が挙げられます。外観に関して、白い毛が生えています。現物を見た人や写真を見た人の中に...
-

-
ナンブイヌナズナの育て方
ナンブイヌナズナは日本の固有種です。つまり、日本にしか自生していない植物です。古くは大陸から入ってきたと考えられますが、...
-

-
カーネーションの育て方
母の日の贈り物の定番として、日本でも広く親しまれているカーネーションですが、その歴史は古くまでさかのぼります。もともとの...
-

-
ジンチョウゲの育て方
ジンチョウゲは、ジンチョウゲ科ジンチョウゲ属の植物で、漢字では沈丁花と書きます。学名はDaphne odoraで、Dap...
-

-
ヒマラヤスギの仲間の育て方
ヒマラヤスギはヒンドゥー教では、古来から聖なる樹として崇拝の対象とされてきました。ヒマラヤスギの集まる森のことをDaru...
-

-
ハナズオウの育て方
ハナズオウはジャケツイバラ科ハナズオウ属に分類される落葉低木です。ジャケツイバラ科はマメ科に似ているため、マメ科ジャケツ...




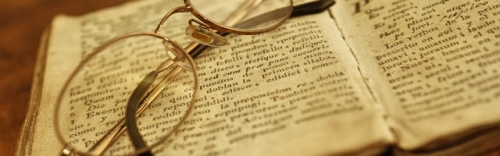





クレソンは、日本では和蘭芥子(オランダガラシ)や西洋ぜりと呼ばれています。英語ではウォータークレスといいます。水中または湿地に生育するアブラナ科の多年草です。古代ギリシア時代からの最古の薬用野菜として知られていました。