メロンの育て方

育てる環境について
メロンは園芸分野では実を食用とする野菜、「果菜」とされています。青果市場での取り扱いや、栄養学上の分類では果物や果実に分類されています。メロンにはいくつかの品種群があります。例えばヨーロッパ型のネット種やカンタロープ、小アジア型のウィンター種、それに東アジア型の雑種等に分類されています。
形態的には、網系と網なし系統に分けられます。一般的に、家庭菜園において比較的作りやすいのは、プリンスメロンや一代交配種とされています。皮が網目状になるネット種は管理が難しく、プロ並みのテクニックが必要になってきますので、家庭菜園では、皮が網目状にならないノーネット種がおすすめです。
果実は多くの場合球形ですが、ラグビーボール形やこん棒形、さらには蛇の様に細長いものまで変化に富んでいます。その多くは中心部が綿状で多数の種子を含んでおり、表面は白色・黄色・緑色等で、複数の色が混ざる事もあります。産地として夕張などの冷涼な地域が有名ですが、現在日本において流通している高級メロンの元になった品種が、
もともと欧州で作られたものであるため、熱帯性の種の多いウリ科植物には珍しく、夏の高温多湿に耐えられないためとされています。果実は熟すと甘くなりますが、酸味が含まれる場合もあります。極粉質の果実をつける品種や、乾燥地帯の品種においては、昔から水筒の代わりとしての利用されている、1年程度もつような保存性のよい品種もあります。
種付けや水やり、肥料について
育て方としては、直まき、育苗どちらもできます。プランター等で育てることもできます。種まきする場合、芽がでにくいので、一晩水につけておきます。直まきのする場合は4月上旬頃に、株間20~25センチおきに1ヶ所2~3粒ずつ、種を入れてビニールトンネルで保湿します。ただし晴天の日はトンネル内が高温になりすぎるので、ビニールの裾を2~3センチ開けて換気するようにします。
育苗する場合はポットやセルトレイなどに種をまいて、4月下旬頃に植えるようにします。サイドに溝を作って真ん中を高くし、土をカマボコ型にします。プランターを利用する場合は、根がたくさん張れるよう、深くて大きいものを利用するようにしましょう。メロンの根は酸素を欲しがるので、通気性のよい培養土を入れて栽培することが大切です。
また手軽に始めるのであれば市販の苗を購入するとよいでしょう。その場合は、双葉が付いていてしっかりとした苗を選ぶようにします。基本的に寒さに弱いので、25℃程度になるように保温するようにします。夜間の気温が18℃以下にならないように注意してください。
親蔓は本葉4~5枚で摘心し、子蔓は2本伸ばして、11~15節に咲いた雌花を授粉します。それまでの孫蔓は早めに摘み取るようにしましょう。人工授粉はその日咲いた雄花を使い、朝10時までに行います。実がついたら、有機配合肥料を追肥し、水をたっぷりと与えるようにします。収穫して2~3日は室温で保存して、食べる数時間前に冷蔵庫に入れるようにします。
増やし方や害虫について
挿し木で増やすことができます。また水耕栽培も可能です。挿し木は、親蔓と子蔓2本を切り取り、メネデール水溶液に挿しておく事で、おおよそ10日程度で発根させることができます。また病気にかかりやすく、虫がつきやすいので、他の野菜以上に注意してあげるようにして下さい。
また栽培するのであれば、うどんこ病、つる割れ病に対して耐病性のある品種を選ぶようにするのも良いでしょう。気温が高くなったころ、日中になると葉が萎れ、そのあとに下葉からだんだんと黄色くなって枯れてくるつる割れ病についても注意しましょう。この場合の対策としては、薬剤による治療は困難なので、株を抜き取って焼却します。
また一度、発病した場所は病原菌が5年くらい生き残るため、同じウリ科やヒルガオ科の作物を後作にしないようにします。また多くのっ植物にとっても天敵でもあるアブラムシにも大変好かれるので予防を忘れないようにしましょう。見つけた場合には、早急に対処することが大切です。アブラムシは、新芽や葉に群生し、汁を吸います。
さらにウィルス病を媒介することにより、様々な病気の原因となります。具体的な対策としては、被覆資材をかけたり、水をかけて洗い流したり、薬剤を散布すると言った方法があります。薬剤は、パイベニカ乳剤やオレート液剤などの殺虫剤を散布するようにします。小面積の散布には、スプレータイプのモノを使うとよいでしょう。またハダニ類も、葉の裏に寄生して汁を吸い、被害が進むと葉が白っぽくなってきます。この場合も殺虫剤を散布して対策を取ります。
メロンの歴史
メロンは高級フルーツの代名詞。その名前は「りんごのようなうり」を意味するギリシャ語の”melopepon”が語源と言われています。原産地は、北アフリカ、中近東、東アジアなどの諸説ありますが、現在ではその生息地は世界中に分布しています。その歴史も非常に古く、紀元前2000年頃には古代エジプトやギリシャでも栽培されたといわれています。
その頃は食用としてだけでなく、薬用としても珍重されていました。欧州に伝わったものは、品種改良が重ねられて網目のある西洋系、中国に伝わったものは、品種改良されてマクワウリなどの東洋系と系統が分かれてきました。昔は暖かい地方でしか栽培できなかった為、北欧州地域で栽培されるようになったのは、14から16世紀以降頃のことであると言われています。
日本においては、縄文時代初期の遺跡からマクワウリやシロウリの種子が発掘されています。古い時代に中国から渡来したものと考えられています。そうした中でも雑草化したものを雑草メロンと呼び、西日本を中心に現在でも広く自生しています。ただし雑草種は苦味が強く、食用には向いていません。
いわゆるフルーツとしての西洋系は、明治時代に日本へ入ってきました。大正時代の頃になると、温室栽培が普及し、本格的に栽培が行われるようになった結果、市場にも出回るようになりました。昭和37年に欧州品種のプリンスメロンが登場すると、一般家庭にも普及してくるようになりました。
メロンの特徴
園芸分野では実を食用とする野菜、「果菜」とされています。青果市場での取り扱いや、栄養学上の分類では果物や果実に分類されています。メロンにはいくつかの品種群があります。例えばヨーロッパ型のネット種やカンタロープ、小アジア型のウィンター種、それに東アジア型の雑種メロン等に分類されています。
形態的には、網系と網なし系統に分けられます。一般的に、家庭菜園において比較的作りやすいのは、プリンスメロンや一代交配種とされています。皮が網目状になるネット種は管理が難しく、プロ並みのテクニックが必要になってきますので、家庭菜園では、皮が網目状にならないノーネット種がおすすめです。
果実は多くの場合球形ですが、ラグビーボール形やこん棒形、さらには蛇の様に細長いものまで変化に富んでいます。その多くは中心部が綿状で多数の種子を含んでおり、表面は白色・黄色・緑色等で、複数の色が混ざる事もあります。メロンの産地として夕張などの冷涼な地域が有名ですが、現在日本において流通している高級メロンの元になった品種が、
もともと欧州で作られたものであるため、熱帯性の種の多いウリ科植物には珍しく、夏の高温多湿に耐えられないためとされています。果実は熟すと甘くなりますが、酸味が含まれる場合もあります。極粉質の果実をつける品種や、乾燥地帯の品種においては、昔から水筒の代わりとしての利用されている、1年程度もつような保存性のよい品種もあります。
-

-
バーバスカムの育て方
バーバスカムはヨーロッパ南部からアジアを原産とする、ゴマノハグサ科バーバスカム属の多年草です。別名をモウズイカといいます...
-

-
ペンタスの育て方
この花については、アカネ科、ペンタス属となっています。和名の方をとってクササンタンカ属とすることもあります。熱帯植物に該...
-

-
アネモネの育て方
地中海沿岸が原産地のアネモネは、ギリシャ神話ではアドニスという美少年が流した血から生まれた花という説もあり、古くからヨー...
-

-
メカルドニアの育て方
メカルドニアはオオバコ科の植物で原産地は北アメリカや南アメリカですので、比較的暖かいところで栽培されていた植物です。だか...
-

-
スモモの育て方
スモモにはいくつかの種類があり、日本、ヨーロッパ、アメリカの3つに分類されます。ヨーロッパではカスピ海沿岸が生息地だった...
-

-
ムクゲの育て方
ムクゲはインドや中国原産とされる落葉樹です。生息地は広く、中近東になどにも分布しています。韓国の国花として知られています...
-

-
鉢植え乾燥地帯原産地「パキラ」の栽培方法について
鉢植え「パキラ」は東急ハンズ等で購入できる乾燥地地帯である中東が原産地の鑑賞植物です。高さが5cm以下の小型の植物で、手...
-

-
キアネラの育て方
キアネラの特徴について書いていきます。キアネラの原産地は南アフリカを生息地としています。ケープ南西部に9種のうち8種が生...
-

-
トリカブトの育て方
トリカブトは日本では”鳥兜”または”鳥冠”の由来名を持っています。この植物の花の形が舞楽で被る帽子の鳥冠に似ている事から...
-

-
ベンジャミンゴムノキの育て方
この植物はイラクサ目、クワ科、イチジク属となっています。イチジクの仲間の植物になります。それほど高くに低い木で、高さとし...




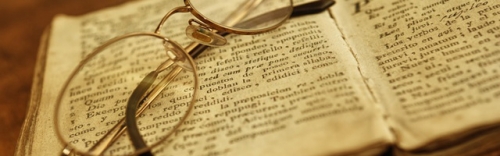





園芸分野では実を食用とする野菜、「果菜」とされています。青果市場での取り扱いや、栄養学上の分類では果物や果実に分類されています。メロンにはいくつかの品種群があります。例えばヨーロッパ型のネット種やカンタロープ、小アジア型のウィンター種、それに東アジア型の雑種メロン等に分類されています。