リッピアの育て方

育てる環境について
ミクロネシアやペルーといった亜熱帯気候が原産であるため、降雪地では育たないと思われがちですがそんなことはありません。生命力が強いため、豪雪地以外ならば十分に育てられる環境です。ただし、育て始めるときはいくつか注意が必要となります。育て始める場合、苗を植えるか種を撒くかの2パターンあります。苗にしても出てきた芽にしても、最初のころはデリケートです。
そのため寒冷地で育てるのならば暖かい4月から9月までに植えることが良いとされています。そして、温暖地も共通して言える植えるときのベストの時期が梅雨となります。リッピアは高温多湿の環境を好む傾向にあるからです。もしも、雨があまり降らない時期や地域で育てるのならば、種まきから1週間は毎日水をやる必要があります。
また植えたばかりでは他の雑草に負けてしまい成長スピードが遅くなることもあります。そのため種を撒く前には雑草を取り除いておくと早く根付きます。ただし、他の植物と違って植える前に肥料を加える必要はほとんどありません。リッピアだけでなくほとんどのグランドカバー植物は肥えた土を好まない性質があります。
堆肥を与えると一見早く生長するように見えますが、実は枯れる原因となることもあります。肥料を与えたくなる気持ちになり勝ちですが、その気持ちは抑えなくてはなりません。リッピアを育てるのに一番手間がかかるのは実は種を撒く前から撒いた後の1週間ほどです。その時期を過ぎればほとんど手間はかかりません。
種付けや水やり、肥料について
高温多湿を好む一方で非常に乾燥にも強いと言う特徴を持っています。どれほど強いかと言うと砂漠をグランドカバーしようという計画が持ち上がっているほどです。そのため、ほとんど水遣りをする必要はありません。ただし、数週間と雨が降らないと葉っぱが枯れてきてしまいます。日照りで葉っぱが変色してきたときは水遣りをしたほうが懸命です。
逆に水をやりすぎたからといって失敗することはほとんどありません。一方、肥料はやりすぎは禁物です。禁物と言うよりも与えるようと考える必要がありません。光と水によって光合成をして成長するからです。その光、つまり日当たりについては良いに越したことはありませんが、一日3時間程度の日照時間でも育つと言われています。
もちろん、日照時間が少ないと生長スピードは落ちます。今までの記述で不思議に思った人もいるかもしれません。花は咲くけど種子ができないなのに、種撒きができるのだから種子があるはずです。その種子はどうやって手に入れるかと言うと種付けです。花が咲いたとき人工的に受粉をすれば種子ができます。
花が咲く時期は5月から9月ごろであり、形はワレモコウのような形で白い色かピンク色の花が咲きます。種付けをすれば種子は取れますが、家庭でするのにはあまりメリットはありません。一度植えれば横に広がっていきますし、株分けすれば他の場所でも増やしていけるからです。つまり、リッピアも他に増殖する手段があるため、わざわざ種子を作る必要がないわけです。
増やし方や害虫について
先ほど記述したようにリッピアは植えたところから広がっていきますし、株分けすることも可能です。またコンクリートにもへばり付いてくるため、建物の近くで育てると建物全体をグランドカバーすることが可能です。増やしていくことは決して難しくありません。逆にどう増殖をコントロールするかが重要です。たとえば、他の植物にも影響を与えることがあります。
多年草などの植物だと下手するとリッピアに駆逐される可能性もあります。そのため、庭に一部だけはリッピアが生えないようにしたいと考えるケースも出てきます。そのときは、生えてほしくない場所に芽吹いてきたリッピアを踏むだけで解決します。生命力が強い一方で踏まれたらすぐに枯れてしまう性質があります。
放っておくと道路まで伸びてきますが、道路は人通りがあるためそれ以上広がることがほとんどありません。そのため、簡単に増殖をコントロールすることができるわけです。また害虫はハーブなのでカメムシなどは近づいてきません。ただし万能ではないことも知っておく必要があります。
虫の種類によってはリッピアの防虫効果がほとんど利かないものもいます。防虫効果を期待できる一方であまり過信しないほうがいいかもしれません。このように、いくつかのポイントさえ気をつければ、非常に育て方が簡単な植物であり、使い方によってはメリットが生じてきます。今後はさらにこのリッピアに対して注目が集まるのかもしれません。
リッピアの歴史
リッピアとは日本名で姫岩垂草(ヒメイワダレソウ)とも呼ばれている多年生植物です。大きく白い花を咲かせるものとピンクの花を咲かせるものの2種類がありますが、それぞれ原産も異なっています。白い花のものはミクロネシア原産であり、ピンクの花のものはペルー原産です。この2つのうち気候の近いとされるミクロネシアの白い花のほうが日本では好まれて植えられています。
その日本国内の需要は年々高くなっています。なぜならば、リッピアにはグランドカバー植物として適しているからです。地表や建築物などを覆い太陽光のエネルギーを吸収して光合成によって熱ではなく糖質に転換してしまいます。建物をグランドカバーすることによって室内の温度が5度ほど下がることもあるため、クーラーの使用を控えることができ電気の節約とともに二酸化炭素排出の抑制にも繋がります。
しかも、害虫も付きにくく雑草も生えにくく手入れもしやすいことから、近年では新しい緑化素材として注目されています。さらに害虫予防・雑草予防の効果から農業でも活用しようと言う動きが高まっています。農薬の使用を抑制しつつ害虫・雑草予防にもなるからです。
また、原発事故にもこの植物は注目されました。なぜならば、セシウムの吸着効果がヒマワリの30倍もあると分かっているからです。そのため、原発事故のあった福島第一原発の周辺にこれでグランドカバーするべきではないかという構想も持ち上がっています。このように多方面から注目されているのがリッピアです。
リッピアの特徴
リッピアは多方面から需要があります。その理由はすでに記述したようにグランドカバー・害虫予防・雑草予防・栽培に手がかからないという特徴があるからです。そこを詳しく述べていきます。本来の生息地は亜熱帯で湿度が高いミクロネシアやペルーであるため、生命力の強い植物だと言われています。降雪地ですら越冬できるほどです。
それがグランドカバーの役割に大きく貢献します。芝の20倍もの被覆進度であります。つまり、密集して生えてくれるため、他の雑草が生えにくくなります。これが雑草予防となります。でも、生命力が強いと背丈が高くなったり、周辺の環境への影響を心配する人がいます。しかし、丈は高くても5cm程度で止まります。
雑草も生えず丈も高くならないため、草むしりや草刈りといった手間がほとんどかかりません。そのため、一般家庭の庭で芝生の変わりにリッピアを植えているところが増えてきています。さらに種子を形成しないため周辺に広がっていく懸念も少ないです。外来植物の環境の影響が小さいため安心して利用できるため一般家庭だけでなく農家でも活用する人が増えています。
そして、ハーブの一種でもあるため、カメムシなどの害虫は付きにくい傾向にあります。というのも、ハーブの香りは虫除けのために発せられているからです。カメムシ以外にも害虫で頭を抱えている人はこれを植えることで悩みが解決する可能性が高いです。このように高い機能性・安全性があるのがこの植物の特徴となります。
-

-
トマトの栽培やトマトの育て方やその種まき方法について
トマトはその赤い色が食欲をそそる野菜となっています。トマトはなす科の野菜となっているので、トマトの育て方としては連作障害...
-

-
オジギソウの育て方
オジギソウは非常に昔から日本人に好かれてきた植物です。そもそものオジギソウの名前の由来を見ると、触ると葉を閉じてしまって...
-

-
イチジクの育て方
イチジクのもともとの生息地はアラビア半島南部、メソポタミアと呼ばれたあたりです。文明発祥とともに身近な食物として6000...
-

-
一重咲きストック(アラセイトウ)の育て方
一重咲きストック、アラセイトウはアブラナ科の植物です。原産地は南ヨーロッパで、草丈は20センチから80センチくらいです。...
-

-
ガステリアの育て方
ガステリアは、ススキノキ科、ガステリア属になります。小型の多肉植物です。日本ではマイナーな植物であり、和名が「臥牛」とい...
-

-
キンモクセイの育て方
キンモクセイはギンモクセイの亜種で江戸時代に中国から伝わってきました。九州には自生するウスギモクセイが変異した説もあり、...
-

-
アガベ(観葉植物)の育て方
アガベとは、別名・リュウゼツラン(竜舌蘭)とも呼ばれ、リュウゼツラン科リュウゼツラン属の単子葉植物の総称のことで、100...
-

-
サキシフラガ(高山性)の育て方
サキシフラガは、ユキノシタ科ユキノシタ属に分類される高山性の植物です。また、流通名はホシツヅリ、別名をカブシア、ジェンキ...
-

-
ミニトマトのプランターの栽培方法
ミニトマトの栽培は初心者でも簡単に育てられ庭がなくても、プランターで栽培出来きるので、プランターでミニトマトの育て方はと...
-

-
クジャクサボテンの育て方
クジャクサボテンはメキシコの中央高原地方で古くから存在していた原種を交配して作り上げた交配種であり、世界的に数百種類の品...




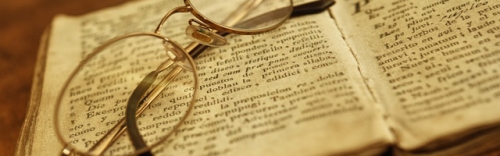





リッピアとは日本名で姫岩垂草(ヒメイワダレソウ)とも呼ばれている多年生植物です。大きく白い花を咲かせるものとピンクの花を咲かせるものの2種類がありますが、それぞれ原産も異なっています。白い花のものはミクロネシア原産であり、ピンクの花のものはペルー原産です。