ヒベルティアの育て方

育てる環境について
ヒベルティアを育てるにあたって、適した環境は雨の少ない温暖な気候です。半耐寒性植物で耐えられる寒さは-5度までです。この植物の原産国はオーストラリアですから、直射日光は苦手ですが温暖で気温差の少ない環境が好まれます。オーストラリアは場所にもよりますが、冬でも昼間は半袖で過ごせる様な温暖な気候です。
また雨も少なく、湿気が少ないのもこの土地の特徴、ヒベルティアも湿気の少ないカラッとした土地を好みます。なので、日本でこの花が育つのに適しているのは温暖な西日本の方が向いているでしょう。ただ日本では鉢植えスタイルがメジャーなので、気温と湿度の管理を徹底出来るのであれば日本全国どこでも育てる事は出来ます。
一番気を付けたい時期は梅雨の時期です。じめじめと湿気が多い長雨は大嫌いな植物です。この時期、花がもう散っている種類もあれば最盛期を迎えている種類もあります。どちらにせよ、軒下に避難させるか屋内での栽培が望ましいです。屋内では、置く場所に配慮しましょう。
陽当たりと風通しの良い環境は好みますので、窓際に置くようにし、直射日光が当たる様な場合はレースカーテン越しに置きます。越冬もこの屋内での栽培がオススメです。オーストラリア産なので霜にも弱いからです。屋内で栽培する時は暖房の風に直接当たらない様にする事も気をつけます。水はあまり与えなくても大丈夫です。これでオーストラリアのカラッとした温暖な環境に近づけます。
種付けや水やり、肥料について
この花は、ナイロンポットに株として販売されている事が一番多いです。種子は出来にくい植物の様です。この花の開花時期である春頃、この株を購入し鉢に植え付けます。つる性植物は花壇に植えると色々な表情を見せてくれて楽しめますが、日本の気候では難しいのが現状です。
鉢植えでもアレンジを楽しみたい時は、ハサミでカットしながら上手に誘引してあげると、思うがままにフラワーアレンジを楽しめます。鉢植えの土は、粘土質の土壌は避け一般的な培養土を使用します。水はけの良い環境を好みますので、腐葉土を混ぜたり川砂やパーライトを混ぜるのもオススメです。
腐葉土を入れる時はコバエが発生しない様に、いちどふるいにかけると良いでしょう。水はけの良さも増します。肥料はあらかじめ暖効性化成肥料を混ぜ込み、生育時に液肥を与えます。液肥は植物の様子を見ながらですが、月に2回~3回程度が目安です。水やりは、株を植え付けた後は少し多めに水を与え、その後の水やりは控え気味にしましょう。この植物は常緑低木です。
育てるポイントとしては、枝は伸ばしっぱなしにしない様にして、こまめな剪定が必要です。わぎ目を出すようにしてあげた方が、栄養もバランスよく行き渡り丈夫に育ちます。根っこもですが、全体的に呼吸出来る環境というのがこの植物の焦点ともなります。生息地が雄大なオーストラリアという割には意外と手間暇かかる花です。中級者向けのレベルの植物、しかしその分可愛らしい可憐な花姿を見せてくれます。
増やし方や害虫について
ディレニア科ヒベルティア属は、害虫被害に遭いにくい植物です。しかしアブラムシやガには注意が必要です。花が咲く時期とアブラムシが活動し出す時期が一緒なので、早めの発見が功を奏します。浸透性の殺虫剤を早めに散布します。また乾燥を好む植物が故に、乾燥し出すとハダニもつきやすくなります。ダニも早めに薬を散布して手を打ちます。
まれに屋内で栽培していると、クモが巣を作りだす事もありますが、こちらはあまり害はないので、薬などはかけずに霧吹きで水を振りかけ巣を壊して巣を作らせない様にします。かかりやすい病気はありませんが、葉っぱが変色し出す時は大抵の原因は根詰まりです。根詰まりを解消し液肥を与えて様子を見ます。最後に増やし方ですが、挿し木で繁殖させます。
一般的な挿し木の繁殖方法と同じで、10センチ程の長さに切ります。葉がついている時は、手でもぎ取らずハサミで切り取ります。そして枝を鉢に最初と同じ様な用土を作り、その用土に切った枝を挿し込みます。使用していた鉢に植える際は、花殻などはしっかり除去しておきましょう。水をたっぷり与え、芽や根が伸びてきたら水の量を減らし、液肥で栄養補給します。
この挿し木の方法で、毎年栽培する事が出来ます。花が咲いてない時期でも、可愛らしい葉っぱなので観葉植物として楽しめるので、年中楽しませてくれる素敵な植物です。寄せ植えなどにも向いているので、楽しみ方が無限大の植物です。鉢植えで美しくアレンジしてプレゼントとにも向いている花です。
ヒベルティアの歴史
原産地をオーストラリアとするヒベルティアという花は、種類にもよりますが花茎が3㎝~4㎝の小さな花を毎年花を咲かせる常緑低木です。熱帯から亜熱帯の地域に分布するとあって、黄色の色鮮やかな色彩が魅力です。でもこの花は常緑低木に分類されているので、花が咲かない時期は観葉植物として葉や木だけでも楽しませてくれます。
そんな可憐なヒベルティアが発見されたのは、18世紀頃だと言われています。皆さんもご存知の通り、この花の故郷であるオーストラリアはアボリジニーという先住民が住んでいましたが、15世紀頃からヨーロッパを始めとする外国から渡航家達が続々と訪れる様になりました。当初は、特に目を引くものもなかった様で大陸を発見し地図を起こす程度でした。
しかしその後の1770年にクック船長が上陸した際、魅力がいっぱい詰まったこの島をイギリスの占領地としたそうです。その魅力の一つとされているのが、オーストラリアに生息する植物です。一緒に上陸した植物学者達は、見るもの全てが未知の世界だと言わんばかりにオーストラリアの植物に興味を示したそうです。
そんな中、アマチュア植物研究家であり、商人のイギリス人ジョージ・ビバートさんが発見し自分の名前に因んで小輪で可愛らしい黄色いこの花にヒベルティアと名付けたそうです。オーストラリアには100種類以上生息していると言われており、オーストラリアを代表する花として知られています。
ヒベルティアの特徴
育て方がやや難しいのがこの花の特徴です。草丈が10㎝~15㎝程で横に10㎝~30㎝程広がる事も大きな特徴です。オーストラリアでは、荒地や砂地などに自生している姿をよく見かけます。日本では寒さや雨に耐えられないので、路地に自生している姿を見る事は殆どなく鉢での栽培が一般的です。開花時期は3月~4月の春で、3月27日の誕生花としても有名です。
花言葉は「無邪気」元気が出るビビットカラーの黄色と可愛らしい小さな花姿が、ピッタリです。ちなみに和名もしっかり付けらており、「黄花魚柳梅(キハナギョウリュウバイ)」と言います。黄花は黄色い花から来ていて、葉が御柳という樹木に似ており、梅の花の様な花を咲かせる事からこの名前が付いたと言われております。
ヒベルティア属には100種類程の仲間がいますが日本で見られるのはほんの僅かな種類です。人気の座を不動の物としているのが、「ステラリス」という種類です。乾燥に強くオレンジ色の花を咲かせるのが特徴です。花茎が3㎝未満と小さいサイズにも関わらず鮮やかでインパクトがある為、鉢植えとして人気が高いです。
次の「セルピリフォリア」は花びらがフリルの様に波打っていて洒落た形をしています。「ヴェスティタ」によく似ていて、初心者には中々見分けがつきません。近年品種改良が進んでいるのが、「ペデュンクラタ」です。黄色の花を次々と咲かせ、品種改良された事により花茎が少し大きくなってきています。
-

-
ルピナスの育て方
特徴の1つは寒さに強く、暑さに弱い事があります。具体的には寒さであればマイナス5℃程度まで耐えられます。外に置いておいて...
-

-
カスミソウの育て方
カスミソウの原産地は地中海沿岸から中央アジア、シベリアなどで、生息地は夏季冷涼なところです。カスミソウの属名ギプソフィラ...
-

-
ジャカランダの育て方
ジャカランダは世界三大花木の一つとして知られており、日本では数多くあるジャカランダの品種の内の一部が栽培されています。日...
-

-
桃の育て方
桃の歴史は紀元前にまで遡り、明確な時期は明かされておりませんが、中国北西部の黄河上流が原産地とされています。当時の果実は...
-

-
スパティフィラムの育て方
スパティフィラムは中央アメリカから南アメリカの熱帯地域を原産とするサトイモ科の多年性植物です。主に森林の湿地帯を生息地と...
-

-
ジニアの育て方
ジニアはメキシコが原産の植物です。生息地はメキシコあたりで、1,796年にスペインへともたらされます。スペインの首都マド...
-

-
ミニトマトのプランターの栽培方法
ミニトマトの栽培は初心者でも簡単に育てられ庭がなくても、プランターで栽培出来きるので、プランターでミニトマトの育て方はと...
-

-
コンボルブルスの育て方
コンボルブルスは地中海の沿岸を中心とした地域で200種くらいが自生しているとされていて、品種によって一年草や多年草、低木...
-

-
ギリアの育て方
種類としてはハナシノブ科になります。別名があり、タマザキヒメハナシノブ、アメリカハナシノブなどの名前が付けられています。...
-

-
ゼフィランサスの育て方
ゼフィランサスについては、ヒガンバナ科(クロンキスト体系ではユリ科)タマスダレ属の植物のことをまとめてそう名づけられてい...




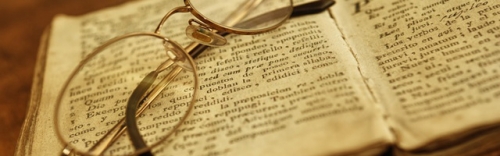





ディレニア科ヒベルティア属は、害虫被害に遭いにくい植物です。原産地をオーストラリアとするヒベルティアという花は、種類にもよりますが花茎が3㎝~4㎝の小さな花を毎年花を咲かせる常緑低木です。熱帯から亜熱帯の地域に分布するとあって、黄色の色鮮やかな色彩が魅力です。でもこの花は常緑低木に分類されているので、花が咲かない時期は観葉植物として葉や木だけでも楽しませてくれます。