ベルフラワーの育て方

ベルフラワーの育て方
初夏のころに紫色の小さな釣鐘型の花をたくさんつけるベルフラワーは、別名オトメギキョウとも呼ばれ、常緑性の小型多年草です。4月から5月ごろに最も多く流通し、花屋さんやホームセンターなどでもよく見かけるようになりますが、3月ごろから促成栽培されたものが出回り始めます。草丈は10センチメートルから15センチメートルほどで、小ぶりの濃い緑色の葉を多数つけます。
茎は根元の部分から密に枝分かれして、直径が30センチメートルから40センチメートルほどのクッション状の茂みを形成します。枝先にそれぞれ数輪の青紫色で直径2センチ前後の釣鐘型で上向きやななめ上向きに咲く花をつけます。石灰岩の崖などが自生地ですが、家庭で栽培する際にも石灰を使用しなければならないわけではありません。
まず植え付けには、水はけと保水力のある肥えた用土に植えるようにします。乾燥にはやや弱いので、家庭で栽培するときにはプラスチック鉢を利用するのがおすすめです。植えつける際には、用土に適量の粒状の肥料などを混ぜ込んで元肥にします。水やりは、鉢の土が乾いてきたらたっぷりと水を与えるという育て方をしますベルフラワーは。
幾分湿り気のある土を好む植物ですが、過度の湿り気は根腐れを起こす原因になるので、冬には特に水やりは控えめにして、やや乾燥気味の状態を保つ育て方をするようにします。小さく可憐な花を多数咲かせるベルフラワーは、花が咲いた後には急激に株が疲労します。この時期に肥料を施すと、枯死することがあります。肥料を与える時には液体肥料を適量に薄めて使用するようにします。
夏が来る前の時期に、ゆっくりと株を回復させることが大切です。花後の株に疲労や痛みなどがみられない場合でも、葉の色が薄くなったと感じられたら液体肥料をやや濃いめに希釈して10日に一度くらい施肥するようにします。けれども真夏には施肥をする必要はありません。暑さが落ち着く9月の彼岸花が咲く時期になったら再び液体肥料を夏前と同じように10日に一回施します。
冬も施肥は控えるようにします。翌年の春八重桜が開花するころになるとベルフラワーも芽が動き始めるので、この頃になったら同様に液体肥料を使って施肥するようにします。ベルフラワーは酸性土に植えると育成が鈍るので、産生土の場所に庭植えをする場合は石灰を混ぜて中和させておくと理想的です。
ベルフラワーは日当たりの良い場所を好むので、花壇や庭などに植えて栽培する場合にも水はけがよく、日の良く当たる場所を選ぶようにします。日光に当たらないと花つきが悪くなります。春と秋は日当たりで管理する育て方をしますが、暑さには弱いので、夏は風通しのいい日陰か木漏れ日程度の半日陰へと移動させるようにします。
ベルフラワーの増やし方
ベルフラワーを増やすには、種付けではなく株分けのほうが簡単です。秋の初めになると盛んに葉やランナーを伸ばし始めるので、株を鉢から抜き取り、古い根や古土を落として根鉢をほぐして分けます。一株を小さめに分けても、しっかりと用土に植え付けておけば大丈夫で、大体1か月ほどで根が張るようになります。
根が張ったらその後はポリポットに植え替えて、冬が来る前までに、できるだけ植え替えた株を太らせるようにします。寒さには強く抵抗力があるので、冬は室外で管理して大丈夫です。地面が凍ってしまうほどの寒冷地でも、5℃前後の気温の寒さにしっかりと当たるまでは室内に取り込まないようにします。
寒さにあたることで花芽をつける性質があるためです。種付けをする場合には4月から6月の上旬に種付けを行うようにします。種付けを行った部分の覆土は薄くするようにします。底面給水して、夏には遮光して涼しい場所で管理するようにして、本葉が2枚から3枚程度付いたらポットに移植します。
10月の上旬ごろに本葉が5枚から6枚になったら元肥を施して定植するようにします。翌年の春に成長が始まるころになったら週一回の液体肥料を追肥してやります。花後に切り戻すと、次から次へとたくさんのつぼみをつけ花を咲かせます。
ベルフラワーの病害虫
初夏の新芽が伸び始めるころにアブラムシが発生したら、殺虫剤や殺虫殺菌剤を散布して退治しておくようにします。アブラムシの二次被害として尾の部分から出る排泄物がアリを誘引したり、すす病を誘発してウイルス病を媒介することがあります。葉を萎縮させたり、湾曲させたりして、種類によっては葉に虫こぶを作るものもいます。
また、ハダニが発生することがあります。ハダニは多くの種類がいますが、葉の裏側などについて植物の汁を吸います。ハダニは一匹がとても小さいので汁を吸うと言ってもごく少量ですが、天敵のいない環境だと爆発的に増えてしまいます。汁を吸うとその部分の葉緑素が抜けて白い模様が浮き上がって見えるようになり、ここまで来てやっとハダニの被害に気付くこともあります。ハダニは乾燥すると発生するので、葉に水をかけてやることで予防することができます。
ベルフラワーの歴史
ベルフラワーはカンパニュラの仲間で、カンパニュラはラテン語の釣鐘を意味する言葉から由来しており、薄紫色のベル状のかれんな花を咲かせます。小さな花が株を覆うように咲くので、鉢物として栽培するのにとても魅力があります。全体的に小型の植物なので、机の隅や窓の端の方に控えめにおいて楽しむのにも適しています。
ヨーロッパを中心とした北半球が原産の多年草で、カンパニュラ属は地中海沿岸地方を中心とした生息地に、原種が300種類以上もあると言われ、改良も盛んに行われているため、種類がとても豊富なのが特徴です。鉢物として出回っているのはポルテンシュラギアナ種で、日本に自生するホタルブクロと同属の花です。
イギリスではカンタベリーの鐘とも呼ばれ、英名ではダルメシアンベルフラワーですが、花の形がベルに似ていることからベルフラワーとして流通するようになりました。キキヨウによく似た小ぶりで可憐な花であることから日本ではオトメギキョウと呼ばれています。
ベルフラワーの特徴
鉢植え用に改良されたベルフラワーは草丈が低く、茎の先に青紫色で花の直径が2センチメートルほどの星形のかれんな小花をたくさん咲かせます。葉は常緑で、縁がぎざぎざのあるのこぎりのような形をしており、茎がほふくして株を増やす性質があるので、ハンギングバスケットなどに利用するのにも最適です。
草丈は10センチメートルから20センチメートルほどで、5月から7月が花期です。鉢植えで市場に出回るのは4月から7月くらいの間です。カンパニュラの種類としてはメディウム種はフウリンソウという和名があり、花の見た目が風船のようにふっくらとした花を上向きや横向きに咲かせます。
カリカンテンマ種は花冠のようなゴージャスな雰囲気を持ち、庭植えに向いており、コンテナガーデンに向くものなど、和風にも洋風にも豊富なバリエーションが揃うのが特徴です。特別な手入れも必要なく、比較的簡単に育てることができるうえ、小ぶりで可憐な花がいくつも咲いてくれるので、ガーデニング初心者でも育てやすいという点はベルフラワーの最大の魅力です。
特別に手をかけてやらなくても、肥料さえきちんとやって置くことを忘れなければ、毎年必ず可憐な花をたくさんつけてくれます。他の植物と寄せ植えにして楽しむのにも向いており、ガーデニングの醍醐味を存分に堪能することができます。まずは比較的育てるのが簡単なベルフラワーを手に入れて、ガーデニングを始めてみるのがおすすめです。
花の育て方や植物に興味がある方は下記の記事も参考になります♪
タイトル:オトメギキョウの育て方
タイトル:ニューギニアインパチェンスの育て方
-

-
ゴーヤーともよばれている健康野菜ニガウリの育て方
ゴーヤーは東南アジア原産の、特有の苦味があるつる性の野菜です。沖縄では古くから利用されており郷土料理”ゴーヤーチャンプル...
-

-
ペピーノの育て方
日本的な野菜の一つとしてナスがあります。他の野菜に比べると決して美味しそうな色ではありません。紫色をしています。でも中は...
-

-
サキシフラガ(高山性)の育て方
サキシフラガは、ユキノシタ科ユキノシタ属に分類される高山性の植物です。また、流通名はホシツヅリ、別名をカブシア、ジェンキ...
-

-
ホメリアの育て方
ホメリアは庭植えの場合に関しては、数年植えっぱなしでもそのままの状態で育つことができます。毎年球根を掘り上げるよりも、花...
-

-
キンカン類の育て方
柑橘系果物の一つにキンカンが有ります。一言でキンカンと言っても複数の種類が有り、キンカン類としてはキンカン属が4~6種類...
-

-
ヒナガヤツリの育て方
ヒナガヤツリは、カヤツリグサ科カヤツリグサ属の植物です。ヒナガヤツリの原産地は北アメリカですが、主な生息地はオーストラリ...
-

-
シンビジウムの冬の育て方について
クリスマスやお正月のギフトによく利用されるのがシンビジウムです。洋ランの一種でありながら、比較的素人にも育てやすく日本で...
-

-
大根の育て方
大根の原産地は地中海沿岸といわれていますが、いろいろな説もあります。紀元前2500年ごろにエジプトでピラミッドを通ってい...
-

-
ミソハギの育て方
種類としては、バラ亜綱、フトモモ目、ミソハギ科となります。水生植物、山野草として分類されるようになっています。花は多年草...
-

-
緑のカーテンの育て方
ゴーヤのグリーンカーテンの育て方についてご紹介です。もともとお花を育てることが好きだった私ですが、去年の引越しをきっかけ...




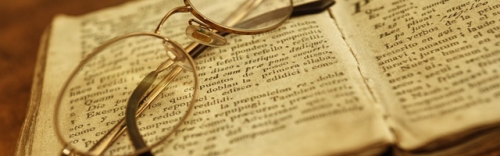





ベルフラワーはカンパニュラの仲間で、カンパニュラはラテン語の釣鐘を意味する言葉から由来しており、薄紫色のベル状のかれんな花を咲かせます。小さな花が株を覆うように咲くので、鉢物として栽培するのにとても魅力があります。全体的に小型の植物なので、机の隅や窓の端の方に控えめにおいて楽しむのにも適しています。