チシマギキョウの育て方

育てる環境について
チシマギキョウの育て方としては、基本的に日のあたる場所を選ぶことが好ましいです。日当りがよく風通しのよい場所で栽培し、夏場の気温が高くなるシーズンには半日陰に移動させてあげるようにしましょう。7月頃から9月の上旬くらいまでは気温が高く乾燥しやすいですので、
日焼けや高温障害を起こしてしまうケースがあります。このシーズンは、30パーセントから40パーセントくらいの遮光をすることが好ましいです。冬の寒いシーズンは日当たりがよくてあまり風のあたらないような場所で管理することがおすすめされています。
庭植えにして栽培する場合は、ロックガーデンを築いて植えつけしてあげるとよいでしょう。鉢植えをして育てていく場合の用土には、軽石や硬質鹿沼土、桐生砂や赤玉土などのような小粒を混ぜて利用することがおすすめです。園芸ショップなどでは、
山野草用の培養土などが販売されていますので、これらの市販の土を使用することもあります。水でよく洗ってから、みじんを抜いて使用するようにしてください。赤土を用土に利用するような場合は、よくふるっておいてから使用してください。
使用する鉢は、3、4号くらいの深鉢や抗火石鉢、断熱鉢などを選ぶとよいでしょう。根と茎の境界線辺りから上部分には、花崗岩質の粗い砂利で覆っておくと効果的です。鉢植えで植え替えをする場合は芽が出始める前の2月から3月上旬くらいがおすすめで毎年おこないましょう。
種付けや水やり、肥料について
チシマギキョウは鉢植えで育っていく場合でも、庭植えをして育てていく場合でも土の表面が乾いてきたらたっぷりと水やりをしていきます。夏場は乾燥しやすくなりますし、耐寒性には優れているチシマギキョウですが耐暑性にはやや弱い性質を持っている植物です。
そのため、気温が高くなる夏のシーズンだけでも二重鉢にして育てていくことがおすすめされています。二重鉢には砂床に埋めておくことによって、乾燥や鉢内の温度が上昇してしまうことを防ぐことができます。砂床の作り方は、発泡スチロール箱などを利用して、
側面の下方のおよそ2センチメートルから3センチメートルのところに水抜き用の穴を数か所あけて、その中に洗った軽石や鹿沼土の小粒を満たしていくようにします。完全に水切れになってしまわないようにしてください。肥料は、植え替えをおこなう際に、
元肥としてリン酸とカリウムが多めの緩効性化成肥料を利用していきます。植え付け後に緩効性の固形肥料を置肥していくとよいです。3月頃から9月頃にかけては月に1回から2回くらい施します。液体肥料を利用する場合には、2000倍くらいに薄めてから施すようにしていきましょう。
真夏の暑いシーズンに肥料を与えてあげる場合には、液体肥料は3000倍くらいにまで薄めてから施してあげることが好ましいとされています。植え替えは毎年1回はおこなうことが好ましいですので、この時に成長に合わせて一回り大き目の鉢へと植え替えをおこなっていきましょう。
増やし方や害虫について
チシマギキョウの増やし方には、タネまきによる方法と株分けによる方法とが用いられています。タネまきをする場合には6月から7月頃に採種したものを保管しておきます。チシマギキョウのタネは茶色っぽくて砂のように細かいものとなります。
採種して冷蔵庫などで保管しておいたものを、翌年の2月から3月上旬くらいにまいていきます。比較的発芽率はよい方ですので、あまり密着してまいてしまわないように注意してください。タネまきをしてから順調に生育していけば、およそ2年くらいで開花していくことが多いです。
株分けをおこなうタイミングは、植え替えをする時に一緒におこなうことがおすすめされています。庭植えをしている場合は、3年に1回は植え替えをすることがこの増しです。株を分けていく場合は自然に分かれている部分で切り分けしていきます。つながっている株の場合は、
それぞれに芽がついているかどうかを確認して根が付いているようでしたらナイフなどを利用して切り分けをしていきましょう。切り分けをした場合には、カットした部分に癒合剤や殺菌剤を塗って保護しておくことが効果的です。チシマギキョウの主な病気には、軟腐病と呼ばれている梅雨のシーズンから夏にかけて発生することが多い病気があります。
発生してしまうと茎の根元部分が腐って抜けてしまうことがありますので、風通しをよくして水はけのよさを保ってください。害虫としては、ヨトウムシ、ハダニ、アブラムシが挙げられます。ヨトウムシは、春の終わり頃から夏の初め頃と、秋の初め頃に発生しやすいので注意してください。
チシマギキョウの歴史
チシマギキョウは、キキョウ科ホタルブクロ属に属している多年草のことを言います。キキョウ科は、真正双子葉植物の科で大部分が草本、一部はつる性でおよそ80属2000種からなり世界的にも広く分布しています。キキョウ科のホタルブクロ属は、基本的に個体として複数年にわたって生存する多年草なのですが、
まれに種子から発芽して1年以内に生長、開花結実して種子を残して枯死してしまう一年草や越年草などもあります。北アルプスなど北半球には、およそ300種類ほどが分布しており日本原産には5種類ほどがあるとされています。日本国内であれば、主に本州中部以北、
北海道の高山の岩場や礫原などが生息地となっています。園芸ショップなどで販売されている商品には、カンパニュラと記載されていることがあります。これは、花の形が釣り鐘に似ている地中海沿岸地方に原産する植物から改良された観賞用植物の総称で、
花の形が釣り鐘に似ていることからラテン語の釣り鐘を意味することばに由来しています。現在一般的に栽培されているチシマギキョウの大部分は、大正時代頃に色丹島で採集されたものの子孫だとされています。チシマギキョウによく似たイワギキョウも各地の高山帯で見られます。
これはは、葉の縁や花冠の向きなども異なります。もっとも分かりやすい違いとしては、チシマギキョウの花冠には長毛がありますが、イワギキョウには毛が生えていないという点が挙げられます。
チシマギキョウの特徴
チシマギキョウの草丈はおよそ5センチメートルから15センチメートルほどで、花茎の先に青紫色をした釣鐘状の花を1輪横向きに咲かせていきます。開花するシーズンは、7月下旬頃から8月にかけてです。花の長さは、およそ3センチメートルから4センチメートルほどで大きいのが特徴です。
花冠の外側は紫色をしており内側は濃い紫色で鐘形または漏斗形になって先の部分が5つに深く切れこみます。花冠の内側には白い毛が密生し、萼筒や萼片には長い軟毛が生えています。萼は筒状になって下部は子房と合着して上部は5裂し、裂片間に付属片がつく場合があります。
雌しべの花柱は雄しべよりも長くて先の部分が3つに裂けています。葉は少し厚みがあり表面にはツヤがあるのが特徴で互生します。 葉の縁には波状のギザギザがあり、 茎の部分には小さな葉を2、3枚つけます。チシマギキョウの萼片は全縁ですがイワギキョウには鋸歯があるのが特徴です。
また、チシマギキョウの花は青みよりも紫色がかっています。チシマギキョウの学名は、Campanula chamissonisでchamissonis というのはドイツの分類学者シャミッソーという意味があり、Campanulaにはラテン語で小さな鐘のという意味があります。
日本の品種には、チシマギキョウやイワギキョウの他にも、ヤツシロソウやシマホタルブクロ、ホタルブクロなどがあります。栽培品種には、ニワギキョウ やヒメギキョウ、フウリンソウ、ホシザキキキョウなどさまざまな種類があります。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:タマシャジンの育て方
-

-
キジムシロの育て方
被子植物で、バラ目、バラ科、バラ亜科となっています。特徴としては、梅に似ているだけあって属以外は梅と同じです。被子植物で...
-

-
ユーフォルビアの育て方
ユーフォルビア、別名、ユーフォルビアダイヤモンドフロストは、トウダイグサ科ユーフォルビア属の植物です。生息地は世界の熱帯...
-

-
ミルトニオプシスの育て方
花の種類としては、ラン科、ミルトニオプシス属になります。園芸の分類としてはランになり、多年草として楽しむことが出来る花に...
-

-
カモミールの育て方について
カモミールはハーブの一種です。ハーブというのは、食用や薬用に用いられる植物の総称です。人の手が必要になる野菜とは異なり、...
-

-
コルジリネの育て方
コルジリネはキジカクシ科のセンネンボク属に属します。原産地は東南アジア、オーストラリア、ニュージーランドなどでの熱帯から...
-

-
フィットニアの育て方
フィットニアはキツネノマゴ科フィットニア属の植物です。南米、ペルー・コロンビアのアンデス山脈が原産の熱帯性の多年草の観葉...
-

-
オカヒジキの育て方
オカヒジキの原産地は日本や中国、シベリア、ヨーロッパ南西部です。「ヒジキ」と言いますが海藻ではなく海辺の砂地などを生息地...
-

-
すなごけの育て方
特徴は、何と言っても土壌を必要とせず、乾燥しても仮死状態になりそこに水を与えると再生するという不思議な植物です。自重の2...
-

-
エボルブルスの育て方
エボルブルスは原産地が北アメリカや南アメリカ、東南アジアでヒルガオ科です。約100種類ほどがあり、ほとんどがアメリカ大陸...
-

-
緑のカーテンの育て方
緑のカーテンの特徴としては、つる性の植物であることです。主に育てるところとしては窓の外から壁などにはわせるように育てるこ...




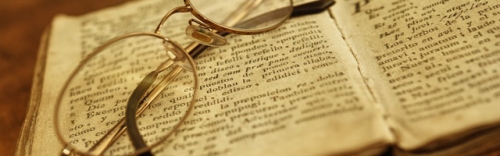





チシマギキョウは、キキョウ科ホタルブクロ属に属している多年草のことを言います。キキョウ科は、真正双子葉植物の科で大部分が草本、一部はつる性でおよそ80属2000種からなり世界的にも広く分布しています。