ナーベラー(ヘチマ)の育て方

育てる環境について
最適な温度帯は25度から30度で多湿が苦手なため、水はけのよい土が望まれます。乾燥も苦手なので水遣りをしっかり行いましょう。場所としては、日当たりがよく風通しのいい場所がベストです。棚を作る際は南向きか西向きで仕立てください。葉が立て込んできたら湿気がこもらないよう剪定をします。
種まきの時期は、本土なら本格的に暖かくなる4月中旬から5月上旬ごろが適しています。発芽の適温が25度以上なので苗床用ポットに1粒植えにし、暖かい場所で育てるのがおすすめです。種の深さは1cm程度で、肥料はやらずに水をたっぷりとあげてください。
遅霜の心配がなければ直まきもOKです。その場合は種をまく2週間前に、完熟堆肥・苦土石灰などを土に混ぜ込んでおきましょう。プランターに植え付けるのなら、大きめでしっかり深さのあるプランターを選んでください。土は市販の肥料入り野菜用配合土を使います。
本葉が4〜5枚開いたら畑や庭へ定植します。関東なら温度の上昇してくる5月上旬ごろからが植えつけの適期となり、着花が遅れないよう5月中旬までに植え付けを完了させておきます。株間は約90cmほどにしてください。プランターの場合は65cmのプランターに1株が適当です。
「緑のカーテン」にする場合は網目が10cm程度の蔓物(つるもの)用ネットを用意します。株のそばに支柱を何本か立て支柱と支柱の間に蔓物用のネットを張れば、つるを這わせる準備は完了です。緑のカーテンの場合も棚仕立ての場合も、重い果実を支え、強風に耐えられるようしっかりと固定してください。
種付けや水やり、肥料について
種の選び方ですが、タワシが目的なら「太へちま(太さ8~10cm長さ30~50cmくらい)」か「大長へちま(太さ7~8cm長さ70~80cmくらい)」を、食用が主体という場合には「食用短形種(太さ6~7cm長さ40cm)」がお勧めです。育て方はどの種でも一緒です。
しかし、どの種を選んでも幼果なら食用に出来ますし、逆に食用短形種であっても実が熟成したら繊維だらけで食べられなくなります。食用にするなら開花から10日目、盛夏期なら7日目程度での収穫が良いようです。長さ30~45㎝、太さ4~5㎝程度を目安にしてください。
種まき時には肥料は必要ありません。植え付け時には、1平米あたりに完熟堆肥を約3kg、有機配合肥料を80g、苦土石灰150gを入れて土を盛り上げておきます。プランター植えの場合には最初から肥料が入った野菜用配合土を利用します。その後は月1回程度、1平米当たり30gの粒状肥料をばらまいて追肥していきます。
水やりは表土が乾いたらたっぷりとあげるようにしてください。着果を確認してからは多めに水やりしますが、過湿には十分注意しましょう。真夏に強い西日が当たり、葉がしおれてしまった場合には夕方に水やりをすれば回復します。ヘチマに確実に果実をつけるためには、人工受粉をしましょう。
その為にはまず雄花を摘みとって花びらをむしり、花粉をむき出しにさせます。その花粉で雌花の柱頭を軽く撫でるだけで人工授粉は完了です。人工受粉は花が新鮮な午前9時ごろまでには終わらせてください。1株の果実を15個程度に抑えることで、優秀なヘチマが育ちます。
増やし方や害虫について
まず「摘心(てきしん)」について簡単に説明させてもらうと、多くの植物は茎の先端部分は勢いよく伸び、株の下の部分ほど芽が出にくいという頂芽優勢(ちょうがゆうせい)という性質をもっています。ですので自然のまま放っておくと、
先端の茎だけがひょろひょろと伸びてバランスが悪くなってしまうこともあります。そこで若い芽のうちに先端を摘み取る「摘心」を行ないます。摘心を行うとわき芽の発達が盛んになるのです。蔓物用ネットを利用して緑のカーテンを作る場合は、定植時に摘心し、
わき芽(子づる)を発生させてネットに絡ませていきます。イメージとしては「横方向への成長」を助けてあげる感じです。子づるが増えたらさらに摘心をして孫づるを増やし、つるをネットにからませながら、伸びる方向を調整していきます。
棚仕立ての場合では、親づるを早く棚上に届かせるために「上方向への成長」を助けてあげます。親づるが棚上に届くまでは、各節から出るわき芽を掻き取っていきます。親づるが棚上に届いたら、芽先を摘心して子づるを3~4本伸ばし、つるを棚にからませながら固定していきます。
ヘチマは病害に強い作物ですが、つる割病は農薬では防除できないので、込み合ったつるがあれば選定し、風通しのよい栽培環境で発生を予防します。日照と風通しが良くなれば、べと病や斑点病なども発生しづらくなります。
同じウリ科の植物を植えた土に翌年ヘチマを植えると、生育不良、病害虫の発生、原因不明な枯死等の「連作障害」を起こしやすいです。ですので前年にウリ科植物を植えた土には植えないことが大切です。プランターなどで土をすべて入れ替える場合は連作障害の心配はありません。
ナーベラー(ヘチマ)の歴史
ヘチマ(学名:Luffa cylindrica (L.) Roem)はインド原産のウリ科の1年草です。ヘチマの歴史は大変古く、インドを中心とした熱帯アジアが生息地とされ、紀元前には既に栽培されていたようです。中国から琉球王国へと伝わり、そこから日本に伝わって来たのは江戸時代だと言われています。
ヘチマはタワシとしては勿論のこと、幼果は野菜として利用し、ツルから採取したヘチマ水は咳止めやむくみ・利尿に効く飲み薬として、塗れば汗疹(あせも)、あかぎれ、日焼け肌の手当てにも効く美人水として重宝されてきました。
最近は自然派化粧品店などでしかお目に掛かれなくなったヘチマタワシですが、ヘチマ水を利用した化粧水の方はいまだに根強い人気で、現在も20を越えるブランドの化粧水が販売されています。ヘチマに含まれるサポニンに抗炎症作用や細胞の活性化を促す作用があるようです。
ヘチマ水は自宅でも簡単につくれますので、ヘチマ栽培の楽しみのひとつなるでしょう。日本でヘチマを野菜として食べている地域は沖縄と九州の一部のようです。沖縄ではヘチマを「ナーベラー」とよび、豚肉と一緒に味噌で炒め煮にした「ナーベラーンブシー」が定番の一品です。
皮を剥いて1cmほどの厚さに切ったナーベラーをフライパンでじっくり焼き、ナーベラーからトロミのある汁が出てきたら味噌を足して炒め煮にしていきます。皆さんが知ってる野菜の中では茄子が一番近い食味かも?と思いますが、茄子ほど柔らか過ぎないのにトロミもあり、1度食べるとクセになる美味しさです。
ナーベラー(ヘチマ)の特徴
低温・多湿・乾燥が苦手とされますが、強健で育てやすい植物です。肥沃な土地に高温の条件が加わると、盛んに分枝するようになり、日照が増えるほど果実が大きく育つ生育旺盛な植物です。生育に適した温度は25度から30度とウリ科の中でも高い方です。
つる性の植物なので、つるで他のものに巻きつきながら成長していきます。黄色い8cmほどの花には、雄花と雌花があります。ヘチマは、ひとつの株の中に雄花と雌花が混在する雌雄異花(しゆういか)で、同じ株の中での受粉が可能です。
花の付け根がキュウリ状に膨らんでいる方がメスである雌花で、これが受粉を経てヘチマの実になっていきます。花の咲き始めは雄花ばかりが咲くので心配になりますが、だんだん雌雄両方の花が咲くようになってくるので安心してください。
雌花の登場を待ち焦がれる形になる雄花たちですが、その寿命はわずか一日しかなく、次の日には花は落ちてしまいます。キュウリのような形をした細長い果実は、幼果は食用にし、成熟して繊維質が発達した果実はタワシに利用されます。人間が収穫せずにそのままにしておくと、やがて果実は乾燥し、
自然とタワシに近い状態へと変化していきます。するとある日果実の頭が破け、繊維の中にとどまっていた種が、果実が風で揺れるたびにひとつふたつと飛ばされていきます。なるべく真下に落とさず、果実の揺れに合わせて種を飛ばすことで、少しでも遠くへ分布していこうとする種の戦略が見て取れます。
-

-
ヘチマの育て方
熱帯アジアを生息地とするインド原産の植物です。日本には中国を通して江戸時代に伝わったと言われています。ヘチマは元々、果実...
-

-
ユーチャリスの育て方
ユーチャリスという名前はギリシア語でかなり目を惹く、という意味があります。日本では、ギボウシズイセンという別名もでも呼ば...
-

-
エリアの育て方
特徴としては、ラン科の植物いなります。開花時期としては春から夏で、草丈は40センチぐらいになることがあります。日本が原産...
-

-
スイセンの育て方
スイセン、漢字で書くと水仙。この植物は、ヒガンバナ科(旧分類だとユリ科)スイセン属の多年草です。地中海沿岸やスペイン、ポ...
-

-
トキソウの育て方
ラン科トキソウ属の山野草です。和名は朱鷺草(トキソウ)で、別名には朱鷺蘭(トキラン)などがあります。日本の本州や北海道を...
-

-
コエビソウの育て方
コエビソウはメキシコを原産とする植物です。キツネノマゴ科キツネノマゴ属の植物で、常緑の多年草でもあります。低木ではありま...
-

-
ミヤマホタルカズラの育て方
ミヤマホタルカズラはヨーロッパの南西部、フランス西部からスペイン、ポルトガルなどを生息地とする常緑低木です。もともと日本...
-

-
フジバカマの育て方
フジバカマはキク科の植物で、キク科の祖先は3,500万年前に南米に現れたと考えられています。人類が地上に現れるよりもずっ...
-

-
アングレカムの育て方
アングレカムはマダガスカル原産のランの仲間です。マダガスカル島と熱帯アフリカを生息地とし、およそ200の種類があります。...
-

-
ナツツバキの育て方
ナツツバキの原産地は日本で、主な生息地は本州から九州にかけての山の中です。ナツツバキはシャラ、あるいは沙羅の木として寺院...




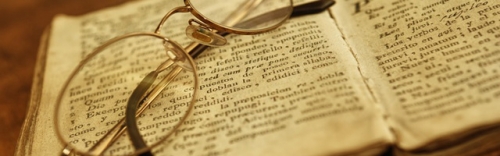





ヘチマ(学名:Luffa cylindrica (L.) Roem)はインド原産のウリ科の1年草です。ヘチマの歴史は大変古く、インドを中心とした熱帯アジアが生息地とされ、紀元前には既に栽培されていたようです。