センリョウの育て方

センリョウの育て方
冬に赤や黄色のつややかな丸い実をつけるセンリョウは、マンリョウと並んでお正月の飾りに欠かすことのできない縁起木の一つです。日本では関東から南の地域に生息し、常緑性の低木で、半日陰の場所に自生していることの多い樹です。
センリョウの花言葉は利益、裕福、富、財産、恵まれた才能などがあり、そうしたことからも縁起が良くお正月飾りに欠かせない存在となっているとも言われています。お正月には切り花の方がよく出回り、丸くつややかな赤い実がとてもきれいで、
とてもおめでたい印象を受けるお正月の花です。切り花の時には水揚げがあまり良くないので、湯上げをしてしっかりと水の上がったものを使うようにします。丁寧に湯上げをして飾っておけばかなり長い間きれいでいてくれます。
センリョウは野生のものは常緑の広葉樹林の下など、一年を通して直射日光ではなく薄日の当たるような場所に自生しています。日差しが強すぎると葉が黄色に変色して生育が悪くなったり、枝枯れしてしまうこともあるので、植える時には一年を通して半日陰になるような場所が向いています。
暗い日陰でも生長することはできるのですが、極端に実の付が悪くなります。もともと暖かい地方の植物なので耐寒性は低く、地植えする場合には東北南部から関東から南の地方が適しています。それ以北の地方では鉢植えで栽培し、
冬は霜や寒風などを避けられるような場所に移動させるような育て方をするようにします。霜や寒風なども、強い直射日光と同じように枝枯れを起こす原因になり、さらに乾いた寒風は花芽まで枯らしてしまうことがあり、翌年に実が付かなくなることもあります。
センリョウの植え付けと増やし方
センリョウは腐葉土のような腐植質のたっぷりと含まれた適度に湿気のある土を好み、乾いた土を嫌います。鉢植えにするときには赤玉土と腐葉土を混ぜた土を使用するようにします。植えつけるのに適しているのは、温かくなってくる5月か、
あるいは真夏の暑さの和らぐ9月から10月の中旬ごろです。地植えにする場合は、必ず植える場所に腐葉土や堆肥などをたっぷりと混ぜておくようにします。鉢植えにするときは、新芽が地面から伸びてこなくなると、
鉢の中がいっぱいになってしまっている可能性が高いので、そうなったら一回り大きなサイズの鉢に植え替えるようにします。植え替えに適しているのは3月から4月ごろです。
増やすには挿し木でも種付けでもどちらでも増やすことができます。
挿し木で増やすのに適しているのは5月から6月ごろです。枝を2から3節の所で切り、先端の葉4枚程度を残して、下の部分の葉は取り除きます。残した4枚の葉も大きすぎる時は先端部分を3分の1ほど切り取り、葉のサイズをコンパクトにすることで、余計な水分の放出を抑えます。
一時間程度水を吸わせてから、赤玉土を入れた鉢にさします。鉢植えの場合は2年に1回程度を目安にして、一回り大きな鉢に植え替えるようにします。地下の茎から盛んに芽が出て株が大きく成長するので、大きな鉢に植え替えをしたくないときには、
ハサミで地価の茎を2つから3つに切り分け、元と同じ大きさの鉢に植え付けるようにします。種付けで増やすときには熟した果実を取って果肉を取り除き、土に蒔くようにします。種は乾燥すると発芽能力が失われてしまうので、赤玉土などにすぐにまくようにします。
種付けの場合には芽が出るまで3か月から4か月程度かかるので、種をまいてからは乾かさないように管理することを心がけます。種付けをしてから、順調に育てば3年ほど経過すると実をつける株に成長します。種付けに適しているのは3月ごろです。
剪定方法などその他の注意点
剪定など3年以上たった古い枝や細い枝などには花が付かず実もつかなくなるので、3月になったら地際から剪定します。センリョウは地際からたくさんの枝を出す株立ちになりますが、ほとんど枝分かれすることはなくまっすぐに、
伸びていくためそのまま放っておいても樹形がひどく乱れることは少なく、剪定はそれほど必要ありません。ただし、枝が茂りすぎると株の風通しが悪くなり、根元が蒸れて葉を落としてしまうことがあるので、枝数が多くなりすぎた場合は切り詰めて枝数を減らすようにします。
この作業は12月から1月くらいの頃に、実がなっている枝を地面ギリギリのところで切り落とし、まだ実のついていない若い枝を残すようにしていくのが基本です。切り取った実のなっている枝は花瓶に活けたり正月飾り用に利用することができます。センリョウは病害がみられることはほとんどありませんが、
根や茎が黒変して、腐って枯死する立枯病に侵されることがあります。立枯れ病にかかった株から土壌を伝って病気が感染するので、羅病した株は抜き取って廃棄し、病気の発生した場所には植えないように注意します。害虫の被害は特にありません。
センリョウの歴史
センリョウは日本や中国、台湾、朝鮮半島、インド、マレーシアなどが原産の、センリョウ科センリョウ属の常緑性の低木です。葉は長さが10センチメートルほどの長楕円形で、縁の部分には鋸のような形のぎざぎざがあります。葉の色は濃い緑色で、葉の表面にはつやがあります。茎の先端部分に対生する2枚の葉の間に赤や黄色の実をつけます。
お正月が近づくと、センリョウやマンリョウなどの縁起木がホームセンターなどの店先に並ぶようにあります。同じように百両と呼ばれるカラタチバナ、ジュウリョウと呼ばれるヤブコウジ、
一両と呼ばれるアリドオシなども、年末からお正月にかけて店先に並ぶようになります。マンリョウは実を下げるようにして付けるのに対し、センリョウは赤い実を上向きにつけるのが特徴です。中国名で百両金と呼ばれるカラタチバナよりも大型であることからセンリョウと呼ばれるようになったと言われています。
センリョウの特徴
花の少ない冬の時期に丸い美しい果実をつけるセンリョウはお正月の縁起物として高い人気があります。センリョウはマンリョウやヒャクリョウなどと同じ仲間だと思われがちですが、センリョウはセンリョウ科の常緑の低木で、ヒトリシズカヤフタリシズカなどと同じ仲間の植物です。
一方マンリョウやヒャクリョウはサクラソウ科の常緑低木なので、センリョウとは違う仲間ということになります。年末からお正月にかけて鉢植えで様々なものが販売されているのを見かけますが、関東地方よりも西では、庭植えで栽培することもできます。
日本では主に関東より南から沖縄までが生息地で、朝鮮半島から中国インドなど広い範囲に分布しています。常緑樹の根元のような、一年を通して直射日光の当たらないような半日陰の場所に自生していることが多い植物です。
6月から7月ごろになると茎の頂点からまばらに花茎を出して、黄緑色の小花をたくさんつけます。その花には花びらが無く、あまり目立たない花で、花粉が風で運ばれてくる風媒花です。そしてその後、直径5ミリメートルほどの丸い果実を茎の頂点の部分にまとまって付、秋の終わりには鮮やかな赤色に色づきます。
十字方向に伸びる濃い緑色をしたぎざぎざの葉っぱと、つややかな美しい赤い果実とのバランスや色合いのコントラストがとても美しい花木です。また、真赤な実ではなく、オレンジ色っぽい黄色の実が付くキミノセンリョウという種類もあります。
庭木の育て方や色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も参考になります♪
タイトル:カラタチバナの育て方
タイトル:ヤマブキの育て方
タイトル:ボケの育て方
タイトル:サツキの育て方
-

-
ミズアオイの育て方
かつてはこのように水辺に育っている植物を水菜ということで盛んに食べていたそうで、万葉集の歌では、春日野に、煙立つ見ゆ、娘...
-

-
ラバテラの育て方
ラバテラは原産地が南ヨーロッパ、北アフリカの植物です。アオイ科ラバテラ属の総称になります。一年草になり、日本には明治に渡...
-

-
アークトチスの育て方
アークトチスはキク科の可愛らしい植物です。とてもかわいらしく可憐な雰囲気のある花ですが、キク科という事もありとても身近に...
-

-
三尺ササゲの育て方
三尺ササゲは別名ジュウロクササゲ、長ササゲともよばれるマメ科ササゲ属ササゲの亜種で見た目はインゲンのようですが別の種類に...
-

-
アレカヤシ(Dypsis lutescens)の育て方
アレカヤシという観葉植物をご存知でしょうか。園芸店などでもよく見かける人気のある植物です。一体どのような植物なのでしょう...
-

-
メキャベツの育て方
キャベツを小さくしたような形の”メキャベツ”。キャベツと同じアブナ科になります。キャベツの芽と勘違いする人もいますが、メ...
-

-
ソヨゴの育て方
ソヨゴはモチノキ科モチノキ属の常緑小高木です。原産地は日本、及び中国、台湾のアジア圏になります。背丈は1.5〜3メートル...
-

-
ストレプトカーパスの育て方
イワタバコ科のストレプトカルペラ亜属は、セントポーリアも有名ですが、その次に有名とも言われています。セントポーリアは、東...
-

-
リンゴの育て方
リンゴの特徴として、種類はバラ目、バラ科、サクラ亜科になります。確かに花を見るとサクラとよく似ています。可愛らしい小さい...
-

-
シペラスの育て方
シペラスは、カヤツリグサ科カヤツリグザ(シぺラス)属に分類される、常緑多年草(非耐寒性多年草)です。別名パピルス、カミヤ...




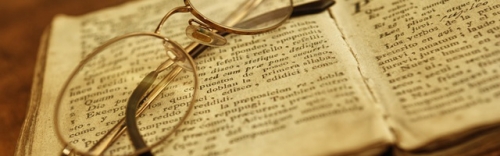





センリョウは日本や中国、台湾、朝鮮半島、インド、マレーシアなどが原産の、センリョウ科センリョウ属の常緑性の低木です。